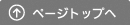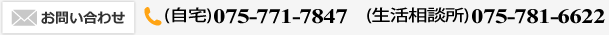(更新日:2012年10月2日)
動画コーナー
議員活動報告動画 「まちこわしSTOP! 子どもたちに、美しい京都のまちを」 (2012年)
京都で新たな景観論争〜三条京阪の開発どう見る~2024年12月26日京都市会まちづくり委員会で質疑しました
2007年に策定された京都市・新景観政策で
重要な位置をしめる鴨川沿いの高さ規制などを
緩和を求める開発構想を京阪ホールディングスが提案。
京都市議会まちづくり委員会で日本共産党のとがし豊市議が追及。
現行の規制の枠内で開発すべきだと指摘。
京都市は規制緩和を受け入れるかどうかの適否は未定と答弁。
((((( 以下、文字お越し )))))
とがし委員:京都市三条駅周辺地域の開発についてお聞きします。京阪ホールディングス株式会社が12月16日に提出した三条駅周辺地域に受ける開発構想についてお聞きをいたします。高さ規制20mのところに、高さ25m東屋含むと29mの建物が建設されようとしております。私はこれ重大な問題含むという風に思います。そこでまず確認したいのが、この三条駅周辺の規制の歴史的経過です。2007年の新景観政策の導入前にはこの三条駅周辺エリアを含む鴨川の東側のエリアはその多くが20m規制でした。新景観政策によって鴨川沿いは12mにして、鴨川から少し離れたところからは15mへダウンゾーニングされました。
ただし、この三条京阪の当該地だけは20mの規制が維持をされました。従って当該地域周辺では現状では20m程度の建物も多数存在いたしますけれども、数十年かけて15mの高さに揃っていくと。その意味では20m規制が維持されている現状においても特別な扱いを受けているという風に見るべきという風に思うんですが、この歴史的な経過についてはいかがでしょうか。
都市計画担当部長:当該地については三条の駅前広場があるということで、交通結節点でもありまして、東山方向の観光の窓口でもあると。そういった交通の結節点ということでポテンシャルが高いという部分で、一定高さについては20mにしているという風な背景があるものと考えております。
とがし委員:従ってですね、20mの規制っていうことで、そこはやっぱりそういう範囲で開発をすべしということで、そういう高さを継続したという重要な意味合いがあるわけです。ところが今回のそういう意味で特別の処遇されたはずのこの20mの規制でも満足できないと言って都市再生緊急整備地域指定を受けての都市再生特別地区の提案を予定しているとして、この規制を取り払って塔屋を含む29mの建築物を建てようとしてると。こんなことを許していたら我も我もと規制緩和を求める動きになってしまうんじゃないでしょうか。とりわけ新景観政策でも特別の位置付けを持つ鴨川沿いでの規制緩和は、新景観政策を足元から突きしてくことになるという風に考えます。また用途としては、ホテル及び商業施設ということなんですけれども、京都市の受け入れられる観光客の数がオーバーキャパシティとなってという下で、観光地がオーバーキャパシティとなってるという下で、さらに規制緩和してまでホテルを建設するというのは本当に適切なのか。高さ規制の枠内で、今の20Mの高さ規制の枠内での事業を進めていただくことが妥当と考えますが、いかがでしょうか。
都市政策担当部長:三条京阪駅周辺につきましては祇園であるとか、東山・岡崎エリアに近い都心の交通結節点でありながら、現状で言いますと、低未利用地が複数あるなどポテンシャルを活かせていないという状況にございます。このため、このエリアが活性化をすることで本市全体でありますとか、当該地域が活性化することにつながるという風に考えております。また、現在一部のエリアや経路に集中をしております人流というものが、新しいエリアが開発をされるということで分散をされるということで、混雑の緩和にも寄与するという風にも考えてございます。現在のところ、具体的な計画の内容というものが分かりませんので、都市再生特別地区を定めるかとか、また規制の緩和をするかどうか、ということにつきましては、本市としてはまだ判断できない状況にございます。今後具体的な計画内容というものが分かりましたら、その内容を踏まえまして、都市計画の手続きの中などで適否を判断していきたいという風に考えてございます。
とがし委員:現時点では都市再生特別地区を指定するかどうかはまだ判断できてないという話でした。で、国においては12月13日に政令が改正されて、この三条駅周辺では都市再生緊急整備地域と指定されたわけなんですけれども、あの事前の協議の状況はどうだったのか。今回は京阪ホーリングにおいては、ちょっとこの開発構想を見る限りで言うと高さ規制緩和だけを利用されるという書きぶりかと思ったんですけも、他の規制緩和や財政税制上の優遇とか考えられているのか。事前協議の中身の状況は今どうなんでしょうか。
都市政策担当部長:現状におきまして、まだ京阪ホールディングさんから開発構想届けが出されたのみということで、一般論として様々この支援メニューに関する相談というものはございましたけども、繰り返しになりますけども、具体的な計画内容とかそういったご相談についてはまだされておりませんので、内容については当方では把握してございません。
とがし委員:枠組としては事前協議があるものだという風に思ってるんですけども、私は是非、この高さ規制の枠の中で事業を考えていただくように、京都市としも強く指導していただきたいという風に思いますし、この地区の指定とか別にする必要ないという風に思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。
#京都 #景観 #まちづくり #開発構想
#京阪ホールディングス #三条京阪 #都市再生緊急整備地域
(更新日:2025年01月03日)
COP29に向け京都市の地球温暖化対策について京都市長と討議〜2024年10月31日市長総括質疑①
人類は今、崖っぷち。#京都市 の #地球温暖化 対策の目標をひきあげ、全国の気候危機打開のたたかいの先頭に立つ役割を果たすように市長に提案。市長は「理想」とは思うが困難との認識を示すにとどまりました。
(更新日:2024年11月16日)
総選挙、いよいよ投票日へ
ぜひ、ご参考ください。
(更新日:2024年10月26日)
京都市GIGAスクール4年の総合的検証を、小学校へのデジタルテスト導入は一律押しつけせず教育現場の自主判断の尊重を
https://youtu.be/-MyesOX072Y?si=dT9BOwujcXFWFiRF&t=3999
とがし委員:よろしくお願いいたします。私からも教育DX推進について質疑します。今年度2024年度から2029年度までのえ22億2900万の 債務負担行為が設定をされますで予備16%分のパソコンを含む9万7000台総額54億円のうち国負担分を除く京都市負担 18億円と、京都市費負担としてACアダプター1億7000万円、フィルタリング対策2億4400万円との うちあけであります。今回かかる費用、全国どこでも同じように必要という風に考えられるわけですけども、国全体においてその本体の補助以外の3分の2以外の部分の財政措置はどのように講じられるのかということと、先ほど京都市にこの間の配備されてるパソコンですけれども2割ぐらい損耗してるという話があったんですけども、今回16%予備率という風にどのように評価されているんでしょうか。
担当部長:まず、残りの3分の1について、先ほど申しましたとおりこれまでは国の臨時交付金をいかして、全額実質国負担ということができましたけど、今回はこの1/3については地方財政措置の対処ということで地方財政の支援ということでございます。特定財源にはならないということで、実質的には本市の負担ということで、かなり財政的な負担もあり、今回はリース契約ということで負担の平準化ということを図っていきたいとこのように考えているとこでございます。それから、故障については約2割ということでございます。で、国の方で今回定められてます15%の考え方としましては、これまでの各自治体の故障の状況でありますとか、今回の各端末 それぞれのOSのですね、堅剛性を増してきているという状況も踏まえながら、国の方で15%と、その辺りを判断しながらされてきたものという風に考えております。国の方でも十分な予備機を各自治体の中で整備していくことということを、国も言っているところでございまして、国の考え方に基づきまして15%、今回整備をしていきたいに考えております。以上でございます。
とがし委員:1/3の京都市の負担分との兼ね合いにもあるのですけども、今度のパソコンを WindowsからiPadに変更されるということで、単価が4万5000円から 5万5000円ということで1万円引き上がる、と。この1/3っていうのは京 都市の負担という風になるわけなんですけども、そういったことをこの費用負担とか色々考えますと、実質京都市の負担も増えるわけなんで私自身で言ったらその分が例えば学校の先生の増員とかに使えるのであれば、そういうこととも含めて色々判断していく必要あるかなと思ったりするということ。この点はどうかっていうこと。あとで資料でお願いしたいんですけども、iPadに変更するという風にした根拠になる選定委員会ですかね、その中でどういうメンバーで選定されたのかということと、その選定で比較検証された中身があると思うので、それ分かりやすくした資料をお願いいたします。後でお諮りお願いします。それでなんですけども、端末にお金をかけるのか、学校の先生の配置増やすとか、サポートする先生増やすことにお金をかけるのかっていうことも含めた検討などはあったんでしょうか。
担当部長:まず4万5000円から 5万5000円に上がったっていうところにつきましてはやっぱり今回、様々な物価高騰等も踏まえながら、かなり各メーカーの方もギリギリの中で今回整備されているという風に聞いております。特にやっぱり先ほどからお話ありました故障率が非常に高いということで、どのメーカーも、今回かなり強度をましながら堅剛性を増してきたで、この間、それぞれその故障の対応に先生方も負担が増えてきたという状況もございます。故障が減ることによりまして教員の負担というところも減ってくると思いますので、より安心して利用できる環境っというのが、学校またご家庭の中でもあるかなと、このように思ってるところでございます。それから2点目、会議のメンバーについてでございますが、やはりGIGAの第1期の時には標準使用書に基づいてこの間進めてきたとこでございますが、例えば、実際に学校で使って見た時の使いやすさ、子どもたちの使いやすさであるとか、例えば端末が故障した時にすぐに取り替えられるのか、それから、繰り返し言ってますけど、端末の堅剛性、こうしたことっていうのは、実際に使ってみないと分からなかった。學校で実際に授業活動する中で分かってきたところはございます。こういったところが、特に学校の中でも問題になってきてるところでございまして、特に今回は実際に使ってる先生方にこの会議に参加していただきながら、より先生方が使いやすい環境、そして、子どもたちに教えやすい環境、そうした中でどの端末をどう使っていいのかということで、今回学校現場の先生方も中心に、今回、この会議に参画いただいて、その議論を重ねてきたとこでございます。以上でございます。
とがし委員:先ほどま総合支援学校で使って、なかなかうまくいってるんだという話あったんですけど、総合支援学校って結構、通常の学級と違って手厚いサポートの中でやられ るっていうことでちょっとやっぱり通常のクラスでたくさんの人数の中でやるのとちょっと事情が違うんじゃないかなと思うので、また資料を見させていただいて判断したいなと思うんですけど。あとですね、今回、GIGA端末、パソコンを更新するということで言いますと、この使い方っていうのは非常に重要な課題やと思ってます。今で言うですね、デジタルドリルが一律に導入されまして現場からは、学校単位とか、学年単位で購入するかどうか自主判断させてほしいっていう要望が出されております。教育効果考えると紙のドリルが必要だということから、保護者が二重に負担せざるを得ない状況があります。で、デジタルドリルを 使うか、紙のドリル使うかっていうのは現場が教育効果を考慮して選択できる ようにすべきであり、学校や学年あるいはクラスの教員の方針いかんにかかわりなく、一律にデジタルドリルなどのアプリの購入するやり方っていうのは改めるべきじゃないかという風に考えます。その点で、このGIGA端末、パソコンにおける学校におけるパソコンに、どこのソフトの運用も含めてお考えはどうでしょう か。
担当部長:学校面の端末の活用ということ、 デジタルドのことも含めてですけれども、まず先ほども人へのお金か端末のお金かみたいなお話もありましたけども、我々、先ほど井上先生やまた大津先生のご質問に答えましたが、1人1台端末があることで、例えば常に子どもたちが持っているということで、子どもたちがその自分の学びを高められると。動画を取って 自分でやりたい時に見直したりとか、例えば事例として書くことが苦手な子供どもってやっぱり普通学級にいるわけですけども、そうした子どもでも書かなくても自分の発音・発言を音声で取って、それを先生に提出 することでしっかりと自分の意見表明ができているとか。絵を書くのが苦手で観察、理科の観察苦手な子でも、例えば写真を取って記録を取ることで自分の好きな花の変化とかを見られるとか。これは1人1台しっかりあることによって、成し得ている教育効果でありますし、我々、今、自分たちの取り組みが100%行っているというまで申し上げませんけども、そうした学びの充実ということの端緒は確実に現れているという風に認識しております。それがつまり、子どもたちの学習権の保障だと 思ってますし、そこにしっかりと予算ご承いただきまして、より充実をしていきたいというのが我々の基本的な考えでございます。どうようなことでございまして、AIドリルにつきましても、全市一斉に導入することによって保護者負担もかなり廉価に抑えて導入していますし、子どもたちが家庭に持ち帰ったりとか、学校の休み時間とか、放課後とか、いろんな場面で使いたい時に使える。また、デジタルですので、紙と違いまして 例えば小学校6年生でも3年生とかの時のこう算数ちょっと分からへんなっていう時 に振り返って、それがまたできるとか。そういった学年を超えて常に端末にありますので、そういった学び直しでありますとかもできますし、さらにちょっと進んだ学年のことを見てみようかなっていうこともできると。それも1人1人の個に応じた学びの充実かなと思っておりますので、そうした意味でできる限り、同じ環境、保護者負担行っていただくこともありますけども、そうした効果として考えられる部分については同じ環境を整えて子どもたちに提供していきたいという風に考えてるのは基本的なところでございます。以上でございます。
とがし委員:過去の議論の中でも、紙に書いて計算したりとか、紙に書いて漢字を覚えるとかいうことも含めて、非常に大事だということで教育委員会の答弁の中でもやっぱりその紙のドリルというものの必要性を言われていて、現場でも紙のドリルっていうのは特に低学年なんか必要ですという話があるわけです。ただ現実には保護者は低学年であろうが高学年であろうがデジタルドリルっていうことで600円 でしたかね払わなければいけないで紙のドリルも600円払わなければいけないということで、やっぱりちょっとそれは二重の負担になっていて。ですから、やっぱり学年とかあるいは学校とかいう単位で、まとまった単位で判断できるようにすることができないもんかなという風に思うんですね。ですから、別に使う必要のないものを買う必要ないわけで、全市である程度の学年以上とか、あるいはある程度の学校が必要だって言ったら一応それはそれで、まとまって購入できると思うんで、事業者との交渉で余地があるんではないかという風に思います。
とがし委員:今回、新しい端末に切り替えるということなんですけれども、小学校のテストについても今後導入するパソコンによって試行するという風にお聞きしてるんですけど。低学年の子どもも含めて一律にパソコンで入力する方式でテストするのがほんまに適切なのかと大変危惧します。単に、学年のいかんに関わらず、学習の遅れのある子どもにとってはハードルが 非常に高くなるんじゃないかと。分からない問題、テストがあって、紙であればですね、バッと見て、「あっここわからへんけど、次、飛ばして答えよう」とで後 になって「ちょっと時間があるからここもといてみようかな」とか。「この漢字、思い出せへんかったけど、どうしようかなあ」「この漢字かな」って言って、最後の最後まで粘って子どもたちは答えるわけです。そういうことがあの紙のテストでは今実践されているわけなんですけども、デジタルだと非常にま操作慣れたらできるという風におっしゃるかもしれないけど、やはりそこは 非常にハードルが高いんではないかなという風に思うんですねで。その授業に使うだけじゃなくて、テストにまで使うっていうのは一体どうなのかなていうのは率直な疑問がありまして、現場の方からそういうお声を聞いています。懸念の声があがっています。この懸念についてはどうお考えでしょうか。
担当部長:テストをパソコンの端末でという、国の方も特に全国学力学習状況調査につきましては今後えまえCBT化と呼ばれてますけども、コンピューターベーステストということで移行していくという方向も示されておりますし、子どもたちには6年生でそういった全国調査も受けていくと、中学校で受けていくということになりますので、そうした段階ではしっかりと対応できるようなスキルについては身につつけるように取り組んでいきたいという風に考えております。で、それについてましてはその何年生からどうしていくのかということについては、当然、慣れもあると思いますし、必要なことについてはしっかり検証していきたいという風に考えております。また、先ほどデジタルドリルにつきましてもその書くことも含めて、書くことと、ご紹介がありましたけども、必ず全てを端末で、デジタルでということで取り組んでるわけでございません。大事なことは、子どもたちが、デジタルを活用するのがいいのか、それか、ノートなり手なり、教科書もこの紙の教科書しっかり調べるのがいいのか、インターネットで調べることがより深まるのかということを 自己決定していける力をしっかりつけていくということが非常に大切かと思います。そうした意味で必ずその紙か、デジタルか、その二者択一ではなくて、常にその1番有効な方法で学べるということを授業中でも実践して取り組みをこれをも進めていきたいと考えております。以上でございます。
とがし委員:今のお話を聞いてると全国学力 テストがデジタルのテストになっていくから、それが中学で実施されるから、それに備えてスキルを鍛えなければいけないというのは、おかしいんじゃないかと。率直に思います。その全国学力テストの目的っていうのは、その全国学力テストで点数を取ることが目的なんでしょうか。そんなんやったら別そんなテストいらないんじゃないですか。元々その一律テストよりは、学校の先生方が必要だと思ったテストをやって、自分たちがやった授業が定着してるんかどうか、と。でこどもたちに、どういう風になテストで自己点検してもらったらいいのかってことを、先生方が判断した 中身でやるのが1番いいと元々思ってるんですけど、今の話で言うと全国学力テストが デジタル化するからそれに合わせて京都の学校のテストをいつどこの学年からか分からんけれどもえデジタルに変えてくんだと。ちょっとその現場の実情とか、子どもたちの発達無視した議論じゃありませんか。
担当部長:全国学力学習状調査がCBT化するということは方向として決まっております。その中で、子どもたちがまずあのICTの 活用になれて、そうしたところもしっかりとご自分の力が発揮できるということをつけさせること非常に大切かと思います。そうすることによって、テストの結果を振りかえって、自分の到達条件を含めて確認ができるという風に考えております。そういった意味で何年生からどうするかていうのは今後ですけども、そういう全国のそういう調査に応じた対応も本市もしっかりと取り組んでいくことが必要かという風に考えているところでございます。以上でございます。
とがし委員:全国の学力テストに流されて京都市の教育を決めるんじゃなくて、京都市にいる子どもたちの実情に応じて学校の現場の先生が試行錯誤される、と。それを後押し、支えるのが皆さんのお仕事だというふに思うんです。
委員長:・・・・・(聞き取れず)
とがし委員:ええっと何でしたでしょう。
委員長:質疑、予算に関連して。
とがし委員:関連して質問させてもらいます。
とがし委員:こういう取り組みを前提に、今回のGIGA端末を導入するですけど、私はね、道具としてこんだけもう家に帰ったら、スマホとか、パソコンもいっぱいあってデジタルディバイスがそこら中に溢れてると社会でたらもう絶対それ触らなければいけないとそういう状況の中で、子どもたちがITCになれて、あるいは、そのリテラシを学ぶっていう非常に大事なことだと思います。しかし、それと、教育っていうのはまた別の議論だという風に思うんですね。ですから、やっぱり私はちょっとその辺で学力テストに合わせて京都の教育を変更するんじゃなくて、現場から考えていただきたい。このことを要望しておきます。
とがし委員:それと今回、眼科のお医者さんなんかのデータとか見解とか見てますと、外界の光が移る紙を見るのと、自ら発効する電子端末見るとでは目の負担が全然違うという指摘があります。デジタルデバイス見る時の姿勢も非常に重要だだという話も書かれておりました。であるいは、低学年であれば1日1.5時間で、高学年であれば1日2 時間以内に抑えた方がいいということも、私が読ましていただいた先生の文章に書かれておりました。で、今で現状で言いますとね、やっぱり子どもたちが学校から帰った後っていうのはやっぱりどうしてもテレビとかよりむしろインターネットとかあのそういうデジタル ディバイスと触れる時間が非常に長いので そういう社会の変容、子どもたちの生き方、暮らし方の変容ということを考えるとやっぱりその学校でもデジタルディバイスに触れる時間っていうのは 一定、発達の観点からあのどれくらいにするかっていう適正な時間を取るべきではないか思うんですけどこの点はいかがでしょうか。
担当部長:目のま影響についてでございますが、国の方でもこうした状況も踏まえながら、子どもたちの目の健康を守ための啓発資料等もされているとこでございまして、こうした資料を基づきながら、各保護者の方々にも、たとえば5家のルール、例として、部屋の明さに合わせて 端末の明るさを調整したり、正しい姿勢で目と端末の距離を例えば 30cm以上開けるとか、30分に1回は20秒以上ですねえ画面から目を離して、きるだけ遠くを見るなど、目を休めるということを推奨させていただいて、それに基づいて学校の中でも勧めさせていただいてるところでございます。またあの特に、深夜の利用等も気になるとこでございまして、例えば夜間の閲覧の制限を小学校ですと9時から 6時中学校でしたらえ10時から6時という形で、そういう形で制限させていただいて、目の健康にも配慮しながら取り組む進めさせていただいてるとこでございます。以上でございます。
とがし委員:デジタルディバイスを、やっぱり教室に持ち込む以上はやそういうちょっとその教育の専門家だけではなくて、そういう目とかあるいは身体についての専門家も含めた、しっかりとした検証がやっぱり必要だという風に思います。先ほど一定の総括の話ありましたけれどもそういうちょっと総合的な検証の場というのがあるのか、どうか。しっかりと今回の機種の更新を機にされたかと思うんですが、いかがでしょうか。
担当部長:今あの先ほど担当部長から申し上げましたの目の健康も含めて、そういう健康面の影響についても、会議ということではございませんけども、我の方、体育健康教育室の方でえしっかりと専門的な学校医の先生方の意見も聞きながら、学校指導課とも連携して 通知分を発出したりとかしておりますので、そうした部分は引き続き留意して取り組んでまいりたいという風に思っております。あと、重ねてになりますけども、端末を活用した国のデジタルによるテストでございますけども、テストはあくまでテストでございまして、我々でもデータ上で例えば様々な課題等が送付されてきて、それをデータ上で考えて返していくということはもう社会に出て当たり前の時代でございます。テストだからやるのでなくて子どもたちにも紙だけではなくて、デジタル上でも自分の意見をしっかり書いても課題を考えて発信できるという力をつけているという意味でも様々なツールでの取り組みと非常に大事かと思っていますので、我々の思いとしてしっかりと取り組んでいきたいという風に考えております。以上でございます。
とがし委 員:テストの時の子どもたちの心境なんかも私紹介をしながらお話ししました けどなかなか皆さんのところに届かないと思うんですが、是非皆さんも自分たちが子どもだった頃なんかも思い起こしながらそのテストっていうのはどういうものだったのかということを考えていただきたいという風に思います。で、それと体育建康室の方でしっかりと専門家の意見聞いて通達出しているから大丈夫だとおっしゃってますけど、やはり、私はやっぱりそういう教育委員会がセクションそれぞれバラバラで、なんかそれぞれにやってるんだっていうんではなくて、もうちょっと総合的にきっちりと検証する場を持たれた方がいいと。先ほどテストに対応しても、デジタルテストに対応、国のデジタルデジタル統一テストですかね学力テストに 対応しなければいけないから、デジタルのテストを子どもたちにやるんだって話なんかが飛び出してくるっていうのはそういう総合的な検討がないからそうなるんで、私やっぱりそういう子どもたちの発達という視点で子どもたちの健康という視点そして当然学びという視点ですねま総合的にきちんと是非専門家の意見とか子どもや保護者の意見とかも聞きながら、考える場を持っていただけたらという風に要望して、終わります。以上です。
担当部長:重ねてになりますけどもテストはテストのだけのためにあるのでなくて、テストは1つのきっかけですけども、今もう学校で 学んだことがどう社会中で課題になってる
のか。実生活に結び中で課題をどう解いていくのかっていうことの1つの自分の理解度を試すのがテストだと思います。先生あのテストを紙かデータかということでおっしゃっておられますけどもそれまさに テストをテストを問題解くということだに取れわられるのはないかと大変、失礼ですけども思っております。我々としては社会に出てから様々な形で子供たちが発信して課題を考えられる力をつけていくという ことでもいろんなツールの中でえそういった学びを自分の中に落とし込んでえ課題に向き合えるという力を育んでいきたいという風に考えておりますし、目のことにつきましては今我々の取り組みでしっかり大丈夫だということをなるように取り組んでおりますけれどもも、決して100%だと思っておりません。まだやはりデバイスによる目の影響っってのは国の調査においても、スマホ等が流行り出した10年前から非常に子どもたちの視力の低下が著しいということはあの発信されております。それは我々としもしっかり受け止めとれますし、そうした部分の中で学校の中でどういった時間 とか休憩時間とか含めて、子どもたちの健康も留意しながら取り組み を進めてまいりたいというふに考えております。以上でございます。
とがし委員:あの私言ったことをやっぱりちゃんと聞いて欲しいと思うんですよね。その現場から上がってきている声なんですね。現場の実情を踏まえて物事考えて欲しいと。全国のことでは全国で文部科学省がやる全国統一 学力テスト中心に物事を考えるんじゃなくて、学校の現場から物事を考えてえテストのあり方っていうのは、学校の現場の判断でやるようにしていただけたい。このこと を求めて終わっておき ます。
稲田教育長:とがし委員から全国学力テストに基づいて京都市教育委員会が教育のありようを変えてるとおっしゃってたのは、担当部長の答弁を曲解しされていると思います。あくまで、子どもたちに、今の社会に生きていく力を育むというのは私たちの使命でありまし、デジタル社会の中で子どもたちがどう生ていくために何をしなければならないかということで今の取り組みやってることでありまして、全国学力テストのために教育委員会が方針を決めているとのは全くの嘘という間違いでございますので、私としては抗議したいと思っております。以上で ございます。
とがし委員:なんか抗議っていうか、別に私は、そうじゃないんやったらそれでいいんですよ。学力テストに合わせてやってへんのだったらそれでいいんですよ。ただ先ほどの答弁がそういう風に聞こえる答弁されたので言っただけなんで、別にそうじゃないって言ってくれはったら別にそれでいいんです。それだけの話なんです。分かります。私は、現場からきちんとそうやって学校ごとで色々テストのあり方は判断させてほしいっていうことがあるわけやから、デジタルやりたいという学校があるかもしれない、学年があるかもしれないけど、紙で引き続きやりたいという学校がある、と。そういう多様な現場の教育のあり方っていうのを大事にして欲しいということを述べてるので。あの曲解でありませんしね、そういうことであれば問題だって質問してるわけなのでね。その辺ちょっと私の質問の趣旨しっかりと理解していただきたいと言って終わりたいと思います。以上です。
(更新日:2024年09月28日)
国道1号線・名神高速が豪雨で使えない時のための「バイパス道路」つくるって本気?~2024年8月22日まちづくり委員会
2024年8月22日京都市会まちづくり委員会
一般質問:国道1号線・9号線パイパスについて
質疑と答弁を文字起こししました。いったいどこにバイパスを通すのか?名神高速も1号線も通行止になるような豪雨が降る日に平常に通過できる道路をつくるなんて本当にできると思っているのでしょうか。正直、いくら地図をみても想像がつきません。私の討論だけでなく、自民党の議論もご紹介しております。ご参考にご覧ください。
とがし豊議員(共)
〇とがし委員:よろしくお願いいたします。国土1号線・9号線バイパスについて質疑したいと思います。国において近畿ブロック新広域道路交通計画が令和3年・2021年度に作策定されまして、その中で堀川通の地下バイパスや国道1号線・9号線バイパスっていうのは位置付けられております。我が党としては、これらの路線については不要不急の大型公共授業であることから、きっぱり反対をさせていただいているところでございます。今日の質疑では、この大津方面と京都を結ぶ国道1号線バイパスと、亀岡方面と京都を結ぶバイパスである9号線バイパスの計画についてお聞きしたいと思います。京都市として、この路線を推進をしようということで、国に対しても予算要望を先般されておりますけれども、こうした予算要望される根拠っていうのは何でしょうか。
⇒(答弁)建設企画部技術企画担当部長:国道1号バイパス・9号バイパスに関する要望の根拠ということでございます。こちらにつきましては、平成28年12月に国・京都府・京都市、また、学識経験者から構成されています将来道路ネットワーク研究会。これを立ち上げて、将来の京都市の発展にとって真に必要な道路のネットワークのあり方について広域的な視点から多様な意見を求めるということでやっております。その取りまとめの中で、平成30年1月に取りまとめておりますけれども、その中で、京都市と大津方面・亀岡方面を結ぶルートにつきましては災害に強い道路整備の必要性が高いというように結論付けられているというところでございます。こういったことに基づきまして、それ以降、国に対して実現に向けた要望をさしていただいてるというところでございます。以上でございます。
〇とがし委員:災害に強い道路とか交通ネットワークにしていかなければいけないと話でありますけれども、私は、この点について言いますと、災害っていうのはいろんな被害っていうのは想定されていく中で、優先的に本当に取り組むべき道路あるいは斜面対策とかも含めてですねえ、もっとあるんでないかという風にま思っております。で、それから、特にお聞きしたいのは、平成30年・2018年1月ということでありますけれども、6年前になるわけなんですけども、現時点に立った上でもう1度再検証が必要じゃないかっていう風に思うんですね。日本全体としては人口減少っていうのが非常に今急速に話題となっておりまして、若者もあの当時と比べても一層車離れが進んでいる、と。団塊世代も、すでに高齢期を迎える中でドライバー人口そのものも減少していくっていうことていうのが、今後、容易に創造がつくわけであります。ですから自動車で移動するっていうこと自身というものが、減ってくま傾向にあるんじゃないかと。同時に気候危機という事態に際して、今、運輸部門についてはモーダルシフトということで、より環境負荷の低い方向へと転換が求められてる中にあって、自動車による輸送というのは削減の対象になってくんではないかと。鉄道とかも含めて貨物とかも含めて転換していく必要性が出てきてるんじゃないか。そういう要素も含めてやっぱり京都市の道路交通も、あるいは、公共交通のあり方も含めた総合的な検討っていうのが今まさにこの時代だから、時期だからこそ、必要になってくるという風に 思うんですが、そういう中で、是非とも京都市における道路ネットワークの あり方を新たに再度検証し直す時期に来てるんではないかと考えますけど、この点はいかがでしょうか。
⇒(答弁) 建設企画部技術企画担当部長:道路ネットワークについての見直しということでございますけれども 、ちょっとあの具体的にお話しさせていただきましたら、国道1号につきましては、これまでから大雨が発生した時には通行止めが度々発生している状況でございます。例えば平成25年の9月なんかの大雨につきましては、名神高速道路も同時に止まった、と。非常にこれは社会的影響が大きかったというようなことを考えてございます。また国道9号も同様でございまして、9号線のみならず縦貫道も同時に止まった、そういった事例もございます。そういったことを踏まえましたら、この国道1号また国道9号につきましては、極めて重要な道路で必要であるという風に考えておりますので、こちらについては、引き続きしっかりと要望を進めて参りたい。そのように考えております。以上でございます。
〇とがし委員:9号線も止まる縦貫道も止まるっていうとんでもない大雨の、あるいは、いろんなとこで土砂災害が起こるような状態っていうのは、おそらくバイパス作っても同じ。同じようにそこも止まるってことになるわけなんで、その意味では、やはり私は逆に、そういう事態になった場合にどう対応するかっていうところで考えていく必要あるんじゃないかって。それが、それこそが災害に強いまちではないかという風に思っております。で、当然、今ある既存の道路網についてやはりしっかりと防災対策というのを徹底的に施していくってことが最優先課題であるという点は皆さんと一致するところであるという風に思います。 総合的な観点から、やはり気候危機という重大な人類的危機に立ち向かう上で社会全体の構造システム自体を改めていく必要があるということ。そういう点からやはり道路ネットワークについ て、あの道路ネットワーク単体ではなくて公共交通機関ともセットでやはり総合的に検討いるんじゃないかということでぜひ再度、こういう研究会以前立ち上げられたわけですけれども、 立ち上げていただいて、今の最新の知見を集中して取り組んでいただけたという風 に思います。私は先般、東京杉並区行きまして、東京都の都市計画道路で優先道路というところに指定されてるところも含めて、事業認可を受ける前のものについては杉並区として住民の皆さんにも集まっていただいて、それらの路線の必要性を検証するデザイン会議っていうものを立ち上げられるということで住民参加で道路ネットワークのあり方っていうのを暮らしの視点から再検証するということに取り組まれております。京都市でも道路のあり方について広く市民と議論する場も持っていただくことも要望いたしまして質疑終わります。ありがとうございました。
委員長:このに関連して他にございませんか。桜井副委員長。
さくらい泰広議員(自)
〇桜井副委員長:私の会派は1号線バイパス・9号線バイパス、そして、堀川通りの整備についてはもう早急に着工せなあかんという、そんな立場で質疑をさせていただきたいと思い ます。京都はもう間違いなく都市基盤の整備っていうのが遅れていると思いますね。その遅れている1つの原因としては、やっぱりあの過去28年間の革新府政の時代に公共事業と縁が薄かった。これも1つの 要因ではないかという風に考えています。よって、早急にこれ都市基盤の整備をするにあたって、特に今議論がありました京都市と大津方面やえ亀岡方面結ぶこの道路に加えて、堀川通りももう道路のネットワークの整備っていうのは、いわゆる物流などを支える、交通の円滑化そして今も部長の方から答弁ありましたけれども災害対策、かつて、その1号線と名神が止まってしまって滋賀県と京都のその行き来が切断されてしまって、確か平成25年ぐらいでしたですかね、あの時は本当にもう大変なことになったという風にもそういう記憶もありますし、これ早急にやらなあかんてのは京都市の未来のための投資やという風に私は思ってますし、あの先日、松井市長、記者会見をされてそこで松井市長、こうおっしゃってます。「街づくりのための戦略的な投資に力を入れる」とはっきりこ おっしゃってますんで、まさにこの道路整備であって、まちづくりのための戦略的な都市基盤の整備っていうのは、そこに当たるんじゃないかという風に思ってますね。 我が党としても先般、堀川通を早急に改善をしていくための議連立ち上げましたし、あの1号線についても東京で総会やって、市長も含めて国交省・財務省にも予防を活動行かれたで9線のもあの巨人化ということで議連立ち上がってます。あの今、こうやって京都市において遅れている都市基盤整備をしっかりとやらへんかった間違いなく将来市民生活であったりとか、あるいは京都市の産業活動に、私は大きな大きな支障をきたつという風に思いますから、一刻も早くこれは道路整備が実現するように本市と、あるいは大津市、志賀県、関係自治体とも連携しながら、引き続き国に対して強く要望していただきたいという風に思いますけれどもいかがでございますか。
⇒(答弁)建設企画部技術企画担当部長:ありがとうございます。まさに京都の未来のための投資ということで、しっかり取り込まなければならないという風に考えております。大津方面・亀岡方面に加えまして、堀川通についての機能強化ですね、こういったことについても道路ネットワークの整備、先生今ご案内いただきましたけども、交通の円滑化、防災上の話も含めて、非常に必要性の高いという風に認識しております。また、先ほど議連を立ち上げていただいたというようなことで、本当に議員連盟をはじめとする先生方のご支援・後押しと言いますか頂いたおかげで、今年度、近畿調整備局の方でで令和6年度の道路調査の見通しという広報 発表されておりますけれども、堀川通、国道1号これは大津京都間、 国道9号、京都亀岡間こちらについては、調査を実施していく路線としてえ付けられているというようなところでございます。これも本当に先生方の後押しもありながら、我々も要望してここまでたどり着いたんかなと思っております。今後も引き続き、関係自治体、しっかり連携を図りまして、要望活動など国への働きかけこれを強めてまいりたい。そのように思っておりますので、 引き続きのご支援どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。
(更新日:2024年09月06日)
コメ不足のおり農地をどんどんつぶす京都市政に待ったをかける質疑を行いました(2024年8月22日まちづくり委員会)
コメ不足が深刻さを増す2024年8月22日。京都市会まちづくり委員会において、向島国道1号線地区の広大な農地をつぶす計画に待ったをかけるべく一般質問を行いました。農業を切り捨てていく自民党農政を忠実に実行する京都市都市計画行政を改めなければなりません。ぜひ、以下の質疑・答弁をご覧ください。
(以下、youtubeの字幕情報をもとに、とがしの責任で修正・文字起こし)
〇とがし委員:おはようございますよろしくお願いいたします。それでは私からは向島国道1号周辺地区における地区計画の見直しについてお聞きをいたします。この見直しの対象となっております向島国道1号周辺地区を含む宇治川の南側一帯っていうのは市街化調整区域に指定をされております。この当該地が市街化調整区域に指定された経過と根拠は何だったでしょうか。
(答弁)都市計画担当部長:調整区域に指定された経過は昭和年12 月28日に線引制度というものがございまして、市街化区域と調整区域に分けるということで、その時に市街化調整区域に指定されたと。当時は市街化を抑制する区域という風な観点でこの当該地についても含めるという風な形で指定されたものと推測されます。以上です。
〇とがし委員:ご承知の通り都市計画法は「国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的というにされておりまして、「都市計画は農林業との健全な調和図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を加工すべきこと、並びに、このためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと」を基本理念とされております。この都市計画法でいう「農林漁業との健全な調和」を具体的に担保する措置として、市街化区域と市街化調整区域という区別があるんじゃないかという風に思うんですね。そして、この当該地というのは市街化を抑制するべき地域ということで「市街化調整区域」として指定をされてきて、そういう土地利用のあり方が引き継がれてきたからこそ、広大な農地として守られてきたのではないかという風に考えますが、この点いかがでしょうか。
(答弁)都市計画担当部長:都市計画法ですけども、市街化調整区域というのは 原則、基本理念としては市街化を抑制する「区」となっておりますけども、だからといって、現状凍結であるとか、あるいは、未来永劫農地を保全するというようなものではございません。本件のように地域未来投資促に基づいて重点促進地区を指定して、そういったところで地区経画を収める前場合など、一定のそういった場合には開発行為は認められるものでございます。このために市街化調整区域であるということを持って、イコール農地を保全するエリアという わけではございません。また都市の成長戦略を実現するためには企業立地の促進が必要不可欠でございまして、道路のインターチェンジに近接するなどの立地優れた土地においては、農地などの周辺環境とも調和を図りながら産業用地の創出を図ることは、京都市の都市計画マスタープランの方にも書いているものでございまして、本市のまちづくりの方針とも合致するものでございます。以上です。
〇とがし委員:私は、その前段で、向島であれだけ広大な農地、Googleマップっという非常に便利なもんで上空から見れますけども、現地行っても農地が広がってることがよう分かりますけども、上から見たら余計とよう分かるんですけども、あれだけの広大な農地が、しっかりとまとまった農地として守られてきた背景には市街化調整区域という都市計画の制度があったんではないかっていうことなんですけど、現状のことでお聞きしてるんですがこの点はいかがです。
(答弁)都市計画担当部長:現状がどうかと言えば、おっしゃる通り、グループマプで見れば、農地が広がっていることは事実でございます。
〇とがし委員:やはり私は、その都市計画っていうものが、その法によって市街化を抑制して、しかも、それは農業との調和を図るという観点から、ここからは市街化するけれども、ここからは農業とか林業を守ってきましょうよというエリアとして区分していることによって、農業がまもられてきたという風に思います。今、日本各地で農地を潰して物流倉庫を作るという動きが強まっておりますが、このような形で全国的に農地を解体していくっていう動きは、日本の食料自給率をさらに低めるものであり時代の要請に逆行してるんじゃないかという風に思います。米不足の話も出ていますけれども、世界的にも食料危機って言われる中で、そういう主食のコメさえ守れなくてどうするのかという風に思ったりするわけでございます。開発資本にとっては格安な土地だから農地を潰したいという衝動にかられる、大きい土地だから潰したいという衝動にかかられるんだろうけども、その土地はなぜ大きいのかと言ったら、やっぱり大きくまとまった土地があってこそ、農業っていうのは、効率的により良い作物を得ることができるわけですので、そういう農業の特性から考えて、ああいうまとまった広大な農地というのは非常に守らなければならないものだ、と。ですからあの土地っていうのは、やっぱり日本の食を守る重要な砦であるという認識を忘れてもらったら困るという風に思うんです。その意味では私はその市街化調整区域においては、農業は重要な産業としてもっと積極的に保護するという姿勢に立つべきだという風に考えます。先ほどの答弁では、産業化していく、農業以外の工業的なところにとか、物流とかにしていくんだっていう趣旨で発言されてると思いますけれど、そちらが大事だという風に言われるけど、あの地域においてはやはりそれよりもより農業の方が大事だという風に位置づけるべきだという風に考えるんですが、この点はいかがでしょうか。
(答弁)都市計画担当部長:農業政策については都市計画局の所管外になりますので、コメントについては控えますけども、状況としてはこの土地につきましては、小水路が走っておりまして、そこから南については農業振興地域に指定されておりますけども、この北側については、農業振興地域外ということで手続きされています。そこを今回指定した状況でございます。都市計画においては、市街化調整区域において、繰り返しになりますけども、何も作ったらダメというわけではなしに、周辺の土地利用状況に配慮しながら、例えば、市街化区域に置くことが望ましくない家屋であるとか、市化調整区域にお住まいの方が利用するような公共施設とか利便施設、また、今回のような地区計画をうってそこで一定そういった要綱に基づいて開発を行っていく、と。その内容について都市計画審議会で認めもの、こういったものについては、一定開発を認めるということで、周辺との土地利用との調整を図りながら整備を進めるということは可能というような手法となっております。
〇とがし委員:法の枠組としてできるから当然されてるんだと思うんですけど、ただですね、やはりあの都市計画っていうものは可能だったら何でもやっていいもんではなくて、理念を持たなければいけないし、その理念の骨格に「農林漁業との健全な調和」っていうのが書かれているわけなので、この理念が京都市の都市計画からから失っているんじゃないかっていうことで、都市計画の所管されているわけですから、それで私お聞きしておりますので、そういう「農林漁業との健全な調和」という視点というのをもう1度ですね位置づけ直していただきたいという風に思います。その上で、具体的な話に入るんですけれども、当該地に建設予定の物流倉庫っていうのは、どのような建物になろうとしているのか。周辺農地への影響ですね、日陰が落ちたりしないのかということだとか、風の影響はどうかとか、あるいは農地には自然のダムとしての機能など多面的な役割があるわけでございますが、この役割が喪失されることになる場合の対応などはどうされようとしているのか、その辺の点について、あるいは、当然基盤整備とかを税金を使ってやることになるのではないかとかいうことも含めて、その辺りの現状について、示すことができる範囲でご説明お願いします。
(答弁)都市計画担当部長:細かい事業計画については事業者が考案中ということで、今、都市計画の縦覧をしておりますので、その内容から言いますと、建物の高さは35mということで、階数ですねは4階建てを想定されております。内容については物流倉庫というような形になっております。周辺の影響ということで、日陰については今回については敷地の北側と東側に日陰が落ちるということで、そちらについては今、事業者の方でその説明を所有者に入っておりまして、特に反対意見はないということを聞いております。その他、周辺の農地に与える影響については、本市の方でも適切に指導されてるということを伺っております。以上です。
〇とがし委員:先ほどもう1つ質問した中で、農地の補水というか、自然のダムとしての 機能、多面的な役割ですね、これへの対応っていうのはどうなっているでしょうか。
(答弁)都市計画担当部長:それについても、当局の所管外でございますけども そういったことも含めて、しっかりと周辺の農地で今後も農業が継続できるよう指導行っております。
〇とがし委員:頂いた資料で見てると雨水貯留施設などが作られてるわけですけども、この辺でどういう風に貯留して、それから現状の水路とか周辺の農業への影響はないのかということも含めてお聞きしたんですけど、いかがですか。
(答弁)都市計画担当部長:調整地のことでしょうか。当該地につきましては雨水貯留施設ということで、まず雨水については、こちらの方ですね、調理施設を作って大雨が降った場合にここに水を溜める形で計画されております。汚水については、この道路中央の方に汚水管を通しまして、施設の中に浄化層を設けて水を綺麗にして、その後、汚水については水を綺麗にしてこの道路に流すということでしっかりと周辺環境に影響がでないように対応されております。
〇とがし委員:そうすると、事業者の方でその雨水とか汚水の処理とか、主流とかも含めて全部責任を持ってやられるという理解でよろしいんでしょうか。
(答弁)都市計画担当部長:もちろん、こういった施設を設ける場合には監督庁がありますんで、監督部署の方でしっかりと内容を協議しながら進めていっております。
とがし委員:具体的に、縦覧の中で色々意見も出るかという風に思いますけれども、引き続き都市計画審議会だとか、あるいは条例とかにもなって出てくると思いますので、改めてその場で引き続き議論させていただきたいと思います。終わります。
(更新日:2024年08月31日)
聖護院・黒谷の景観を守る会の陳情についての審査(陳情第1978号マンション建設の指導について)全文字お越し
2024年7月10日京都市会まちづくり委員会
陳情第1978号マンション建設の指導について(聖護院円頓美町)
陳情についての説明(都市景観部長)
それでは陳情第1978号マンション建設の指導(左京区聖護院円頓美町)につきましてご説明申し上げます。まずお手元の陳情文書表をご覧ください。陳情者につきましては記載の通りでございます。次に要旨でございます。東山の山並みを背景とした聖護院門跡から黒谷に至る兼官を守りたいとの趣旨で令和6年2月21日に京都市眺望景観創生条例第 7条第1項に基づき眺望景観保全地域の指定を求める提案書が提出されています。具体的には聖護院門跡南西角の路上、春日北通りから東南方向を眺めた際に聖護院円頓美町の建築物等が突出して東山の山並みの眺望を遮らないように眺望景観保全地域に指定することが提案されているものです。陳情事項は今回の市民提案による視点場を一刻も早く承認してマンション建設の指導に行かすよう願うものです。
次に条例の基点についてご説明いたします。陳情にあります。提案は条例第7条第1項の「何人も京都の優れた眺望景観の創生にふさわしいと思慮する一団地の土地の区域について眺望景観保全地域として指定することを提案することができるという規定に基づくものです。7条第2項で市長は提案内容が京都の優れた眺望景観の創生にふさわしいものであると認めた時は提案にかかる区域を眺望景観保全地域として指定することができるとしています。続きまして提案に対する検討状況についてご説明いたします。本市ではこの市民提案を受けて以降提案内容が京都の優れた眺望景観の創生にふさわしいものであるかについて検討を進めております。眺望景観保全地域に指定することは新たな規制が生じることになります。そのため規制範囲内の第3者の私権を制限することから慎重に検討を行っているものであります。視点場としては永続性や歴史性、認知度、親しみ度などから優れた眺望景観を享受する場所かどうかの検討を行っております。例えば聖護院や熊野神社、平安神宮などと、視点場の関係性や古い絵図を確認することでどのように街が作られてきたのか。古い絵図にどのような記載があるのか。現在の春日北通りの街並はどのようなものか。などの確認を行っています。これらの検討内容を総合的に判断し、今後本市としての採用の可否についての考え方をまとめていきます。なお提案を採用し指定する場合は、条例第6条第2項に京都市美観風致審議会の意見を聞くとともに、市民の意見を聞かなければならないとされています。一方で提案を採用しない場合についての規定はありませんが、手続きの透明性や審議会との提案事例の共有の観点から、これまでから京都市美観風致審議会への報告を行ってきおります。
次にマンション建設計画に関する手続き状況についてご説明いたします計画地は景観法に基づく山並み背景型美観地区に位置しているため、その基準に基づき審査を行い、令和6年6月3日に認定しております。認定にあたっては東山への眺望の配慮や背景の山並みの緑の調和、歴史的な街並み景観の保全の観点から、周囲の緑との連続性を考慮した植栽を施すことや、春日北通りや聖護院からの見え方を検証すること、春日北通りへの圧迫感を低減することなどの配慮事項を伝え、事業者から提出された春日北通り聖護院門跡からのフォトモンタージュにより状況を確認しております。中高層条例にづく手続きは令和5年12月7日に標識の設置が行われ、その後、事業者が近隣住民への個別説明を行うとともに12月12日に条例に基づく説明会が開催され、令和6年1月15日に説明状況報告書が提出されており、中高層条例の手続きは完了しています。なお令和6年6月21日に建築確認が降りております。説明は以上でございます。
とがし委員(共産)
〇とがし委員:かおはようございます。よろしくお願いいたします。私ですね住民の皆さんからご案内いただきまして、住民説明会、6月20日にありました説明会に参加させていただきました。で、驚いたのは説明資料が全く配されないという不正実さでありました。配布されたA3の紙は、簡単な目次と周辺の住宅地図を貼り付けただけ。あとはプロジェクターの画像を参照 せよというものでありました。三菱地所レジデンスという大きな社会的責任を負っている大企業が、こんな不正実でことなことでいいのかっていうことを率直に思いました。で、一般的にこの手の説明会で事業者から示されるような「建築パース」についても過去の説明会も含め1度も資料としては示されない。山並み背景型美観地区と言われながらも、どのように景観や住環境と調和したものになるのか、住民には何の資料提供もないままに進められようとしてる。で、常に画像を見ろという話であります。あまりにも誠意のかけた対応であり、改善を求める声が説明会でも、繰り返し上がっております。こうした点についてまず三菱地所レジデンスに対して改善求めていただきたいという風に思うですけれども、そうした指導をお願いしたいと思うんですがいかがでしょうか。
☛建築指導部長:本件につきましては、中高層条例に基づく説明会など12月12日に行われておりまして、その後あの6月20日に行われたというのは任意で行われた説明会という風に認識しております。中高総条例で求めておりますのは、計画の内容をえ説明会なり、事前に回るということで、きちんと知らせるということですので、資料の配布を義務付けてるということではございません。内容について、しっかりあらかじめ説明するようにということを求めてるものでございます。
〇とがし委員:私は、住民からもうちょっと丁寧な説明が要望されてるってことはしっかり、これまでも伝えていただいてきたと思いますけども、今回の説明、任意だとはいえ、きちんと説明していただきたいという風に求めていただきたいというに要望しときます。
〇とがし委員:それからですね。この説明会では紙媒体での情報提供は全くない元でありましたけれども、非公開を前提に周辺住宅との関係を示す模型や聖護院門跡の門や春日北通りのある一定の視点からの画像、それからGoogleマップの画像データを参考に作成された動画シミュレーションを使った説明がなされました。なぜこれらの情報を非公開するのか全く理解、納得いかないわけでありますけれども、ある住民の方は、これを見た感想をこういう風に述べておられました。「右手に聖護院八ッ橋、左手に西尾八ッ橋という京都を代表する銘菓の本店、味わいある街並を抜けると、正面に美しい東山が広がり見えてくる。すると突然、聖護院門跡の右手南側にそり立つようなコンクリートの壁が立ち現われ、え!なんだこれは!と心臓を強く叩かれるようなショックを感じた」という風に述べられておりました。ボリューム落としてほしいっていうのは率直な住民の声でありまして、あの住民説明会の中では「西側のすごい圧迫感はそのまま」だと。で、「日照は完全になくなって環境破壊だ」と。で、「あなた方がしていることは我々の生活を壊してる」というような指摘などが相次いで出されるというものでありました。これらの住民の声について、京都市としては どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
☛建築指導部長:本件につきましては先ほども申し上げました通り、中高層の手続きをもう一通り進められておりまして、その間もきちんと建築計画とか、工事計画を周辺住民にしっかり説明するようにということですとか、協議を申し入れられた場合は、誠意を持って対応 するようにという風に指導してきてきたものでございます。それで、任意の説明会なども行われてきたものだという風に認識しておりますけれども、その近隣への見下ろし対策とか圧迫とか、日照、通風の影響の低減などにつきましても、指導しておりまして、その結果、当初考えられてた計画から北側の道路からの後退距離を大きくしたりですとか、西側の臨地からの離隔距離をえ大きくされたり、ということですとか、窓からの見し対策として目隠しの設置ですとか、バルコニーの位置の変更などが行われてきたものでございます。
〇とがし委員:大幅って言はれですけど、本当にちょっとしか変わってないっていうことな んで、それもあの去年の段階でちょっと変更されたていうところであって、やはり、この住民の声っていうのは全く完全に日照が遮られるということも含めて、しっかり受け止めて、
引き続き、そういう声があるっていうことを事業者も聞いてるわけですけども、京都市としても、お伝えいただきたい、と。
〇とがし委員:それから今回、眺望景観創生条例に基づく新たな視点を設置してほしいっという住民の提案、速やかに進めるべきだと私も考えております。今回の視点場の指定の提案っていうのは、この地において景観を守るために堅持されてきた不文律のルールを明文化するような内容であって、遡及適用できなくてもその不文律だったルールを事業者に理解 いただくという効果は期待できるんじゃないかと思うんですね。で。陳情書には「この歴史的な文化的な景観が失われてから市民提案が受理されても遅いのです。なんとかお力を貸しください」と書かれております。是非、早期の指定をして、その指定を生かしたマンション建設指導を求めたいんけどですけど、いかがでしょうか。
☛都市景観部長:まず、提案されてることと、山並み背景型美観地区これに基づく景観の指導とは、別のものであるということは、まず最初にお断りしたいと思っております。そのことを持ちまして例えば市民提案につきましては、先ほど言いました場所の歴史性、公共性こういったことを総合的に判断してきっちり考え方をまとめていくということは、引き続き検討進めてまいります。期間的には先ほど申し上げましたように、これまでの事例にもえ2件ほどあるんですが、それを考えますと、大体10ヶ月、12ヶ月 程度というのはかかってくるものと考えております。さらにデザイン基準に基づく指導の中でも市民の方からのご
提案というのもありますが、そもそも山並み背景型美観地区で、東山との連続性でありますとか東山への眺望こういったことを基準にも定めております。基本、景観計画の方にも基本方針として定めておりますので、これに基づき指導してまいりました。結果、先ほど言いました、そのシュミレーションですとかも非常にたくさんの件数を提出させ、見え方でありますとか、影響、圧迫感そういったことを材料の確認も含めて、きっちりこなしてきたと思っております。
〇とがし委員:材料の確認も含めてって言うんですけど、住民にはそういう説明一切ないんですわ。率直に言いまして。
〇とがし委員:富士山の景観が損なれるということで、国立市・富士見通りのマンション建設の場合には、積水ハウス自身の判断として解体を決断された、と。6月15日土曜日の朝の読売テレビのウェイク アップという番組では、この富士見通りのマンション解体に至たる経過と合わせて、今問題となっている聖護院門跡前のマンションについても全国ネットで報道し、全国的なまちづくりの問題として、開発と眺望景観を巡って問題が起ってることを紹介をされました。6月28日の京都新聞朝刊には、美観を隠す高層住宅の建設という近接する住民の方の投書が掲載されました。少し紹介したいと思います。山並み背景型美観地区に新たな建築物を作る場合、背景や周辺環境との調和が求めらはずだが、なぜこのように突出した建物の建設が進むのか、法や条例の基準満たしているだろうが、山並み背景を覆ってしまうような建物が周辺環境と調和してるとは到底言いがい。これは法や条例の不備と言えるのではないだろうか。京都市は市内の景観をどうしていくつもりになるのだろうか。市自らが指定した山並み背景型美観地区をその字句通りに保全するための施策を行うべきだ」いうに書かれております。私も最もだという風に思うんですけれども、今後のことにも書かれますけれども、この点に関してどのようにお考えでしょうか。
☛都市景観部長:平成19年に新景観政策として様々な景観に関する政策を始めさせていただいております。1つがデザイン基準と高さ規制こういったものを組み合わせ京都の景観を守るべくえあらかじめ基準を定めて、建設される方も周辺の方々も事前にある程度ご理解いただけるような関係は整ってるかなと思います。さらに、19年時点で眺望景観創生条例も設けて、さらにその10年後ぐらいになりますけども、さらにそれを進化させ視点場を増やすとこういったことを持ちまして、京都の景観というのを保持してきているという風に考えております。あの他の都市のこととは別で、うちとしましては、それだけの法的な部分は整ってきたと思っておりますし、先ほども申し上げました通り、その景観計画に書かれてます景観の方針、それとデザイン基準これに基づいて業者の方とはきっちり指導して協議をしてきた結果だと思っております。山並みとの調和であって山波を遮らないというものではない基準だということでございます。
とがし委員:周辺から突出した建物を作ることによって周辺に住む多くの市民の眺望景観を覆い隠すことによって眺望景観を独占し、それ売りに利益上げるという開発の構図が続くと、京都の町は一体どうなっていくのか、ということをよくよく考えていただきたい、という風に思います。聖護院門跡は光格天皇、孝明天皇が仮御所として住まわれたことから「聖護院旧仮皇居」として国指定史跡となっており、「書院」は重要指定文化財に指定されています。現在、幸いもこの当該地以外のエリアは大きな敷地は限られていて15mの高度制限であるとしても、10m 以下の2階建て3階建てが密集する形態となっている。しかし、土地がまとめられるなどすれば巨大なマンションが建設されかねないリスクがある。で、ここでなんとか食い止め、低く抑えることがこの地域を守ってくでも試金石になってくるという危機感が住民の皆さんにはあるということをよく考えていただきたい。このことを求めて質疑を終わります。
桜井副委員長(自民)
〇桜井副委員長:まず最初にえ私どもの自民党会派、本日から4人の体制でこの委員会に望ませていただきますんで、よろしくお願いいたします。それであの今、いろいろ住民の皆さん方のこととか詳しいご説明がありましたけれども、私からは簡単に事実関係だけご確認をさせていただきたいと思います。今も部長の方からご説明ありましたけれども、まず当該の物件でありますが、あの場所にマンションを建設するにあたって関係法令については、例えば中高層条例、これは完了してる、それからえっと確認申請も確認済みということでえっとほぼ必要な全ての条例については準拠してるということであれば、仮に今この瞬間からマンション建設着こしますよってことも可能ですよね。
☛都市景観部長;今ご紹介いただきましたように、建築基準法の手続き、それから中高層条例の手続き、この場合ですと景観法の手続き、これが出てまいります。こういった手続きに ついては全て完了しております。要は、基準に適合した状態であるということです。ですので、先ほどおっしゃっていた「いつでも着工できる」状況にあるということでございます。
桜井副委員長:分かりました。現状全ての法令に準拠しながら着工が可能だということを確認できました。それと眺望景観に基づく、市民の皆様方の提案で、これについてはえ先ほどもご説明あった通り、詳細の中身の確認であったりとか、かなり遡って古いこのなんていうか資料なんかもご確認されながら、最終的にご判断をされていくというところで、そうしますとえ10 ヶ月から12ヶ月、結論が出るまではかかるということで、これちょっと繰り返しのご答弁になるかと思いますが、それで間違いないということで、もう一度ご答弁お願いします。
☛都市景観部長:今おっしゃっていいた通りです。これまでの事例でごいいておりましてそれぞれ に期間見ますと10ヶ月12ヶ月それぐらいの期間をいただいてるというところで ございます。
〇桜井副委員長: えっとそれでもう1点確認は、この要望ですね。視点場のご要望ですけれども、えっとご要望が本市に提案を提出されたのは、本計画がオープンになる前から地域でそういう要望があって提出されたのか、あるいは、本計画が何らかの形で、マスコミなりにいろんな形で地域の説明になり、あるいは看板ももちろん立ちますから、そのオープンになった後にこの眺望のご要望が出されたのか。それは、いかがでございますか。
☛都市景観部長:今回の場合は中高層条例に基づく標識設置、これが行われたのが12月でございまして、ご提案いただきましたのが 2月になりますので、中高層条例の標識後、要
は、マンション建設計画が認知されてからの提案になっております。
〇桜井副委員長:そうしますと、住民の皆さん方はこのオープンになった後に、この視点場のご要望を出されたということでございますね。で、ちょっと整理しますと、今この時点で、明日からでも今この時点からもマンション建設着工できるよということで、仮に、そしるべき時期に着工され、そして、その後に、この視点場の認定、仮に、ここがそのご要望通り認定されたとしても、先ほども少し議論があったのかな、当然、その認定されたことは遡及しては適用はされないということで大丈夫ですか。
☛都市景観部長:おっしゃっていただいた通りで、新たな規制の適用につきましては、条例の方に規定をしております。その内容が新たに指定されたことを持ってマンション建設に着手した場合、新たに規制がされたことを持って京都市の方から計画の変更を求める基準に合わせるといったようなことは求めておりません。
〇桜井副委員長:そのことは当然で、もしそれが後から作って適用してくださいなんて言ったら京都中、大混乱になっちゃうかなという風に思います。今いくつか確認できました。全ての法令準拠して明日からでも着工できますよっていうこと。そして、この視点場の認定については、約10ヶ月から12ヶ月かかるよっていうこと、そして、この視点場のご要望はこの本計画がオープンになってから、住民の皆様方からこの要望を出されたということ、そして、視点場が仮に認定されても今、現行ですに着工しておられれば遡及して適用されることはないということが確認できましたんで、これで私の質疑は終わります。
(更新日:2024年07月11日)
バス路線維持に向けた新たな支援について~2024年6月5日予算特別委員会(都市計画局)への質疑
予算特別委員会 第2分科会 都市計画局 6月5日
とがし豊議員
バス路線維持に向けた新たな支援について
ーーーー
○今回バス路線の維持に向けた支援として、市バス8路線、民間バス19路線を支援するとして路線の赤字の5割、民間バスは赤字の8割を市が補助金で補填、穴埋めをすることで路線を維持していくというが、この対象になる基準と一定の市民利用がある生活路線という基準というのはどういうことか。あと、5割8割という補助率で本当に維持可能なのか。
(答弁→事業推進担当部長)補助対象路線の考え方は、当該路線が廃止されることによって鉄道駅やバス停の範囲、鉄道では半径800m、バス停エリアでは300mの範囲から外れる地域が発生すること、その路線の収支が赤字であること、一定の市民利用がある路線だ。一定の市民利用がある路線というのは、市内の完結路線及び市内外にまたがる路線のうち市内部分であること。それから1日3回以上の運行があること。または、国のガイドラインに示す交通空白地域に該当し、2回以上の運行があること。日祝のみの運行、季節運行路線ではないことで対象を絞っていく。補助率は、市バス2分の1だが、民間にはインセンティブ持たせることで、5分の4で非常に高い補助率にしている。今非常に困っているのは、運転手がいない深刻な状況。周辺部路線を守っていけるよう、しっかり事業の趣旨を説明していきたい。
○運転手さんの確保と処遇改善とセットだが、我が党としても公共交通を支援する考え方は本当に大事だと求めてきた。鉄道駅800m、バス停300m、あるいは交通空白地域については、2回以上だが、1往復しかない厳しい所、先ほど縮小してしまった所をなんとか復活できないかという話は、私も本当に要望しておきたい。交通不便地域として、先ほど路線がなくなってはいけないということで、1つ考え方を示されたが、鉄道800m、バス停300m以外は交通空白地という概念を交通不便地域と捉え、そもそも路線のない所も含めて、しっかりと課題解決に取り組むことを求めておきたい。
○この間、敬老乗車証制度の改悪によって、民間バス、市バスへの支援が大幅に縮小するが、経営上の打撃はかなり大きく、敬老乗車証の負担金の軽減や対象年齢を70歳に戻すなどして利用の促進をして、その分を支援するという合理的な公共交通の支援のやり方がある。京都市の公共交通の計画においては、使って守るということを掲げているので、福祉政策も含めて総合的に民間バス、市バスの効果的な支援のさらなる検討を求めたいがいかがか。
(答弁→事業推進担当部長)敬老乗車証制度の話は、保健福祉局だ。我々は今厳しい事業所をしっかり支援して必要なバス路線を守れるように交通政策の観点で今回制度を創設する。敬老乗車証の話でいくと、この間見直しの中で年間証の拡大などに関しては我々も意見交換している。
(答弁→都市計画部長)交通制度は、市民生活を守っていく観点で非常に大切だ。我々は交通ネットワークをいかに維持していくのかは最大の観点だ。その上で持続可能性、どれだけの経費がかけられるのかを考えながら制度をブラッシュアップしていくべき。他の委員からも交通ネットワークは非常にクリティカルなものだと。東京BRTが駅から10分以内で行けますと紹介されていたが、例えば、洛西地域で鉄道駅から境谷大橋から10分以下で届く。その交通利便性をしっかりお示し、それに対してしっかり経費をかけ、しっかり利用していただく。それに対して我々としては持続可能な制度を作っていくのが1つ大事なことだ。
(更新日:2024年06月07日)
子育て世代の定住対策は、過去の大型開発の総括の上で計画を~2024年6月5日予算特別委員会(都市計画局)への質疑
予算特別委員会 第2分科会 都市計画局 6月5日
とがし豊議員
子育て世代の定住対策は、過去の大型開発の総括の上で計画を
ーーー
○2023年4月の外環状線沿道での高さ規制などの緩和を行う都市計画変更に続き、今回の「meetus山科-醍醐の推進に向けた機運醸成」予算が第二次編成で計上をされた。時を同じくして三条駅周辺の「都市再生緊急整備地域」指定の動きが表面化した。30年前、地下鉄東西線整備と一体に進められた五大プロジェクトが実施された三条駅、山科駅、醍醐駅の周辺をさらに大きな仕掛け、大きな範囲で再開発しようというものではないか。5月23日のまちづくり委員会の都市計画局長の答弁で、過去の経過を踏まえながら必要な事業・施策を展開したいという抱負が述べられた。過去の経過を振り返ると言うなら、五大プロジェクトをどう総括しているのかと正したところ、「総括は建設局の所管」だと述べられ、駅前広場の整備としてはきちんとやっているぐらいの浅い話で終わった。都市計画局としては、もっと総合的な観点から過去の経過と総括、現状分析をやるべきだがどうか。
(答弁→まち再生・創造推進室長)山科駅前地区第一種市街地再開発事業については20年以上前の事業だが、道路や駅前広場などの公共施設が未整備で、土地利用が細分化された低層の木造住宅が数多く存在したため、公共施設、住環境及び商場環境の一体的な整備を行い都市機能の向上と土地の効率的かつ健全な高度利用を図ることを目的として実施された。この結果、施行前の狭小な道路や広場、歩車道の分離、電線共同溝整備、ラクトの4棟の施設建築物の建設、公園の整備、地下道に接続する駐輪場の整備、案内板やサイン灯が配置され、分かりやすいまちづくりが進められた。人々に憩いと潤いを与える空間が提供された。これにより、山科駅周辺を始めとする地域のにぎわい活性化に寄与貢献したと捉えている。
○こういったことを提案する場合は、事前に誠実に予め説明される必要があるのではないか。五大プロジェクトについてはその後のまちづくりにどう影響を与えたのかをしっかりと総括していくことが大事な前提だ。どこの事業にしてもそんな簡単に話が進んだわけではなくて、破綻したもの、計画変更、規模縮小、紆余曲折も含めてしっかり総括がいる。それがあって初めて失敗を繰り返されないということになる。まちづくり委員会でも、京阪京津線が地上にあった時代の賑わいに時計の針を戻すという話もあったが、現実を見ない話で、願望が先走っているのでないかと危惧する。meetus山科-醍醐のプロジェクトについては、しっかり過去の経過の上に住民の皆さんの声をしっかり聞いて計画を進める必要があるのではないか。
○そこでmeetus山科-醍醐の推進本部の資料を見ると、当該エリアにはすでに大規模商業施設、マーケット、飲食店、病院などが多く存在をし、豊かな自然、公園などがまちの魅力として押し出されている。その魅力と比較して、外環状線の高さ規制を緩和し高層マンションを建てまくる構想には大変違和感がある。子育て世代からタワーマンションに住みたいとの要望が果たして本当にあるのか。むしろ、高層マンションではなくて空き家とか中古住宅に転入とリフォームを誘導する方がニーズに合うのではないか。この高さ規制緩和で無理にこの高層マンションを推進すると、地価高騰で逆にマイホームの夢が遠のくことになってしまう。京都市中心部はなかなか手が出ないが、山科だったら今回のいろんな補助を受けて住めるかなと思った人の手が届かなくなってしまうのではないか。このリスクについて、お考えを聞きしたい。
(答弁→まち再生・創造推進室長)都市計画の見直しは、外環状線沿道の賑わいと潤いある都市空間を作る目的で様々な配慮とセットで行ったもの。こういったことを実現するため、meetus山科-醍醐プロジェクトの中でしっかりと取り組んでいく必要がある。これを通じ、住みたい移住したい方の受け皿となる住まい環境向上が、山科・醍醐の魅力ポテンシャルを高めることになる。
○それが地価高騰を招いて、せっかくまだ住める住宅があるのに生かされないことになったら本末転倒になるのではないかと危惧しているので、その点受け止めていただきたい。
○東部クリーンセンターの跡地について、地元の方からは、学校の跡地を民間資本の開発に差し出すのではなくて、京都市の施設として活用してほしいと。とくに、子どもみらい館のように子どもたちが使える施設が欲しいだとか、公園を作って欲しいという要望などもたくさんある。住民の要望をしっかり受け止めてまちづくりをしてこそ、空き家に入って生活していこうかということで人口が増えるのではないか。是非そうした視点を持つよう要望しておく。
(更新日:2024年06月07日)
北陸新幹線の京都地下延伸計画、洛西など均一区間外での民間バスに同調した市バス運賃値上げについて、政府担当者から直接聞き取り〜倉林明子参院議員&京都市会議員団〜
日本共産党京都市会議員団は2024年5月15日、倉林明子参議院議員と一緒に国土交通省職員から2点の施策について説明を受ける「政府レクチャー」を実施。
北陸新幹線地下延伸計画について、民間バス運賃値上げに同調しての京都市バス運賃値上げについて説明を受けました。北陸新幹線に関しては「無用な混乱をもたらす恐れがあるから」とほとんどの情報が不開示とされましたが、わかったこともいくつかあり、その結果をご報告しています。また、バス運賃に値上げに関しては、同調しなくてもよいこともわかりました。実際はどうかは別として今後の議会論戦に大いに生きる収穫の多い取り組みとなりました。
(更新日:2024年05月17日)