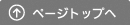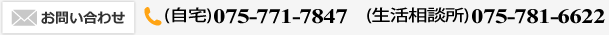(更新日:2012年10月2日)
動画コーナー
議員活動報告動画 「まちこわしSTOP! 子どもたちに、美しい京都のまちを」 (2012年)
東北部クリーンセンターの運転監視業務が民営化で焼却炉運転のノウハウ喪失の危機!2024年2月20日環境政策局質疑
2024年2月20日の環境福祉委員会で京都市は、自民党市議の質疑に応えて、東北部クリーンセンターの運転監視業務を2025年4月から民営化(民間委託)を表明。これに対し、私は大反対である旨、討論にたち、クリーンセンターの運営や焼却炉運転はじめとしたノウハウを喪失し、今後プラントメーカー言いなりになりかねないことを指摘しました。
動画はこちら(字幕あり)
とがし委員:よろしくお願いします。今、令和7年4月から東北部クリーンセンターの運転監視業務についても委託化するというお話がありました。私はこれ大反対です。その立場が質疑するんですが、実際にどういう業務を民間委託しようとされているんでしょうか。
適正処理施設部長:はい委託の対象についてでございますけども、委託を行いますのは、プラントの運転監視業務及び点検や清掃等の定型的な保守管理業務これを委託しようとするものでございます。
とがし委員:クレーンの操作だとか異常及び故障時の緊急対応だと、今言われたような保守点検ですね、電気系統とかも含めてですね、あるいは、軽微な修繕だとかもされるわけで、なおかつ、実際には終日ですね、焼却炉全体に対して責任を負うという業務なんです。まさにこれこそ根幹ではないかと思うんですが、いかがでしょう。
適正処理施設部技術担当部長:クリーンセンターの作業計画と保守管理・オーバーホール計画、この企画立案策定、運転監視業務の履行確認といったクリーンセンターの安定稼働の確保のためのえ根幹となる業務、これにつきましては直営で、今後も引き続きやっていくということでございます。で、運転監視委託業務について行う業務につきましては運転監視とか定例的な点検清掃と言いましたえ比較的単純で定型的な作業でございまして、企画立案等の根幹となる業務とは一線を隠すものと考えてございます。
とがし委員:そこがね、やっぱり、皆さん現場のこと結構知ってはずやのに、なぜそのような発想が出るのかが、私疑問で仕方ありません。というのは、焼却炉を日常的にケアするということを通じて、それぞれの炉の特徴だとか癖だとかも分かってくるし、どういう保守点検が必要なのか、あるいは、部品の交換が必要なのかっていうことも、そうした現場で実際に焼却炉を運転・監視してそれ手入れをされるから分かるんじゃないんですか。で、それを全部民間に丸投げして、しかも、プラントの関連業者に任すということになってしまいますと、京都市自身が実際どういう本当に必要性があるのかどうかっていうのを把握できずに委託先に言われるがまま対応せなあかんてことになってくるんじゃないですか。で、そうなってくると、いくら京都市の職員が作業計画だとか保守管理とかオーバーホールの計画立てるにしても、その判断の大元の部分を民間委託先に依存することになるということではないですか。だったら、この根幹の根幹たる根拠っていうのは失われるんじゃないですか。いかがですか。
適正処理施設部技術担当部長:実際に運転監視に携わってなければ、なかなかそのクリーンセンターの状態が分からないのではないかというご意見でございますが、運転監視業務を委託してるクリーンセンターにおきましては、市職員はクリーンセンターの先ほど申しました作業計画とかオーバーホール計画を立てますが、その際にこの運転監視業務の履行確認っていうのはしっかりやってございます。これは書類だけ見て終わりではなくって、実際に現場でどのようにえ運転監視を行っているのか手順とか方法とか、その結果として焼却炉の焼却状態とか灰ガスの値がとか、どんな挙動があったとかえそういうことまでも含めて確認することを含んでございます。そのことから、運転監視業務を直接経験せずとも、履行確認等を行うことにより、クリセンターの状態をしっかりと把握することができ、可能かと考えてございます。
とがし委員:履行確認するぐらいやったら、その横で見てるんやったら、それ直接やったらいいんじゃないですか。別に市の職員が。ほんで、その経験した人が上司になってそれで指導されるという風にやった方がよっぽど合理的ではないんじゃないじゃないかと思うんですけどいかがですか。
適正処理施設部技術担当部長:履行確認と申しましても、1から10まで最初から最後まで付き添ってるわけではございませんで、途中の過程は業者の方で実施して最後のところで確認をするというのが、履行確認だと考えてございます。
とがし委員:結局それで言ったら、最後のとこで確認するっていうぐらいの話になるんですけど。そうすると、実際に現場に携わってないので臨機応変の対応という局面は知らないわけですよ。結果として報告受けるかもしれませんけど。ということになりますから、私は、その点で京都市のノウハウが失われていくんじゃないかということを極めて危惧するわけです。現時点で言ったら、実際に運転監視業務をやったことある人が、京都市の環境政策局にもたくさんいらっしゃるという状況の中で、民間委託がされてるわけですね。2箇所について。で、しかしそれがこれこれからどんどん民間に丸投げしいくと、履行確認の引き継ぎはされるかもしれませんけれども、なぜその確認をするのかっていうことの意味が分からなくなってく。だんだんだんだん。民間に丸投げしていくと。ということが、やはり、私は極めてえ問題だという風に考えます。で、以前ですね、焼却灰溶融炉の問題で、まさにこれはプラントメーカーとの激しいやり取りあっったわけですけども。その時、結局あのプラントメーカーが何を言ってたかていうことで言うと「こんな不純物を燃やすとは思ってなかった」っていうことを言ってたって話を当時やり取りお聞きしたとに思うんですね。で、これに対して、プラントメーカーが一生懸命この焼却灰やろやろうとするけど、うまくいかないので、結局、京都市のその現場の職員に助言受けなければいけないということになったわけです。で。それはなぜ助言ができたかということで言ったら、結局、京都市の職員が実際に焼却炉の運営に携わってたからじゃないですか。で、そういうことがもうできなくなってきたら、いろんなプラントでいろんな問題が起こったとしても、もうそういうこの現場のこと分からんわけですから、対応できなくなってくんじゃないですか。技術的に。いかがですか。
適正処理施設部技術担当部長:あのクリーンセンターの業務に関わる技術系職員の技術の向上・維持について、大変重要なご指摘をいただいたとは考えてございますが、今まで以上に研修というものを充実させておりまして、クリーンセンターに初めて来た人間には、保護具の扱い方から工具の使い方、そういった基本的なところから研修を行いまして、さらに高度な排ガスの清浄でありますとか、どういう点を見ていったら、安定的な稼働ができるかとか、そういった研修まで含めてやっておりますので、履行確認と合わせて技術力の維持は可能かと考えてございます。
とがし委員:その研修できる人はどうやって育つんですか。指導できる方は。今はいるでしょ、実際やったことがある人が。で、これいなくなってくでしょう。かつて運転したことのある人から引き継いた方がさらにその先に引き続ぐ話になってくるわけやから、どんどん薄くなるじゃないですか。で、その意味では私は、今ちょっと研修されるいわはったんですけど、実践に勝る技術研修はないという風に思いますので、その点でこの運転監視業務についての民間委託に関しては是非、京都市の中でですね、技術的な継承という問題からでもよく検討していただきたい。で、それからあのやっぱり民間に委託をして経費を削減するんだと言われるんですけれども、結局それはどうやって捻出されるかって言ったら、あの京都市の職員よりも処遇が低くなるわけですよね、職員、そこで働く方の。ということですから、やっぱり私は、やっぱそういう形で働いてる人をコストとしてみなして削るという発想っていうのはぱ改めなければいけないし、この安定的な業務を確保するということで考えましても、やはり私はその民間に委託してた場合その事業者が何か問題を起こした場合に、もうたちまちじゃあその事業者ができななくなったらどうするんかという問題が起こると思うんですけども、その点についても私は大変危惧するわけですので、是非ですね、その民間移管については見直していただきたい、ということを申し上げて終わりたいと思います。以上です。
(更新日:2024年02月21日)
「聖護院・黒谷の景観を守る会」提出の陳情審査~三菱地所レジデンスさん、聖護院門跡の正面、かつ、低層の住宅群の中に巨大なマンションは似合いません!2023年12月6日京都市会まちづくり委員会
京都市会まちづくり委員会2023年12月6日(メモ:とがし豊作成)
京都市会まちづくり委員会2023年12月6日(メモ:とがし豊作成)
◇委員長:それでは陳情第 1325号「マンション建設計画の指導について」を審査いたします。それでは理事者説明願います。
☞(理事者説明)建築指導部長
ありがとうございます。それでは陳情第1325号「マンション建設計画の指導ついて」ご説明申し上げます。お手元の陳情文書表をご覧ください。陳情者は記載の通りでございます。陳情の要旨でございます。住民は元より京都市民も聖護院門跡から金戒光明寺(通称・黒谷)に至る景観と住環境を大切にしてきた。しかし聖護院門跡の前に三菱レジデンス株式会社が計画している分譲マンションは、歴史ある聖護院門跡を見下ろす計画であり、この地にふさわしくはない。さらに敷地境界からほとんど隙間もなく五階建てが立ち、マンションの壁やベランダが直近の家にそそり立つことになる。ついては、聖護院門跡から黒谷に至る山並みが見える低層の景観や近隣の家の住環境を守るため、次の2点を願う。1点目は聖護院門跡を見おろすようなマンション計画を見直すよう事業者に指導すること。2点目は2階建てが連なる近隣の住環境と調和した建物になるよう事業者に指導すること、というものでございます。想定される計画地の地域地区につきましては、用途地域が第2種中高層住居専用地域、高度地区は15m第1種地区、景観規制は山背景型美観地区に指定されており、建蔽率60%、容積率は200%でございます。また計画地の周辺状況につきましては、北側が幅員8mの道路及び駐車場を挟んで聖護院門跡西側及び東側が2階建ての戸建て住宅、南側が7階立ての共同住宅や6階建ての商業ビルとなっております。本件の手続きの状況でございますが、12月6日現在、中高層条例に基づく届出や報告書は提出されておりません。また景観法に基づく認定申請も提出されていないため、本市では建築の概要は把握してございません。今後、中高層条例の手続きが行われた場合、条例の趣旨に基づき周辺の住環境に配慮した計画となるよう指導行うとともに、景観法に基づく認定申請が提出された場合には、美観地区の基準に基づき周辺の街並みに配慮をした計画となるよう指導を行ってまいります。ご説明は以上でございます。
井上副委員長・自民党
〇井上副委員長:このマンション建設計画の指導についてですけれども、先日、陳情者の方と私とそしてまた島本委員と一緒になって直接お話もお伺いしました。この計画地の規制内容をもう少し具体的に説明していただきたいのと、実際にこれどのような規模のマンションの建設が可能なのでしょうか。
☞(答弁)建築指導部長:はい、計画地につきまして、用途地域が第2種中高層住居専用地域で建蔽率は60%、容積率は200%でございます。高さにつきましては15m第一種高度地区に指定されており、マンションでありましたら通常地上5階のものが建築可能でございます。さらに勾配屋根を設ける場合には高さ18mまでの緩和措置がございます。景観規制につきましては山並背景型美観地区に指定されておりまして良好な屋上の景観や周辺への圧迫感の低減などの配慮が基準として定められてございます。以上でございます。
〇井上副委員長:はい、まだ手続きがされていないということですけれども、この規模の建物を建築するためにはこれどのような手続きが必要となるんでしょうか。
☞(答弁)建築指導部長:はい。陳情書によりますと階数は5階建てですので、高さが10mを超えることが想定されます。その場合は通常の建築確認申請に先立ちまして中高層条例の手続きが必要になります。具体的には建設予定地に建築物の概要を記載した標識を設置するとともに、近隣住民に計画内容を説明した上でその説明状況について本市に報告していくことになります。加えまして当該地は山並み背景型美観地区に指定されておりますので、景観法に基づく認定申請を本市に提出し認定を受ける必要もございます。以上でございます。
〇井上副員長:これ今後、中高層条例や景観法に基づく認定申請の手続きにおいて、どのような指導を行っていかれるんでしょうか。
☞(答弁)建築指導部長:はい。まず中高層条例で申しますと、届け出が提出されましたら、建築計画 の内容、それから近隣への説明状況を精査した上で、条例の定に基づきまして必要に応じて近隣住居への日照・通風への配慮、それから近隣住居への見おろしに対する配慮などを求めていくことになります。
☞(答弁)都市景観部長:はい、認定申請が提出されましたおりには、その手続きを通しまして山並み背景型美観地区のデザイン基準定めております。これに基づきまして周辺への圧迫感の低減を図るため道路からの十分な後退や外壁面の分節等の配慮それと、緑の連続性。この地域非常に緑豊かでございます。それを考慮した植栽計画の検討などについて協議してまいりたいと思っております。その結果としまして歴史的な街並み景観の保全を図り、東山山麓の緑豊かな自然景観との調和に配慮した計画となるように求めていくことと考えております。またあのあたりの景観との調和、周辺景観への圧迫感の低減を図るという点では、例えばですが、春日北通からの見え方、それに加えまして、聖護院からの見え方につきましても、シミュレーションをきっちり相手から出さして検証を行っていくということも相手の方に求めてまいりたいと考えております。
〇井上副員長:はい。あのしっかりとあの事業者に指導をしていただくようにお願いをして質問を終わります。
神谷副委員長・維新京都国民
〇神谷副委員長:よろしくお願いいたします。私どもの会派にも住民の皆さんがお越しになられまして、左京区の議員中心に皆さんのお声をしっかりとお伺いをしたところでございます。基本的に先ほど制約・規制等については答弁があった通りでございますけれども、やはり、あのこの周辺、低層の住宅があってですね。で、西側にまさに隣接して2階建ての住宅があるなどの現場もあることから、またながらくこの土地駐車場になったことからですね5階建てが急に立つってことで住民の方々の戸惑いも一定理解できるところではございます。法で規制できるとこ、できないとこ、色々あると思いますけれども、先ほど井上副委員長からもありましたが、しっかりとあの今後事業者に対して、近隣の皆さんのご意見をしっかりと伺ってですね、これまでもそうしていただいていると思いますけれども、丁寧に対応するように、京都市からも是非アドバイスをしていただきたいと思いますが、改めてになりますが、いかがでしょうか。
☞(答弁)建築指導部長:はい。今後、建築手続きがなされましたら、それぞれの制度の趣旨に乗っ取りましてしっかりと事業者の方には対応を求めてまいりたいと考えております。以上でございます。
〇神谷副委員長:ありがとうございます是非よろしくお願いいたします。あとですね。もう1点ちょっと確認をさせていただきたいんですけども、この陳情の中でも懸念されている聖護院門跡との間で、事業者は実際何か協議を行っているのかっていうことと、また、京都市に対して聖護院門跡から何か相談等が何か寄せられているのか。その辺についてちょっと確認をさせていただけたらなという風に思います。
☞(答弁)建築指導部長:はい。計画内容に関して、まだ事業者の方から京都市に相談を我々の方に受けていることはございません。それから聖護院門跡の方から我々に相談ということもありません。以上でございます。
〇神谷副委員長:分かりました。まだ相談はないということですが、しっかりと住民の方々のご意見をお聞きしてですね、丁寧に進めていただけたらと思います。以上で終わります。
平井委員・日本共産党
平井委員:今回のマンション計画に対して、マンション計画の見直しへの指導や2階建てが連なる周りの住環境と調和した建物になるようにということで、指導してほしいというのが趣旨だという風に思います。左京区で連続的なマンションの開発が行われてるっていうことに対して、多くの住民の方から、この状況では本当に自分たちの住む場所のやっぱ風景も暮らし奪われていくっていうことを危惧されての陳情だという風に思います。新景観政策の策定時、2005年当時の市長であった桝本市長の定例記者会見では「おし寄せる経済至上主義の波に圧倒され古るき伝統的なものが効率性の名のもとに次々淘汰されました」ということで、記者会見の冒頭部分で述べられています。さらに「クリーピングディストラクション、忍びよる破壊とも言うべき社会現象に是非、一石を投じていきたいと考えております」と述べられております。今回の計画も含めて、あの経済至上主義が詰まったマンション開発に対して、僕は京都市として一石を投じてですね、既存住民を守るとあの貴重な伝統文化など守ることっていうことが責任ではないかと思うんですけれど、いかがでしょうか。
☞(答弁)建築指導部長:はい、繰り返しとなりますけども、この地域には高さ規制ですとか、景観規制定められてございます。で、それぞれの制度に乗っとりまして周辺の住環境への配慮、それから景観への配慮、これをしっかり求めてまりたいと考えてございます。以上、でございます。
〇平井委員:制度に乗っとるということで言われましたけれども、やっぱりマンション計画の設計自身はですね、あの文中にも書かれている通り、容積率いっぱいに建てられて壁やベランダが直近の家の窓辺そそりたち、見合わせる近さで向かい合うものとされていると。これは経済至上主義そのものだと言わざをえないわけでありまして、当時の市長のこの発言となんというか、その当時の市長の発言がやっぱり非常に良かったなと思うんですけれども。一方では、今の京都市の姿勢というのは法に乗ってここまでしかやりませんよ、ということでありまして、そういうことになれば既存住民が住み続けられなくなり、持続的なこれまでの営みが途絶え、こういう地域に、新たなマンションの建設を誘引するのではないかと非常に危惧するんですよ。こういう点からでも、新景観政策が、徐々に徐々に骨抜きになっておるんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
☞(答弁)建築指導部長:はい。まず陳情書に書かれています「隙間がなく立っている」といった状況。我々まだ届けで受けておりませんので、実際にどういう計画かを把握してございません。その計画内容をしっかりと見た上で、近隣への配慮が必要であればその点についてはしっかりと指導してまいりたいと考えでございます。以上です。
〇平井委員:一言言っときますと、陳情で出ているんですから、すでに計画を含めて見るべきだという風に思います。わずか15年で今の都市計画の見直しがかなりされていますけれども、当時の市長の決意をね、やっぱ尊重すべきだと。最近、続いてる、もちろん、その高さ規制・制限が今それぞれ地域で決まっているのは分かりますけれども、やっぱりそういうこと今後どうするのかっていうことが今問題提起されているという風に思うんですよね。だから あの開発がそのどの地域でもこう起こっていくことによって既存の住民の方々のその生活基盤っていうのは変わってくると思うんですよね。だからそういうところも見ながら都市計画をどうするのかっていうのを考える必要があるという風に思います。あの手続き上で言えば今から中高層条例もありますし、先ほど言われたようにあの景観法に基づいたあの認定申請なんかもあるっていうことでありますから、そういう機会にやっぱり住民の声を きっちり聞いていただいて既存の住民の 方々のその思いっていうのを是非受け止めた上で指導していただきたいという風に思います。
井崎委員・無所属
〇井崎:地元で私も何度か住民の方来られているんですけど、一番おっしゃってたのがその窓を西向けの作りになる、あの鴨川が見えるようにということで作るので、その自分たちが住んでる他の家がそのマンションの窓から、いわゆる「丸見え」になるっていうことで、窓の場所を変えて欲しいということを、三菱地所さんとすでにやり取りをされてるけれども、なかなかそれはあの価格が変わってくると鴨川が見えるかどうかでマンションの価格が変わってきますのでというようなお返事があるんですけれども、ここはなんかこう法律とかで規制とかはできないもんでしょうかねっていう具体的なご相談もすでにいただいてるんですけど、これから建物は建築確認に入りますけれども、今のところだから京都市としては何も業者さんとそういう相談は何もないっていうことですか。
☞(答弁)建築指導部長:はい。まだ計画内容に関する相談はいただいておりません。
〇井崎:1m離れていたらあのプライバシーのそのなんだろう、あの壁を作る必要はないとか法律上はそういう風 になっていると思うんですけども、後で私また松ヶ崎の件でもご質問しますけれども、法律上クリアしていてもその住民の声がなかなか届かないっていうのが本当に頻発していると思うんです。これお願いですけど、後でも言いますけど、やっぱ説明会とかそういう場に是非京都市の方も出ていただいて、どこが問題になってるのか、長年住んでいる方がどういう要望あるかっていうのは、是非今後聞いていただきたいなと思います。終わります。
◇委員長:他にございませんか。(手を挙げるものなし)なければ本件は陳情ですのでこの程度にとめます。以上で陳情審査を終わります。
(更新日:2023年12月11日)
2023年8月8日◇京都市会環境福祉委員会◇日本トータルテレマーケティング株式会社による不正請求について追及する質疑(とがし豊)~刑事告訴と参考人招致を要求~
とがし豊議員(共):よろしくお願いします。私からもNTM・日本トータルテレマーケティング株式会社によるコールセンター委託料過大請求についてお聞きをいたします。先ほど最初は事務的な誤りから始まったかもしれないって話があったんです。私はこれは事務 的な誤りではないというふうに思います。で、そして、とりわけ、この79億円という契約金額と今回の深刻な過大請求の実態から考えて、環境福祉金委員会にNTMの社長の参考人招致やあるいは特別委員会の設置など議会としても特別な対応が必要だというふうに思います。その点では、各会派の皆さんにぜひと協議したいと思います。まずは、正副委員長でご検討よろしくお願いいたします。それからですねあのもうこれ先ほど今あのご答弁ありましたように、NTMの第三者委員会の設置のいかんに関わらず警察含めて対応していくというふうに言わましたけれども、ぜひその立場ですね、もうすでに10ヶ月経過してるわけですから、もう待てない状況であって刑事告訴すべきであるということも申し添えておきたいと思います。
とがし豊委員:それでは質疑に入りたいと思うんですが、総額79億円もの契約に関してNTMが京都市を二重三重に騙して過大請求してきたことが分かって入札参加資格停止となりました。で、前回までの市議会でこの明らかになった一連の不正請求の実態あるいは疑問などについてNTMから京都市に対して何かその謝罪はあったのかどうか。先ほどの話では返還に応じるって話あったんですが、そもそも謝罪があったのか。この点についてお聞きしたので、特に謝罪があったんだったら、どういう形でどう謝罪したのか、ということを聞きたいと思います。
担当部長:前回の委員会でご報告しましたけども、京都市の調査結果が出たということでこれに関しては 速やかに電話の連絡でしたけどもしております。これは第一報ということでその際に担当の方から謝罪があったというのと、その後ですけども、本市が返還を求めた中で、7月31日に社長以下が来庁されまして、私どもの方に対して謝罪を受けております。内容としましては、7月のちょうど1か月ほど前なんですけども、直接社長とお会いしまして、その際にはもう 令和4年8月以前に関しては過大請求みたいなものがほぼないという ようなご発言をいただいておりましたのでその中で1ヶ月経ってこれだけの過大請求を明らかになったということに関しての謝罪。またあの資料の出し直し等々もありましたので、それに関して京都市の職員に対して非常に手間をかけたという ことこういったことなどについて直接謝罪を受けております。
とがし豊委員:私ね、これ4000万円についても謝罪してほしいというふうにそもそも思うんですけど、まあそれはなかったという話ですので。私も昨日、夕方頃、NTMのホームページが更新されたのを確認をいたしました。で、「京都市新型コロナウイルスワクチン接種事業に関わる調査委員会に設置」なる文書が発表されましたけれども、このコメントに関して京都市としてはどのように受け止められましたか。
担当部長:はい、昨日夕方に今ホームページにアップされてると中身としましては第三者調査委員会を設置するということと、京都市への謝罪等々が冒頭に 述べられてなのかなと思っておりますで、私どもとしましては先ほども申し上げましたけれども、この調査委員会設置されて調査されるというのは、それは置いといて、これにかかわらず、これまで厳正に対応してきた流れがございますし、その警察等々の相談も引き続き行って徹底的に調査を行っていくということで受け止めております。
とがし豊委員:私のその姿勢、非常に大事だと思うんですね。で、NTMが昨日発表した文章はこんなこと書いてありました。「令和3年2月分から令和4年8月分の請求分について過大請求がされたことが判明し本年7月に 1年間の入札参加停止処分を受けることになりました。深く申し上げます」と。で、「請求における不正の有無なども含めて調査」するということ第三者委員会を設置して 調査するというふうに述べていました。私ね、今更不正の有無の確認のかって率直に思いました。で、まずは不正を率直に認めて、その真相究明に踏み出してこそ自浄作用が発揮されるんじゃないかと。この後に及んでも4000万円の過大請求の時と同様に事務処理のミスと言い逃れられる可能性を残すような言い方してるわけですね。で、形でひょっとしてこれは第三者委員会とは言うけれどもそんなに権限もなく形だけの調査になるんじゃない かって 疑念を抱かざるを得ないそういうニュアンスが滲み出ているということです。で、4000万円の過大請求に関しては一言もないですね。詫びているようには見えるけど肝心な部分について曖昧にしているということです。ですからその点でこの調査委員会これ当然やっていただくの当たり前の話だと思いますけれども、しかしこの調査委員会に 関わらずこの警察との相談などして取り組んでいくというその姿勢というのは本当に貫いていただきたいというふうに思います。で、次にこのNTMに関してはコロナワクチンコールセンター以外に令和4年度高齢者インフルエンザ予防接種コールセンター運営等業務 京都市新型コロナウイルス感染症にかかる帰国者・接触者相談センター運営業務の2つの契約がありました。京都市は前回の委員会では創価契約だから今回の単価契約のような問題起こらないと説明されましたが果たして本当にそうなのか。改めて、契約書を見させていただきました。で、新型高齢者インフルエンザについては令和4年2022年9月から15回線以上、10月からは11月は25回線以上確保が条件とされ帰国した接触者外来は昼間は8回線以上夜間は3回線以上の稼働が条件とされていてそれぞれ1回線に1人以上の職員配置を義務付けている記載となってます。で、日報では回線数や応答率が示されますけれどもすべての回線数に見合う人員がいたかどうかわからないんじゃないかとで契約通りに席が埋まっていたかどうか確認するためにこの契約2つの契約についてもNTMに対してタイムシートを要求すべきではないかと思うんですがいかがでしょうか。
担当部長:高齢者インフルエンザコールセンターで ございますけどもこちらに関しましてはその 業務完了後に提出される事業報告書の確認 を持って委託料の支払いを行ってたということに加えまして今先生の方がございましたけども、日報という形で毎日その 応答率とか回線数といったような状況を毎日報告を受けていたという状況でございます。その中で確認しますと応答率などに関しましては原則90%以上の確保を求めておりました。けれども報告書によりますと、期間を通じますと99.7%という高い大通率だったのと最も低かった日でも96.3%ということで 業務の履行については問題なかったのかなと考えております。で、加えましてその市民からまあコールセンターに連ながらないといったような苦情もございませんでしたので契約が履行されていないと言える状況ではないという状況でございますので、現時点ではタイムシート等の提出を求めるということまでが予定はしておりません。
とがし豊委員:厚生労働省は4月12日に新型コロナ ウイルスワクチン接種体制確保事業などの委託にかかる不適正な事案に関する通報 窓口を設置されましたその中の事例として委託事業者が使徒の協議により決定した 席数よりも少ない席数での運営を委託業者に指示し、市に対しては、市と協議した 席数で計算した金額を請求というふうにありますこれは総価契約でも起こりうる 事態であってとりわけNTMに対してはタイムシート要求してこれ本当に 契約がですね、今言われたのは応答率の部分ですけれども、それ以外の ところも 望ましいこの回転数については望ましいというところから確保するとはっきり切り替えてるわけなんで、そういう意味では その契約が本当に完全に履行されてたかということをこの後この事態に及んでは、やはり提供を求めるっていうのは筋が通った要求ではないかと思います。NTM自身も、他の契約に案件についても調査するっておっしゃってるんですから、ぜひ京都市としてもそれ求めるべきだとで、また同文書では厚生労働省が不正な事案についての情報 提供を求めておりまして現時点で明らかにことについてやはり京都市としても直ちに 報告すべきだと考えますがこの点はいかがでしょうか。
担当部長:国への報告でございますけれども、コロナワクチンのコールセンターの関係ではこれまでから適宜ご報告をしてまいりました。最初に分かった4000万円の 過大請求こういったところからですね 適宜ご報告を行っておりまして昨日動きのありましたその第三者調査委員 会の話ですとか 返還請求に応じる意向を示しているといったことも含めましてこの国の方にはすでに伝えております。
とがし豊:国にいただいているということで当初お聞きしてたらある程度結論が出てから国に伝えるって仰ってたのでその点ではきちんと国に伝えていただいたというのは前進かなというふうに思いますけれども、先般いただいた資料でも21都市で同様の契約が結ばれている類似の契約があるということで私は やっぱり全国的な問題になりかねない事態ではないかというふうに思いますでその点 でぜひ京都市としても積極的にその全国的な調査についても大いに協力をしていただきたいというふうに思います。最後に先ほど ですね 社長からの謝罪があったということなんですけれどもその謝罪の中身についてもし 何かメモのようなものがもらえるのであれば個人への資料で いただきたい委員会資料いただきたいということ。それから、あの個人資料としてお願いしたいのがありまして高齢者インフルエンザ予防接種コール センター 業務の各月ごとの日報のまとめ及び報告書をいただきたいと帰国者接触者外来の相談センターについてもそれに準じるもの があるのであればいただきたいということです以上です。終わります。
委員長:ただいまとがし委員から要求がなりました、社長などの謝罪の中身について、委員会資料として要求することに異議ございませんか。理事者提出できますか。
担当部長あのこちらの方でちょっとまとめて出させていただきます。
委員長:提出できるということですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。
委員長:ご異議ありませんので委員会資料として提出を求めることとこと に決定いたします 理事者におかれましてはなるべく早く提出していただくようによろしくお願いします。それと先ほどシーンから後手提案がありました ことについてはまず制服委員長で協議
いたしたいと思いますので、ご承知おき願います。
(更新日:2023年12月04日)
なんと77億円の黒字!なのに行財政改革の見直しなし、うち35億円を公債償還基金に前倒し返済!?~2023年9月22日京都市予算特別委員会質疑~
去る2023年9月22日京都市予算特別委員会で補正予算の審議が行われました500億円の財源不足どころか、収入が大幅に上振れし77億円の黒字に。行財政改革により市民負担増の見直しに手を一切つけることなく借金の前倒し返済に動くのはどうなんでしょう。質疑に立ちました。
ーーーー
とがし豊議員(共):2022年度決算で77億円の黒字が出て、これを主に活用して編成されたのが今回の補正予算ということであります。2023年の実質102億円の黒字に続いて2022年度の決算は 77億円の黒字と。しかも2年連続で、前倒しで「過去の負債の返済」ということで「公債償還基金」への積立が行われます。決算を受けた今回の補正予算も含めてですけれども市民からは「京都市の財政は大変なのか?それとも余裕があるのか?どっちなのか?」という声が出てきているというのが率直な現状です。当初、市長や財政当局は、毎年500億円の財源不足で令和6年2004年には基金が枯渇し財政破綻と主張してこられましたけれども、その説明からはあまりにも乖離している現状にあるんじゃないかというふうに思います。京都市財政が厳しいことは確かでありますけれども、毎年500億円の財源不足というのは、やはりかなり誇大宣伝だったんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
室長:当時、行財政改革計画を策定する段階におきまして有識者会議を開いて議論をさせていただいたわけでございますけども、その議論を始める最中と言いますか、その直前に、コロナ禍に見舞われたということでございます。財源不足500億円毎年ということでございますけども、やはり、そのコロナでの影響というものが非常に大きい状況でございました。これはこの見込み方につきましては、令和3年度の他都市の予算の状況を見ていましても、市税収入大幅に減少見込まれる。また、国が地方の財政の見通しを毎年立てているわけでございますけども、その中でも5%を超える減少が見込まれる中、本市ではそれをよりもまだ少し影響が低いという風な見方をする令和3年度予算を編成さところでございますけども、そうしたことが非常に大きかったかというふうに思っておりますが、これにつきましてはそうしたことにならないためにそんな見込みがある中でも国において的確な財政出動され、また、京都市におきましても国・府と歩調を合わせる中で市民中小企業の皆様の支援をする、また、市民の方、事業者の方が懸命にご努力をなされる中で我々が見み込んでおりましたリーマンショックのような時のような状況にはならずに進んだということでございます。
とがし豊議員(共)まあ今ですね、直前にコロナ禍だったということで、そういう中で財源不足ならないようにという話だったんですが、結局、国はコロナ対策でしっかり手当して京都市はその臨時交付金の枠内で対策を打ち、地方財政についても国は同水準を維持するというルールを守って財源もしっかり確保してきたという状況だったと思うんですね。ですからあのリーマンショック級の税収の落ち込みという行財政改革計画を見通しが大きく外れて大幅は生まれる上振れによって今回77億円の黒字となったわけであります。で、大幅に見立てがくるっているという状況のもとで、今回市長が補正予算編成の考え方として「今なお急激な物価高騰等にお困りの市民事業者皆さんへの更なる支援」というふうに述べられてるんですけれども、京都市の場合にはそのコロナ物価高騰に加えて行財政改革計画による福祉削減によって痛めつけられている市民生活というものがあります。ここに対する手当てというものを今回の補正予算の中で組まないっていうのはやはり市民の実情を見てないってことになるんじゃないかと。その点で、私はですね、この予算編成の考え方の中に行財政改革計画による負担増の見直しっていうのも入れられて然るべきだったんではないかと思うんですが、この点の検討はいかがだったでしょうか。
室長:この間行財政改革の取り組みの中で事業施策の見直しを行ってきたことについてということでございます。今回のこの見直しにつきましては施策を持続可能なものにするという観点から行ったものでございます。例えば使用料手数料につきましては施設を利用する方、しない方の公平性の観点も踏まえながら適切な公費負担割合になっているかどうかということについて点検をして適正化をしたものでございます。また、その他都市を上回るようなとこ実施施策の理念を引き継ぎながらも引き続き他都市水準を上回るサービスを将来にわたって維持をしていくために人口動態、社会経済情勢それから制度の課題を踏まえて再構築を行ったものというものでございますので、こうした考え方で再構築をしたということでございますので、黒字になったからということで元に戻すということではないというふうな考えでございます。これらにつきましては、その単に元に戻すとか戻さないというそういう議論ではなくて、今現状あるこの事業政策を現状に照らし合わせてどうなんだと、課題があるのかどうか、そういう観点で見ていく必要があるものというふうに考えておりまして、議会からのその付帯決議も踏まえた指摘も踏まえましてこれまでからも事業の検証し、また、見直す際におきましても適用範囲を拡大する新たなサービスを付加して利用しやすくするというような取り組みを加えたり、また検証する中で、経過措置を設けるもしくはより重々させるというような見直しもすでに行っているところでございますので、引き続きそうした観点で事業・政策については検証していく必要があるというふうに考えてございます。
とがし豊議員(共):引き続き検証していく必要があるというふうにおっしゃるわけなんですけれども、詳しくはですね決算審議の場に譲るわけですけれども、例えば敬老乗車証で言えば負担金倍増で2万5000人の方が敬老乗車証を諦めると。で、民間保育園の13億円の補助金削減によって、これの13億円にとどまりませんでした実際は、補助金削減よって15の保育園で給与カット、58の保育園で賞与カットという事態を生み出しているということが 2022年の12月の市議会に報告されております。で、世間で賃上げが叫ばれている時に賃下げなどありえないというものです。この未来世代を育てる保育現場の先生方と粗末に扱う京都市であってはならないと思うんですね。こういう事態が現に起こっているという状況の中で、例えば今回の補正予算を検討するにあたって、保育予算の増額を盛り込んで本格的なこの保育予算削減についての軌道修正を行うべきではなかったのか、行財政局と子ども若者ははぐくみ局との間でそうした意思疎通っていうのは本当にあったのかどうか。この点について確認したいと思います。
室長:今回の 補正予算につきましては大きく2つの視点での考えで予算を編成させていただいております。今回、冒頭ございましたように令和4年度では77億円の黒字を達成する
ことができる中でその財源を今と未来のために活用していくという中で、1点は過去の負債、これは500億円が残っているということでございますので、それを着実に返済をしていくこれ重要な視点だと思っております。一方で 今の方に対して課題に対してどう対応するかということで物価高等への対応また経済が正常に戻りつつある中でも、生産力の向上ですとか消費関係等ですね事業者の後押しをするようなそういう視点で編成をさせていただいたというところでございます。
とがし豊議員(共):今と未来を考えて編成したと言うんですが、今の保育の現場も守れないという現状がある中で、例えばその子ども若者はぐくみ局との間でどういうやり取りがあったのかということを聞きたかったので極めて残念に思います。同時にそうした今と未来と言いつつも、その今が極めておろそかにされているもとで 未来が果たして守れるのかという根本的なこの予算編成の考え方についての疑問も呈しておきたいと思います。
とがし豊議員(共):次に今回の補正予算の最大の費目が公債償還基金への積立ということになりまして。平たく言えば借金の前倒し返済35億円ということになると思います。これは京都市が自由に活用できる一般財源53億円のうちの7割を占めております。2021年の決算で187億円を借金のこの前倒し返済交際基金の積立に使ったことと合わせますと2年間で222億円に及ぶものとなっています。京都市の財政が慢性的に厳しい状況であるとは事実であり、この公算償還基金を一定の考えで積み立てることも必要な措置ではあるんですけれども、その回復との規模とスピードというのは市民生活との両立がなければならないという風に考えます。その点で、当初あと10年で達成するとしていた収支均衡とその特別の財源対策からの脱却というものをすでに達成している下において、この上この 2年間で222億円の前倒し返済っていうのはバランスを欠いているのではないかというふうに考えますがいかがでしょうか。
室長:過去負債の返済を優先して行うという姿勢でございますけども、これは返済を後回してもいいというようなことは決してないというふうに考えております。一方で両輪、両立させる必要があるのではないかというご指摘でございましたけども、今回の中でもですね、返済のみを行うということではなくて、今の課題に対応するところにも財源を振り向け予算を提案させていただいているところでございますので、決して返済のみを優先をさせて行うということではないということでございます。
とがし豊議員(共):返済のみを優先させるわけではないと言うんですけれども、先ほどから35億円の返済の根拠として高齢化がピークを迎える令和20年、その24年がピークで、その直前の24年にまでにこの13年間その13年間の間に505億円返済するということで、この単純に割り算をして算出されているわけであります。コロナ禍、物価高騰の今に一挙 返済する必要あるのかというふうに率直に思うわけですね。そもそもこの京都市財政が厳しくなった原因である地下鉄東西線の工事にあたってゼネコンに言われるがまま契約変更を繰り返して2倍に工事費を膨張させたことや平成初期に身の丈に合わない規模・スピードで大型公共事業やってしまったこと、その借金の返済のピークがこれから迎えるというところに今の京都市財政の苦しさがあるわけであって、その返済の原資っていうのは、やはり、投資を過大にしすぎたということであれば投資的経費の抑制によって確保すべきではないかと思うんですがいかがでしょうか。
室長:市債の返済がピークを迎えることについては事実ではございますけどもこれまで行ってきた投資につきましてはいずれも必要な投資であったというふうな認識でございます。
それからすいません。先生ちょっと、ご指摘を、ちょっと現地を通して経費を充てるんじゃないかという確か質疑だったと思います 。
とがし豊議員(共):京都市財政が苦しい原因はそれ共有できる話だと思うんですけれども、その先ですね、その結果生まれているこの財政の苦しさなわけですから、今後については やっぱり投資的経費をより抑制するということによって捻出してこうした公債償還基金の計画的な返済ということも考える必要があるんではないかということでお聞きいたしました。
室長:すいません大変失礼いたしました。投資的経費につきましては行革計画、現行の計画の中でもですね、今後その施設の維持修繕のために多額の大規模改修等ですね必要になる中でそれを一般財源べースで言いますと170億円に抑えると いう中で 計画をしているところでございます。行ってその抑制をするということも鑑みて、今後の公債費が大きく膨らまないようにもしくは低減をさせていくようにという中で計画をさせていただいているところでございます。投資事業全て悪いかのように言われるところもございますけども、決してそうではなくて今ある施設を維持していくためにも必要なものであるというそういう認識でございます。
とがし豊議員(共):私は投資が全てダメって言ってるのではなくて身の丈にあった規模とスピードでやらなければいけなかったにもかかわらず、それを考えない過大な投資がやられてきたんではないかでそのペースあまりにももし必要な事業であったとしてもペースが 身の丈を超えるペースでどんどん作っていったら財政が厳しくなると誰が考えても明らかなわけで30年後までに返済しなければいけないって話になってくると、より一層その将来世代に負担がかぶるということを将来世代との負担の公平性という名のもとにやってこられたわけであって、その過去の皆さんが職員だったじゃなかった時代も含めてですけどもその過去のツケを今払うということであればその視点はやっぱり 過去の失敗の原因というところに着目したお金の使い方の見直しっていうのがいるんではないかと。私も過去にですね。京都会館の問題だとかにしても、北泉橋の問題にしても、区役所問題にしても様々のお金をかけずに移転しない方法やとか、改築の方法やとか含めて京都市当局の内部の資料なんかも示しながら、対案を示して言ってきましたけども、そういうことも全然聞かずに進んできたわけで、その結果今京都市の借金があるということですので。やはり、その点では今後の投資経費の見直しについてはより踏み込んだものを求めたいと思います。最後にですね、私はこうした中で今回補正予算が組まれるということで、77億円もの財源が出てきたという状況の中で、先ほどもちょっと冒頭申し上げましたように、行財政改革計画の中で 削ったものについて、どこかでも見直しをして、負担軽減をすると。あるいは課題を検証すると言われましたけど検証するまでもなく結果出てきている課題が現実にあるわけで、それはやっぱり、具体的に解決するような補正予算に組み替えていただきたいということを求めて質疑を終わります。以上です。
(更新日:2023年10月02日)
新型コロナワクチン過大請求問題~さらに1700万円の過大請求発覚~ついに、警察への通報・協力要請へ
委員長:進行いたします。
とがし委員(共産):よろしくお願いします。まずですね日本トータルテレマーケティング社以下NTMと省略させていただきますけれども、このNTMによる新型コロナウイルス 接種ワクチン接種コールセンター業務の委託料過大請求について前回に引き続き質疑をさせていただきます。今年の1月に判明した2022年9月分の4061万0350円の過大請求に続き、8月以前について調査されたところ6754時間 約1785万円分の過大請求があったということが明らかとなりました。同一人物の二重計上やタイムシートに記載のない勤務を書き込むなど、この過大請求の手口は極めて悪質だという風に考えます。日本共産党京都市会議員団としてもこの事態を重く見て全容解明に力を尽くし、不正を徹底的に正したいというふうに考えております。情報を提供いただいた方はおそらくよほどの思いを持ってこの不正を告発されたものだと考えます。そのことがあったからこそこの間過大請求が明らかになってきているのではないかと思います。その勇気ある行動に京都市としても総力を挙げて答えていただきたいというふうに考えます。警察はじめあらゆる関係機関の協力を得て、あらゆる手段を講じて徹底的に全容を解明し、不正を正すために全力を挙げていただきたいというふうに思います。まずこの点について確認したいですが、いかがでしょうか。
担当部長:先ほどからご答弁している通りなんですけども、令和4年9月の時点では私どもとしてはその「事務誤り」というような説明も受けていということでその不正といったとこまでの認識には至っておりませんでした。ただその後の調査を行いまして色々と不審な点出てきておりますので、そういった疑問点に関してはですね、徹底的に調査をした上でですね全容解明に向けまして、関係機関のご協力も得ながらやっていきたいということで考えております。
とがし委員:9月分の4,000万円の過大請求が判明した時点についてはその時点ではまだ不正という認識はなかったという話なんですけど、ちょっとその点について前回についてちょっと確認したいと思います。で、そもそもこの11月29日にNTMからシフト表が提出された当時にタイムシートを廃棄したという説明を受けられました。これに対して京都市として疑問を感じなかったのかという点です。労働基準法第109条では「使用者は労働者名簿、賃金台帳および雇い入れ、解雇、災害補償、賃金、その他の労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない」と定めています。NTM自身もおそらく直営というか自社のアルバイトなんとかも含めてですねあるいは自社の職員も含めてですね、この現場に働かせていたでしょうから、その点ではこのような説明はありえないというふうに思うんですけれどもいかがでしょうか。
担当部長:タイムシートの廃棄に関してですけども、令和4年9月も含めましてそれ以前タイム シートに関しては廃棄したというような説明を何度か受けております。ただ、私どもとしては今ご指摘いただいたように、その労働関係基準法とかですね、そういった関係法令の中でも保管義務があるということでございますので、私どもとしても当然あるだろうという認識のもとですね、まあそういった提出の方の依頼を何度も行っていたという ところでございます。
とがし委員:あるだろうということで何度も求めていたということですね、はい。で、それやっぱり当然の反応だというふうに思うんですね。で、これやはりですね、あのこの廃棄したっていうことを平気で言って言い直るということ自身がちょっとこう普通ではないというふうに思いますし、その点何度か問いただされたということですけれども、これ本当に廃棄したということであれば労働基準法違反するということで、法令遵守するつもりの全くない会社だとでそういうところと京都市がお取引していいのかという話になるわけですね。ですから、やはり、私はこの時点でかなり問題だったんではないかというふうに思います。で、前回の質疑であの2022年の9月分の 勤務実態に関わり11月29日にNTMが提出したシフト表と1月16日にNTMが提出した勤務実績一覧表とは全く別物といってもいい乖離した内容になっていた件についてお聞きをいたしました。NTM側がシフトを通りで働いていると説明した話は全くの嘘だったってことがこの時点で判明したんだというふうに考えますが、この点について説明を求められたでしょうか。
担当部長 あの令和4年9月分の請求に当たりましたそのシフト表、タイムシートの代わりにシフト表というものが一旦だされておりまして、その通り勤務していたというご説明でした。1月には改めてその実際の勤務状態を示す資料というものが提出されております。この際にも、私どもとしてはそれなぜ違うのかというお話は当然お伺いしておりますけれども、それに関しましては誤りであったと言ったような説明があったというところです。
とがし委員:まあその誤りだったという説明は前回答弁でお聞きしましたけど、拠点を大阪などから京都に一本化したために人が集まらず時間数が不足したというのがNTM説明だということなんですが、それならば、なぜシフト表の始業時間と勤務実績一覧表の始業時間が全く一致しないのかという疑問を感じるんです。で、シフト表では全員8時から勤務ってされてるんですけれども、勤務実績一覧表では8時15分と8時50分と9時というのが結構多数に上ってこれ非常にバラバラ、それ自身もバラバラです。けれども、極めて不自然だという風に考えますけども、この点自体いかがでしょうか。
担当部長:今回の8月以前も含めて全容解明の調査を行いました。その中でですねまあ今ご指摘いただいたようなその疑問点と言いますか、不思議に思う点っていうのは他にもございますので、そういったことも含めてですね、今後の警察等へのご相談の中では共有していきたいと考えております。
とがし委員:でまあねあの、今の時点ではそうやって警察に相談していくという話も言っておられるわけなんですけど、この出された時点でやはりこれかなり不信だというふうに思わなければならないと思うんです。で、そもそもですね、だからこれだけ違うものが出されてきたらやっぱり結局ですねこのシフト表通り働いてたと言いながら全く違う勤務実績一覧表があってで、しかも、全く様式が違うと、従ってこのシフト表なるもの自身が本当に正しいものだったのかっていうことが、シフト表としてねあったのかどうかっていうこと自身も私大変疑問になってくると思うんです。11月29 日に京都市を騙して満額を確保するために作成された文書ではないのではないかという疑念を持つんですが、この点はいかがでしょうか。
担当部長:実態としてそういうことがあるということは認識しております。ただ今おっしゃったようにその1点を取られましてこれがどうだったかっていう判断についてはちょっと私でも叱る部分ございますので、ちょっと今後の調査に生かしてまいりたいと考えております
とがし委員:私はこの時点でですね本当にまあこのコロナワクチン接種という国の税金市民の税金を搾取しようとしているということで、やはり、刑事告訴に値するものではないかというふうに思います。で、当初、固定されたシフト表についてNTMはそのシフトを提出したシフト表ですねこれ自身についてはどのような位置付けを持った文書だという ふうにその後説明してるんでしょうか
担当部長:1月にまたその誤りということで説明を受けておりますけれどもそのシフト表自体はもともとのシフト表と元々勤務用にあったシフト用だというそういうことかと思います。
とがし委員:私がなぜこういうふうに聞くのかっていうことで言うとその後のですねあのこの始業時間が8時っていうよりはもう8時15分 が多くてそのまあ9時だとか8時50分というのもあったんですけどもそこから見てもその当初からの勤務表本当にシフト表だったのかどうかっていうのも疑わしいと思うんですね。こういうシフトで想定で事業を営めないと思って計画を立てるって事あると思うんですけれどもしかし実際には全くそう違うそうではないわけで 京都市に提出する時点でこの8時からにしてるということ自身も大変 問題ではないかと実働8時間じゃなくて9時間にしているというところも、極めて問題だというふうに思います。その点ではやはりもっとそのそうした点について掘り下げて聞くべきではなかったかというふうに思うんですけども、当時京都市として本当にですねこれ徹底究明する姿勢があったのかどうか、事を大きくしないというような際は働いたんじゃないかというふうに思ったりもするんです、けれども、なぜ当時の時点で徹底して 対処することできなかったのかというふう に思うんですがこの点いかがでしょうか。
担当部長 はい先ほどからちょっと何度か答弁しておりますけれども私どもとしてはその捜査権みたいなものがございませんので空いてるが説明された内容ですねそれをまあ 特に根拠もなくですねそれは全くおかしいんではないかと言ったような指摘がなかなかしにくいということがございます。今後ですけれども今回の調査でもまあ同じように不審な点というのは出ておりますので、そういったことも合わせましてですね、今後解明していきたいということで考えております。
とがし委員:今後解明するって話なんですけど私自身が ちょっと実際見たこの勤務実績一覧表をもう1回 改めてちょっと見ておりましたら9月のものを改めてちょっと精査しました。で、これをですね、令和3年分からずっとやってくること自身がものすごく大変な作業だったと思います。けれどもこれ私が9月分しか持てないので9月、ちょっと確認したんですけどこのまあ要求資料でも明らかに拠点は9月以降ですね、京都市内一箇所に集約化されて。で、この一覧表見ていると一人の統括管理者のもとで全員が業務についているということになっているとでところがですねこのコールセンター業務に関連して複数の勤務体系が 存在して私はその点が非常に不自然だというふうに思います一部ですねの例外除いて例えば1つ目のグループは 8時15分始業して1時間15分休憩をして17時30分終業とで実働8時間と。で、2つ目のグループは9時に始業して一時1時間休憩して18時終了とで実働8時間とのグループですと。で、3つ目のグループは8時50分始業して1時1時間休憩をして 17時30分終業で実働は7時間40分ということになっているとで、果たしてですね同じ職場同じところで働いてる人たちがこんなバラバラな勤務体系で8時30分から17時30分までの電話対応業務が成り立つのかという点大変疑問に思うんですがこのバラバラな勤務体験についてもこれ当時疑問に思わなかったのかという ふうに思うんですけどもとりわけですね。これ休み時間っていうのはかなりこの職場環境を考えると非常に重要なポイントになっていて、休憩する職員がいる一方で建屋この休憩できない人がいるということはありえない話だと思うんでそういう点で言ってやっぱりこれ極めて不自然な タイムシートなり勤務実績一覧表になってるんじゃないかと 思うんですけどもこの点いかがでしょうか
局長:今先生ご指摘の先生が持ってやるタイムカードっていうものの私ちょっと状況は正直わからないんですけれども、私どもとしてはですね、NTMから出されたタイムカードの中でですね確認をしてきたわけでございます。先ほどの先生のご質問にもお答えしました通りワクチン接種のコールセンター業務あの時間帯によって様々ななんて言うんでしょうか繁忙時間帯もありますので、時間帯が何かしらズレてるからで絶対おかしいのって言われて、これ確かにずれてるって事に関しては疑義持つっては大事だと思うんですけれども。ずれてるから絶対ダメなのかって言うとですね私も調査権ない中でそこだけの判断もしかねるという状況もあろうかと思いますそういった中でですね9月分以降についてはタイムカードを求めて確認してきたわけでございますけれども、それだけでは不十分だということで8月以前分についてもですね確認をして膨大な調査をしてですねこのような形で 20件以上の問題とかも判明してきたわけでございますので全体をしっかりと全容解明して正しい道に向かっていくということで警察への通報・相談等も含めてですねしっかり対応していきたいという考えています。
とがし委員:証拠がないわけないわけでねその実際どういう運用しているかっていうのはその会社の裁量権の範囲に入っているという意味だと思うんですねでただこの8月までの調査においては同一人物の二重計上やタイムシートに記載のない金額にしたというふうにありますけれどもその そもそもそのようなずさんな手法によって辻褄合わせしている時点で私はこの9月以降先ほどの質疑もありましたけど9月以降の勤務実績一覧表とその裏付けとなるタイムシートそのものが果たして本当にこの京都市のコールセンター業務についた職員のものなのかというふうに信憑性さえなくなってしまったんじゃないかというふうに思います。その点も含めてですねぜひ徹底的に究明していただきたいと思います。それから私は今回の事態を解明する上、もう一つ大事なポイントはお金の動きでは ないかというふうに注目をしております。それぞれの実績この NTMを筆頭というか代表者とするコンソーシアム は NTMだけでやってるわけではなくてたくさんの会社が参加してると思うんですがそれぞれの実績に応じてこのNTMとその協力会社の間で、京都市から来る委託料などの分配が行われていたはずだという風に考えます。その分配とNTMの今回の報告の整合性があるのかも見る必要があるという風に考えます。京都市が契約しないはNTMだけではなくてコンソーシアム全体だということですから、従って、京都市から直接すべての協力会社から請求書の表紙と明細書を資料として提出を求めるということはできないでしょうか。
担当部長:各協力会社に関しましては直接私どもからそういう依頼を出したことはございませんでして、基本的にはNTMが取りまとめておりますので、そことのやり取りです。ただ、以前ですねその向こうからの報告の中でその各協力会社からNTMに対してのその請求書みたいなその金額ですね、そういったものに関しては提供を受けています。
とがし豊委員:明細書の提供をもらっているということですか。
担当部長 提供はありました。
とがし委員:京都市に対してそれはもう全期間について出されているということでよろしいんでしょうか。
担当部長:あの全期間ですね、令和4年8月8月以前の分、全期間。
とがし委員:そうするとそのままあの明細とそのタイムシートっていうのは符合してるんでしょうか。
担当部長:結果的にはずれているものだったと。
とがし委員:今ちょっと「ずれ」をどういう「ズレ」なのかっていうのがちょっとわからない。今、わからなかったんですけど、この今回調査結果で報告していただいたこの合計6754時間のズレと符合しているのか、もしくはそのさらにズレてるのかどちらでしょう。
担当部長:今回のズレと同じくズレれてるということです。
とがし委員:そうしますと協力会社から出されたその明細出されたものがあのNTM介して出された明細書というものはタイムシートと符合していたけれどもしかしその実績勤務実績一覧表とは符合していなくていなかったということで言うとその分がNTMのいわば、あの利益というかポケットに入ってたという理解でよろしいんですか。
担当部長:そのずれてた金額がちょっとどこに行ってるかっていうことに関しては現段階では私ども把握はしておりません。
とがし委員:わかりました。確かに実際のお金の動きがその明細書通りかどうかわからないという部分もあるとは思いますけども。わかりました。で、まぁちょっとそれでですねあとですね、このNTMは今回のコロナワクチン以外に京都市と類似の契約も結んでいるではないかという ふうに思うんですで今日私は記憶ではインフルエンザ予防接種コールセンターも受注しているというふうに思うんですで、そのこれそれでこのこれでそれでいいのかどうかこの点についてまず確認したいと思います。
担当部長:NTMとの契約状況ということで保健福祉局に限らせていただきますけれども過去にその高齢インフルエンザのコールセンターに関してもまあ受託はしてました。ただ、あの他にも何個か受けておるんですけれども、それらに関しましても、基本、総価契約という形の契約をしておりますんで今回とはちょっと違うのかなと考えております。
とがし委員:ですからいくつか契約がある中でインフルエンザも成長のコールセンターも受けておられるけれども、また、今回のような単価契約じゃなくて総価契約という方式なので単純に比較できないということだというふうに思うんですけど、ちょっとそのそうちょっと、まあ私専門的な知識ないもので申し訳ないんですけども、総価契約の場合に今回のような過大請求のような事態は起こり得ないのかどうか。その過大請求というのは片方で過大請求してるわけなんでもう片方の方で過大請求ないのかということについて確認がいるかと思うんですけど、この点いかがでしょうか。
担当部長 その他の事業でございますけれども先ほど総価契約ということで実績に応じた支払いではございませんので、基本的には調査の必要はないのかなと考えております。
とがし委員:わかりました。で、それでこの NTNが後ですね京都市と契約していた期間において他の自治体とも類似の業務委託を受けてるというふうに思うんですけどもこの点についてはどの程度の委託を受けてるかっていうのについて わかるようでしたらお示していただきたいんですがいかがですか
担当部長:本市外とのその類似のコールセンターですかね。コロナワクチンのコールセンターということで限らせていただきますけれども、京都市で把握してる分で言いますと22の自治体と契約をされていると聞いております。
とがし委員:具体的にはどこになりますか。代表的なもので示していただきたい。
担当部長:今、政令市で言いますと、福岡市とか熊本市といったところと契約がされている。
とがし委員:熊本や福岡や他の自治体を含めて合計で22ですか。22。わかりました。で、前回ですね、委員会で要求したその「コールセンターの執行体制の変遷」という資料ですけれども、これによるとNTMは京都拠点のほかに、大阪拠点1、大阪拠点2、その他ってことでこれその他が複数かどうかわかりませんけどその他っていうところで少なくとも4拠点以上に分かれて業務を担ってきたとで同時におそらくそれらの拠点では京都市以外の自治体の業務も行っていた可能性もあるというふうに思うんですね。で、そうなれば、これタイムシートについても混在する可能性もあるのではないかというふうに思われます。で、従ってですね、他の自治体とも連携して、類似の事件が発生してないかどうか照会にかけるなどの措置も必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
担当部長:現時点ではあくまでこの今回の契約に関しましては本市と受託事業者との間のものかと考えておりますしまずは必要な情報を収集精査し今警察等への相談もしてまいりたいとそんな中でその特定の都市に協力お願いするようなことがあればですね必要に 応じて連携していきたいと考えております。
とがし委員:ぜひ連携していただきたいんです。で、それからですねこのコロナ対策に充当すべき大事な国民の税金の使い方の問題として私はこれ深刻に受け止める必要があるというふうに思いますでMTMがですね22の自治体と契約を結んでいるということであればやはりですねこれは本当に京都市だけの問題にとどまるのかっていう率直にそういう心配をするわけですね。そういう意味では厚生労働省への報告だとか協力要請とかもいるんじゃないかと思うんですがいかがでしょうか。
担当部長 今回に関しましたその返還金というものが出てきますので、当然私どもの国との協議・報告なりをしていくことになりますんで、まあどういった状況であるかということに 関しましても国の方にもご報告をしていきたいと考えております。
とがし委員:国の権限も大いに期待したところなんですけれども、先ほどからねご答弁にもありましたように、まあ、おそらく国にしても、京都市と同様にですね調査に限界がある
だろうと思いますし、京都自身だけであった難しいということで、先ほどからあの繰り返しご答弁の中で警察との協力っていうことをおっしゃっていただいております。これぜひですねあの警察などの捜査機関の力を借りて全容解明していただきたいし不正はぜひ正していただきたいというふうに思いますので、この刑事告訴も視野にですね動いていただきたいというふうに求めておきます。
とがし委員:で、最後にちょっとあの委員会資料で委員長の要求したいのがありますのでちょっとあの言いたいと思います。まずは一つ目ですけれども NTMが他都市から受注している22自治体って言って先ほどありましたけどその一覧がいただきたいということで、2つ目の資料はその協力会社から請求書の表紙と明細表ですかねこれ全期間について全期間はないのかな8月以前があるっていう話ですんでそれをいただきたいとで、3つ目にこの コンソーシアムに加わっていた全協力会社の名前・所在地で業務に関わった期間ですね。それぞれの会社がで4つ目にこれ二重計上やタイムシートの裏付けのない記載というのはどのような形で記載されていたのかっていうことについてちょっと全ての事例についてまとめたものがもらえないかと。で 、5つ目に月ごとの委託業務の実績のわかるものですね、で、ちょっとぜひそれを応答率が始まりましたことを出していただきたいということです。で、あとその上でちょっと個人資料としてお願いしたいのが、勤務実績一覧表ですけどこれは全ての期間についていただきたい以上です。
委員長:ただいま、冨樫委員から要求がありました資料については理事者提出できますか。
担当部長:ちょっと今数多くご請求いただいたんですけどもちょっと詳細を確認しなければいけない部分がございますので、ちょっと出し方に関しては別途ご相談させていただいてもよろしいですかね。
とがし委員:ちょっとあのいろんな関係があるから出せるも出せないもいろいろあると思いますけど、ちょっとその辺は相談させていただいたらと思います。
委員長:はい。では相談していただいてその上で提出するということでよろしいでしょうか。
桜井副委員長(自民):全体の部分なんですが、かなり、この細かい部分まで踏み込んだような内容でございましたので、あえてそれ委員会資料で要求される必要があるのかどうかっていう風に思います。よって、個人資料としてご対応されたらご要求されてはいかがかというふうに考えます。
湯浅副委員長(公明):私の方からも今回冨樫委員が今ご指摘をされましたが、内容的にも相当込み入ったものでもあろうかと思いますし、当然お二人だと言いますか、局との間でどういったものが出せるのかとやることにも言っておっしゃっておられますので、ここで委員会として提出を求めることはそぐわないというふうに思いますから、まずは決めていただいて、その上で個人資料として取られたらいかがかなというふうには思います。
委員長:委員会資料として提出することに今ご異議あったということなんですが、冨樫個人資料でよろしいですか。
とがし委員:ちょっと今の湯浅委員からちょっとお話ありましたので確かに何を出すかっていうのがはっきりしない中で、委員会資料にしろって言いにくいかと思いますので、現時点で今言ったやつの中で即出せるという風に答えられるものについてあるでしょうか。
担当部長:NTMがその他の自治体と契約してるということでその都市の一覧でしたら私どもが把握してる分ということになりますけど、それでよろしければ出せます。
とがし委員:そうしたらですね、1点目のNTMが他都市から受注している類似事業一覧については委員会資料として要求をして、その他言いましたものについては個人資料で要求したいと思います。
委員長:今、とがし委員から変更がありましたけれども、NTMが他都市から受注している類似事業についての一覧については委員会資料でよろしいでしょうか、ご異議ありませんか。異議ありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれましてはなるべく早く提出していただくようによろしくお願いいたします。
(更新日:2023年07月20日)
2023年7月4日 新型コロナワクチン接種コールセンター委託料過大請求について(とがし豊の質疑)
7月4日コールセンター過大請求問題について質疑を行いましたが、7月18日の環境福祉委員会でも、引き続き追及します。まずは、前回の質疑のやりとりを紹介します。
2023年7月4日 新型コロナワクチン接種コールセンター委託料過大請求について
とがし豊議員(共):よろしくお願いします。ワクチンの 接種コールセンター業務を委託先である日本トータルテレマーケティングが9月だけでも少なくとも4000万以上課題請求していたという問題についてお聞きをしたいと思います。京都市には業務の関係者から通報があり、それを受けて京都市として事業者である日本テレマーケティング社に対して9月分の勤務実績を要求され、昨年11月29日に提出されたのがシフト表であり業者はそのシフト票通りに勤務させており、その実績に見合って請求していると主張して、当時の金額を請求したということで間違いないでしょうか。
予防接種担当部長:当時事業者の方から受けた説明としてはその通りでございます。
とがし豊:それで私この事業者が11月に提出したシフト表拝見いたしました。そうしますとほぼ全員が 8時から18時の勤務で実働9時間1時間休憩との記載になっています。例外的に9月1日から30日までの30日間のうち例外的に14日間だけ、コールオペレーターの方1人だけが11時から21時までのシフトに入っているということになってました。これだけ見ても、管理者が残ってるって言ったらまだわかるんですけど、オペレーター1人だけで何百人もの職場にいるということはありえないことだと思うんですが、これちょっと全体として極めて不自然なシフト表だというふうに思われるんですが、この点について再度当時これは不自然じゃないかということで確認はされたでしょうか。
担当部長:事業者の方からはですね。請求内容通りに勤務していたという説明をまず受けたということの中で私どもとしましては、その当時ですね、あの先ほどありました通りの外部からの通報といった状況もございましたので、その真偽を確かめる必要があるということで、そのタイムシートという日々の出勤状況ですね詳細に記したものですけれども、これの提出を求めました。で、ただその際事業者の方からを破棄したということで説明を受けております本市としましてはその調査に限界がある中で、求められている必要な請求書類が提出されたということで、執行期限が近いという中で支出することになったということでございます。
とがし:私ですこれでねその後京都市としては12 月に今おっしゃったように9月分を請求通りに払らわざるを得なかったと。で、その年末に日本トータルテレマーティングから連絡が入って1月5日に面談されたと いうことでお聞きしてます。その面談においてこの日本トータルテレマーケティングには過大請求を認めて、差額4000万円を返還するという表明 があったというふうにお聞きしています。1月16日にその根拠として新たに勤務実績一覧表が破棄したはずのものですけど、これ出てきたという話であります。で、その勤務実績一覧表ちょっと拝見しますと当初提出されてたシフト表と見てもあまりにも乖離するということに驚いたわけでございます。で、5月18日に保健福祉局が答弁で述べておられた「事務において錯誤があった」などというレベルない違いだと思うんですが、この点いかがでしょうか
担当部長: 1月に「勤務実績一覧」というのが改めて提出されております。その際タイムシートに関しても改めて提出されたわけですけれども、それに関しては業務を行っている協力会社というのがありまして、その事業者の方から改めて取り寄せたということで提出がされております。大きく差が出ているという点でございますけれども、事業者の方からはですね令和4年8月までは京都市内だけでなく大阪の拠点でも業務を行っていたという中で、本市の求めに応じまして9月から京都市内の拠点に集約をした。その中でオペレーターを派遣する会社が限定され配置時間数に不足が発生したというのはその差の要因であるということです。また、その請求なんですけども事業者の運営責任者これが令和4年7月に後退をしておりましたが、その際の引き継ぎが不十分であったということで、誤って実施数分の時間で請求したとです。そのことが、事業者の自主点検の中で発覚したということで説明を受けております。以上です。
とがし豊:事業者はそのに言ったんですけれども、ただちょっとその事前にもお聞きしておりましたら、その事業者単価契約じゃなくて総価契約だと思い込んで満額請求していて、それを是正するものだという説明だったということなんですけれども。ただですね、あのこれ明らかにこう全く違いますよね。で、その前と今回今回提出してきたものの大きな乖離が生まれてる原因については何という風に言ってるんですか。
山口担当部長:大きく差が出たという点については先ほどご答弁申し上げました通り、その拠点の集約化に伴って実働数が不足をしたという点だということでご説明を受けてます。
とがし豊:実働数が不足したしていたということはおそらく当時も把握をしているはずだと思うんですけれども、その点についてはもうその日本トータルテレマーケティングが委託した会社に任せきりで全く実態を把握していなかったという認識だということでよろしいですか。
担当部長:NTMとしてですね、その不足をしていた状態というのは把握していたかどうかっていう点ですかね。その点について把握はされていたものと思っております。
とがし豊:やっぱりその11月の時点で出されたっていうのは、結局、実際にきちんと実態にあった勤務実績表を出してしまうとその時点に 4000万払わなければいけないという思惑が働いたんではないかというふうに思わざるを得ないわけですね。私はその点ではやっぱり京都市が騙されたということではないかというふうに思います。それから今、令和3年2月から8月まで 昨年8月までの勤務実績一覧表と各自事業所から出されている緊密実績についても突合して精査しているということですけれども、これそれ以前、これ自身を事業者からこれだけ差額出ているというふうなことでさらに返還する意向が述べているかどうかという点を一つ確認したいということ、と。あと、そもそも9月以降のところの勤務表なんかもうあのちょっとよく見ていたら、休憩時間が1時間15分っていうのはだいたい基本なんですが、ところどころにですねその1時間の休憩しかないとかいうことで 勤務実態が違う。同じ職場で働いていたら起こりえないことが起こってるんじゃないかというふうに思うんですけれども、そういう一つの京都に一本化したと言われるんだけれどもその京都に一本化したっていうけれども、それぞれ違う体系の中で働いておられるということであればその実態なんかもわかるようにしていただきたい 。9月からちょっと一本化したっていう問題あるから9月以降の部分とそれ以前ですね 8月以前のこの業務の体系とか成功体験とかいうものが、こう分かりやすい資料を求めたいと思います。
担当部長
今の求めいただいた資料なんですけれども、その拠点の変遷というかそういう形の月次別と言いますかそういうものでよろしいでしょうか。はい、あの提出させていただきます。
委員長:答弁だけお願いします。
担当部長:あの8月以前に関してですけども現在の調査をしているところですのでちょっと内容に関しては控えさせていただきます。
委員長:それではただいまとがし委員から要求のありました 8月以前の業務体系ですね
とがし豊:委員長いいですか。8月以前と9月から体制が変わってるんで9月以降とどちらともです。
委員長:すいません。分かりました。その9月以前と8月以前と9月以降の分について資料は提出できますでしょうか
山口担当部長:提出させていただきますはい
委員長:提出できるということですので委員会資料として提出を求めることにご 異議ありませんか ご異議がありませんので委員会資料として提出を求めることに決定いたします 理事者におかれましてはなるべく早く提出 していただくようにお願いいたします。
(更新日:2023年07月16日)
関西で初となった2023年6月4日の再生可能エネルギーの「出力抑制」について議論しました~京都市会環境福祉委員会2023年6月20日
◇一般質問:再生可能エネルギーの「出力抑制」について(とがし豊)
委員長:次に再生可能エネルギーの出力抑制について、とがし委員、どうぞ。
とがし豊:よろしくお願いします。関西送配電の管内では6月4日の9時から13時30分まで、初めて太陽光発電・風力発電の出力抑制が行われました。この状況京都市としてはどういう ふうにご覧になってるでしょうか。
☞(答弁)エネルギー政策部長:はい。出力制御でございます。出力制御とは電力の需要と供給のバランスが崩れますと大規模停電などが発生する恐れがあるために供給量と需要量のバランスを取るために供給量を調整する措置ということでございます。今委員からお話ございました通り、関西電力送配電の館内におきましては6月の4日でございますけれども、休日で工場等の稼働が少なくなり電力需要が下がると見込まれる中で、好天のため太陽光発電の出力が伸びることが予想されたため関西電力送配電により太陽光・風力の再生可能エネルギーの出力制御が行われたものというふうに承知してございます。
とがし豊:九州電力の館内なんかではかなりの頻度であったわけなんですけれども、ついに出力抑制ですね、出力制御とも言われますが、この波関西に来たなというふうに受け止めたわけです。で、関西送配電の報告書を拝見してますと火力発電等を最大限抑制してもなお供給力が1615万キロワットにのぼって、揚水発電所の運転で需要を吸収してもなお1559キロワットという需要量ということで、それ以上需要を確保できないということになりまして結果として最大時で57万 KWの余剰となったと。で、その分の出力制御でが必要だったということで、太陽光と風力に白羽の速があったということでありました。この太陽光と風力による発電は、当時で言うと526万KW発電する能力があったんですけれども、その1割を捨てるということになったわけであります。一方、原子力発電所の方は出力調整が困難であるということからそもそも今回の調整の対象外となっています。当時のエネルギーの供給状況を考えた時に 結局ですね 原発3号機、高浜原発3・4号機、大飯原発3・4号機などによる供給過剰っていうものの煽りを食らったんじゃないかというふう に率直に思うんですけどこの点いかがでしょうか。
☞(答弁)エネルギー政策部長: はい今回の出力制御でございますけれども、再生可能エネルギーの出力制御に至る前に今委員からもお話がございました通り、火力発電等の出力抑制等が行われており ます今回の措置でございますけれども再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する 特別措置法及び全ての電気事業者が加入いたしております。電力広域的運営推進機関の総拝殿と 業務指針において定められております。優先給電ルールに基づいて行われているものでございます。今回はそれらの措置を講じてでもなお供給量が需要を上回るということが見込まれたことから、一部の時間帯において出力制御に至ったものというふうに承知して おります。また、現在、国におきましては出力制御の低減に向けた検討が行われていると承知しておりまして、こういったことも引き続き注視してまいりたいというふうに考えてございます。
とがし豊:注視するだけでいいのかというのをちょっと率直に思うのですね。で、今の段階で 1割この再生可能エネルギーを捨てさせられてるという状況になってまして、今後も増やしていた時にですね、一体どうなっていくんだろうというふうに率直に思うんですね。で、あの関西電力の「優先給電ルールに基づく需給解析」っていうの、政府の資料の中にありましたけど、これに、やっぱり原子力っていうのがずっと500万KW ずっとこうベースでずっと続いてるという状況があって結局こういうものが再生可能エネルギー普及の妨げになってるんじゃないかなというのを思うわけなんですね。で、供給側の問題としてですね、出力調整が全くできないこの原子力発電所っていうもの、これは障害であるというふうに思いますし、この原子力発電所をまとめた場合に電気が不足するじゃないかっていう話なんかもありますけれども、これまでも電気が足りなかった時なんかは原発ではなくてやっぱり需要調整を行うということで乗り越えるって事が十分可能なので、やっぱりこういう原発を止めるっていう決断をしていってこそ、今後ですね、この京都だとか関西においても再生可能エネルギーを大規模に導入していく上で必要なことになってくるんじゃないかと思うんですけど、この点についてはいかがでしょうか。
☞(答弁)エネルギー政策部長:はい。本市では、これまでから国に対しまして脱炭素社会および原子力発電に依存しない持続可能なエネルギー社会の構築に向けた再生可能エネルギーの主力電源化に必要な支援措置の充実を要望しております。また、指定都市自然エネルギー協議会等におきましてもこの間、系統連携線の増強や整備を着実に進めるよう求めておりまして、国においても再エネ最大限の導入促進や再エネ導入に資する系統整備等について取り組んでいくこととされております本来、元より、本市では平成24年3月の市会決議を重く受け止めまして、この間、国に対しまして脱炭素社会及び原子力発電に依存しない持続可能なエネルギー社会の構築について要望提案を行っております。今後も、引き続き、国に対して要望提案を続けてまいります。以上でございます。
とがし豊:京都市からも再三いろんな提言な提案になったとかを他の都市と一緒に協力していただいておりますけども、非常に国の動きが鈍すぎるということがありますので一層 取り組んでいただきたいというふうに思います。それで原発なんかは原発もし止めたらどうなるかと当然ですね この500万KWのベースになった部分がなくなるわけでそうなればですね 確かに夜間の電力が足りなくなるかもしれないですね、で、ただその夜間の電力が足りなくなるということは夜間に仕事をするというこの24時間社会のあり方そのものを 問うことになると思いますし、で、逆にですね再生可能エネルギー普及していけば各家庭で家庭において蓄電して夜間その午前中朝蓄電したものを夜使うということなんかもできるようになるわけですから、その点でもですね、やっぱりこの需給調整が可能な発電方式であるこうした様々なこの原発以外のエネルギーというのをこそが必要でそういうベースとミックスと いうのがいるしで当面はそういうベストミックスで行くとしてもですね、この原発以外のですねベストミックスで行くとしてもですね、あのその後ですね、最終的にやっぱり再生可能エネルギー100%していこうということになってますと京都市が行っているように送電網をもっと早期にきちっと整備するということなども求められていると思いますし再生可能エネルギーやっぱり主力電源の筆頭として位置づけるというぐらいの取り組みがいるんではないかなというふうに思いますし、この点についてはやっぱり原発をなくしてですね、排水の陣で望んでほしいということを京都市としてもしっかり要望していただきたい、というふうに思いますが、最後にこの点だけお聞きして終わりたいと思います。
☞(答弁)エネルギー政策部長:再生可能エネルギーの主力電源化を進めていく上では先ほど申しましたとおり系統連携線の増強等と合わせまして、需要側での調整と言いますか、蓄電池等についても整備これに向けた国の支援等が必要と考えてございまして、この間、私どもの方としても様々な場面で要望提案を行っているところでございます。今後も引き続き国に対して機会を捉えて要望提案を続けてまいります以上でございます。
(更新日:2023年06月21日)
陳情審査◆敬老乗車証をもとに戻して!~2023年6月6日環境福祉委員会で今年度2回目の議論をしました~全部書き起こし
◆陳情審査「敬老乗車証制度の交付基準の見直し」
委員長:ますそれでは保健福祉局関係の陳情審査を行います。陳情第4号から492号 及び493号敬老乗車証制度の交付基準の見直し以上490件はいずれも同一内容の陳情ですので一括して審査いたします。理事者説明願います。
<陳情説明>
健康長寿のまち京都推進室介護ケア推進担当部長:それでは敬老乗車証制度に関する陳情についてでございます。これまでご説明しておりますとおり、敬老乗車証制度については他の政令指定都市7市が廃止、または制度を持たない中、本市では高齢者の社会参加支援を目的とする大切な福祉施策として、制度を廃止することなく将来にわたって続けていくために見直すこととし、行財政改革計画案でのパブリックコメントを経た上で、市民の皆様の付託を受けた市会において重ねてご議論をいただき、令和3年9月市会におきまして 条例改正のご議決をいただいたものでございます。本市ではこの改正条例に基づき 昨年10月から交付開始年齢や負担金の引き上げ等の持続可能性を高めるための取り組みを実施 しており、この見直しによって生み出す財源の一部を用いて本年10月 からは敬老バス回数券の新設及びフリーパスの適用地域の拡大を実施し利便性の向上につなげていくこととしております。今後とも改正条例の議決に当たって頂戴いたしました付帯決議の趣旨を踏まえ、しっかりと情報発信や制度改正後の検証等に努め敬老乗車証制度を将来にわたって続けていけるよう引き続き取り組んでまいります。説明は以上でございます。
<陳情審査>
委員長:只今の理事者の説明について何か質問はございませんか。
玉本なるみ議員(共):よろしくお願いします。まずの行財政改革のもと持続可能な制度とするということで当初の自己負担から昨年2倍、今年3倍4.5倍に増えるということで敬老乗車証の申請数は減ると、交付率も当然下がるということは予想されておられました。昨年の負担の2倍化で交付率は 44.67%から37.67%になり7%低下になったということはもう明らかなんですが、この秋3倍から4.5倍3倍とあと4.5万円の方もいらっしゃる負担額の増大でこの交付率はどのように影響するかということは考えておられるか。まずご説明いただきたいと思います。
☞(答弁)健康長寿のまち京都推進室介護ケア推進担当部長:制度の見直しについてでございます見直しにつきましてはこれまでからご説明をしておりますが、受益と負担のバランス、それから世代間の負担のバランスこれを踏まえまして20万円の価値があるものにつきましてその利益と負担のバランス、世代間の負担のバランスを踏まえて見直しをさせていただくものでございます。今議員ご指摘のとおり交付率につきましては令和4年10月に37.67%ということでございます。けれどもこれにつきましては試算時に想定した交付率と大きく開きはないといった状況でございますので、令和5年10月から負担金2段階目の見直しをするということでございますけれども試算、検討した段階の中では、他都市で負担金の見直しをされた自治体それの負担、交付率それの状況それの交付率の状況を例にしまして試算しておりますけれども、約30%になるというふうに見込んでおりますけれども、これもご紹介のとおり、令和5 年10月からの利便性の向上を高める敬老バス回数券と見直しの新設、これ等によってトータルでの交付率っていうのを目指して引き続きしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
玉本委員:後で議論しますけども回数券を交付率に入れ込むということでねちょっとあの考え方が大きく変わるので比較が難しいくなるようなことになるということなんでしょうけど。ちょっとそれは後で議論するとして私にあの20万円の価値というふうにおっしゃるんですけどもこれは普通に働いておられて通勤定期とかに使っておられる方がほとんどだと思うんですけども そういった方々が働きながら必要とされる交通手段として定期券を買う20万と高齢者になって年金生活になっておられる方々の20万というのはねまた全く違う次元の話だと思うんですね。それを引き合いに出して、価値があるんだと言われても高齢者の20万円の得なんだから負担金はこれぐらい我慢してくださいというようなね、あの考え方をの本当に押し付けで的な考え方だと言わざるを得ないと思っております。今回の陳情者の数は500近く寄せられておりまして、私はこの市民の声の重さをしっかり受け止めていただきたいというふうに思っています。あれですよね高齢者がの暮らしというのは厳しくなる一方なんですよね。年金が下がってきているという問題またね。この間は高齢者の医療費の増大が強行されました。昨年10月から一定額のある方の75歳 以上の医療費は1割から2割になっております。そんな中で私たちも地域歩きますとね、高齢者の方が「本当に高齢者いじめの施策をやめてほしい」とでそのまあ全体の問題で言われます。なので、敬老乗車証もその高齢者いじめの一つに入っているわけですよね。あの敬老乗車証のことのみで早くやっぱり高齢者の暮らしを支えるツールとしていくつもの要素があるわけですがの支える大きな一つの敬老乗車証だという認識を持っていただきたいというふうに思っています。だから、存続させるためには仕方ないんだというのではなくてやっぱり高齢者の暮らしに目を向けて、その果たしている敬老乗車証の役割っていうものから考えていく必要があると視野を広げてこの位置付けを考えていくべきだと思うんですがいかがでしょうか。
☞(答弁)健康長寿のまち京都推進室介護ケア推進担当部長:今回陳情たくさんいただいておりまして、これまでからもいただいておりますけれども、これもこれまでからご答弁させていただいておりますけれども、そのお声といいますのはやはりこの制度を残してほしいと廃止をしてほしくないとそういったお声でもあろうかなというふうに考えております。これも説明しておりますけれどもこの制度を将来にわたって続けていくために価値としては20万円ですけれども、見直し前については多くの6割以上の方が年間 3000円で乗り放題だったということでございますけれども、やはり受益と負担のバランスとを踏まえますと、今回令和5年 10月からはその6割以上の方の負担金が年間9000円という形になりますけれども、そのあたりしっかりと負担をしていただけるように説明をしていきたいなというふうに思っております。この敬老乗車証訴訟が果たす役割、あのご指摘のとおり社会参加を支援するというものでございますので、やはりこれも申し上げておりますけれども、これを続けていくことによって社会参加支援の一つのツールになるというふうに考えておりますので、まずはしっかりと持続可能なものにさせていくということを踏まえて見直しをする中で、またこれも付帯決議で頂戴をしておりますけれども持続可能のそういう制度がしっかり 持続可能な制度になっているのかといことをしっかり点検しながら今後とも進めてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます
玉本委員:持続可能にするっていうのはこれまでの敬老乗車証制度で持続させてほしいというものであって、どんどんとこの負担金をあげて利用しにくくしといて持続可能だっていうのはちょっと市民には納得いかない話だというふうに言わざるを得ないと思っております。で、回数券のことなんですけども、回数券は私はもう敬老乗車証と全く別の仕組みであってこの敬老乗車証の交付率の対象に入れるというのに本当お門違いと思うんです。回数券そのものはやっても私はもちろんこういう制度というのはあっていいとは思うんですけども、それが敬老乗車証にかわるものではないというふうに思っております。実際、地下鉄は適用しないということになっていますし、あの負担もその半額補助ですけどもキャップかぶせて1万円までの半額補助5000円が天だというようなことも市民にとっては「なんや、そんだけか」みたいな声はもうあちこちから聞いてるわけで。これと、今まで1年間自由にお使いいただき病院にもお買い物にもそして社会参加にもご利用いただきたいとお渡していた敬老乗車証とは全く別物だというふうに思っております。地下鉄に乗れないということも含めてご見解お願いします。
☞(答弁)健康長寿のまち京都推進室介護ケア推進担当部長:制度につきましてはこれまでからやりましたフリーパス制度これを補完するものとして今回経路バス回数券というのを導入させていただくものでございます。もちろん、これは制度を見直しをすることが前提でございますので見直しをしない中では回数券というのが成り立たないということは前提でございますけれども、今申し上げましたように多くよく市バス地下鉄をご利用なられる方についてはフリーパスをご選択いただいて ただ一方でそれほど乗らないよという方もおそらくたくさんいらっしゃるかというふうに思いますので、その方の方々の選択の幅を広げるという意味で敬老バス回数券を導入をさせていただこうとするものでございますので、敬老乗車証制度の1つの中でフリーパス、それから回数券、ご自身の利用頻度、生活スタイルライフスタイルに応じて選んでいただければというふうなものでございます。今回敬老バス回数券ということでバスの回数券の導入をさせていただくものでございます。地下鉄につきましては地下鉄の回数券というのが地下鉄の券売機でしか買えないものであること、それから発行から約3ヶ月が有効期限という形になりまして既存の今の公共交通機関そういうの制度を活用しながら実施をしておりますので、あのそういった今の制度がそういう状況になっているという中で導入ついては難しいのかなというふうに検討したところでございますし、また京都の市バスについては生活路線をしっかりと隅々まで 走っていただいている部分があろうかというふうに考えておりますので今回既存の公共交通機関がある中での選択として敬老バス回数券というのを導入させていただこうというものでございますなので よくする方についてはフリーパスをあまり乗らないよという方については回数券を選んでいただくと言うべく今後とも しっかりと周知に努めていって選択をしていただけるように努力をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
玉本委員:結局ねなんかその説明一貫してやっぱりちぐはぐが出てきているなというふうに私は思っております。敬老乗車証優れた制度で喜ばれていた制度を悪くして利用しにくくしているところに関して補完するものとして回数券が出てきたというふうに説明は私はそのように聞き取れますでその上で補完するものだということで行われる回数券の中でも 地下鉄に関しては今ある回数券が3ヶ月期限なので 他のバスとは違って 適用するのは合わせにくいんだということでそこはまた 交通 局の回数券地下鉄の回数券の基準を持ってきて物差し当てるというよう なことになっていますが元々は保健福祉局が敬老の精神で高齢者の皆さんに社会 活動をしっかりしていただく必要ない病院にちゃんと行っていただけるということで 発行しているものですからねそこを貫徹した取り組みにしにくいと 接していく必要があるし利用しにくくするということ自身が問題だと言わざるを得ないと思っております なので回数券私は作ることを別に絶対的にこれはダメだっていうんではなく てこれはこれであっていいんですかだけど その保管するものとしてね敬老自動車ショーの仕組みを大幅に変えておいてそれ を保管するという位置付けではなくてね、こういう制度もありますということで プラスアルファで持ってきたら何も問題はないんですが敬老乗車証の申請を抑え込む形で出してくるということが私は問題だと思っております。もう一つ、前回の委員会で冨樫議員も行った質疑の中で紹介しましたけども、交通局のとの関係も一言申し上げたいなと思うんです。京都新聞に市長が国に対して様々な要望を出されたという記事ありましたけども、市バスの財政措置の拡充も求めて支援を要請さされておられます。私はねやっぱり市バス何としても運賃値上げは回避しなければ、敬老乗車証もそうなんですけども、多くの市民の足を奪うことになってしまうと思ってますので、これ回避する必要があると思っています。その敬老乗車証が交通局等の運営に私はすごく貢献してきている面がはっきりしているなというふうに思っていまして、この敬老乗車証の利用がどんどんと減る状況の中でまた制度が変わる中で交通局に今まで保健福祉局から入っていたお金が大幅に減るということも明らかになってきています。交通局の試算では、昨年12月23日産業交通水道委員会で質疑をしているんですけども、そこで、だいたい12億 交通局は減るというふうに試算されています。これはですね、もう少し細かく言いますと市バス地下鉄合わせると21億の減収になってでその回数券とあとICカードと入ってくる中で 9億円の増収になって差し引きということで説明を受けたんですが、これね本当に大変な打撃だと思うんです。この市長が市バスなんとか運営していこうと いうことで要請している一方で今年の中でですねあの交通局に打撃を 与えるものになっているということはもうはっきりしているなというふうに思うん ですがこの12億円に対してのご見解もご説明いただきたいと思います。
☞(答弁)健康長寿のまち京都推進室介護ケア推進担当部長:敬老乗車証制度につきましては既存の公共交通機関これの公共交通も活用して実施をさせていただいているものでございます。この交通局等にお支払いする交付金につきましては毎年協定書を各交通事業者と締結をいたしまし協定に基づきまして前年度の交付者数、これに基づき算定をし交付金を出しているというものでございます。ですので、各交通事業者を何か補助するというもので はなくて、ご利用した利用状況に応じて交付金をお支払いしているというものでございますのでそのルールに基づいて 支払って交付金を交付しているということでございますし今後もそういう協定を基づいてやっていくことになろうかというふうに考えております。その公共交通のその公共交通網の状況につきましてはこれも 前回もご答弁させていただきましたけれどももちろんあの敬老乗車証を使われる高齢者だけでない、市民全体の問題になってくるかというふうに考えておりますのでそれにつきましては公共交通問題の公共交通全体の問題として京都市全体で考えていくことになろうかというふうに考えているところでございます。以上でございます。
玉本委員:最後におっしゃった市民全体のものとしてね考えていく必要があるというところが非常に大事でありまして、それはあのちゃんとそのテーブルが用意されていて相談する仕組みがもうできているのかということを最後にご答弁いただきたいと思っているのと、どうもやっぱり縦割り行政的な感覚でご答弁いただいておりますが京都市総体として高齢者を含めた市民が交通局の市バス地下鉄の運営に大きく関わってくるということで言うと 果たしている役割っていうことでねあの私は落として落としどころを持って保健福祉局 もかかっていく必要があると思っていますがいかがですか。
☞(答弁)健康長寿のまち京都推進室介護ケア推進担当部長:公共交通の全体に全体の問題につきましては何か困難とか会議というテーブルがあるわけで はございませんけれども日頃から情報共有とかいうのはさせていただいているところ でございますので我々といたしましてもその敬老乗車証制度を扱う一員として関係各局としっかり連携をしていきながら引き続き検討等がございましたら 協力し対応してまいりたいというふうに考えております以上でございます 浜本委員それでは不十分だと思います はっきり言って結局日頃の情報共有で今のような敬老乗車証を後退させていくような仕組みに全体としてなってきたということでありますからねやっぱりあの市民の暮らしをどうやっぱり支えていくのか交通 政策を保健福祉局の立場でもものをしっかり言っていくというねテーブルを ちゃんと作っていくということね求めておきたいと思います終わります。
委員長:他にございませんか。なければ本件は陳情ですのでこの程度にとどめます。
(更新日:2023年06月14日)
カンポ跡地「用途地域の変更および建設計画の指導」についての請願審査の様子~全文書き起こし~2023年6月12日京都市会まちづくり委員会~
京都市会・まちづくり委員会2023年6月8日 とがしメモ
●委員長:それでは、請願第5号「用途地域の変更及び建設計画の指導」を審査いたします。本請願の審査については、初めに紹介議員から趣旨説明を聴取し、この趣旨説明に対して質問があればこれを行っていただきます。次に理事者から請願内容にかかる補足説明を聴取した後に審議質疑を行い、最後に請願の取り扱いについてご協議いただくことといたします。それではまず紹介議員の説明を聞くことといたします。
<請願趣旨説明>
●くらた議員(日本共産党 上京区):請願者からいろいろな思いも文書でもいただいておりますので、これを代読する形で紹介をしたいと思います。ちなみに事前に現地の調査を行わせていただきました。また左京区のご協力もいただきまして、ちょうどその西側がこの計画地になりますので、どのような実態になっているのかということも調査をさせていただいております。それでは今回の請願の趣旨ですけれども、左京区松ヶ崎にあった元株式会社かんぽ生命事業所跡地、これを、株式会社長谷工コーポレーションが買収をされたと。で、この買収土地の開発構想届が2022年 11月1日にすでに京都市長に提出がされているということであります。構想 概要ですけれども敷地約7千坪に分譲共同住宅これ406戸高さ15mの5階建てで9棟を擁する大変大きな巨大マンション建設計画であります。計画地の周辺北側西側南側すべての地域が第一種低層住居専用地域、高さでいきますと10mの制限がかかる高度地区ということになっています。で、この巨大マンション建設計画に対して低層住宅に住む近隣住民からはこの閑静な住宅地が広がる地域でございましたから、そこの環境が大きく損なわれること 日常生活面でもですね高さこの15メートル横幅150m、当初の計画ですけれども、こうした規模のマンション、コンクリート群ということで、その壁が自分たちの地域に要塞のごとくやはり圧迫感を与えるこういう大変危惧と恐れを感じるということでありました。当然、スカイライン空が小さくなる。そして、これまでの味わってきた住環境とは異なるもの になるというこういう声があるということであります。そして、やはり今回のこうした計画が起こった要因ということで見ますと、本来自分たちが住み合っている住宅地域の用途とそして、今回の建設計画地の用途・高度地区が違っているということであります。これは 歴史的な経過ということがありますけれども、1950年頃は松ヶ崎地域全体が高さ20mの建物を建てることが実は可能だったこういう地域でありましたけれども。そして、田畑が広がっている地域でしたが、 60年から70年前に宅地開発が進み一戸建てが増加し、住宅地が 形成されたということであります。京都市は1973年都市計画法に基づき一帯を低層住居専用地域に指定をしたと。ですから、今その低層住宅地域に住宅が建ちそこに住んでいるということであります。一方、現在のマンション計画地にはその当時すでに旧郵政省の建物があったためこれはその部分だけ低層住居地域から除外された状況にあったということですね。でまあ住民からすると今後の都市計画上住宅地域なのだから周辺の住宅地域との、やはり適切な調和が図れるような都市計画の手法がなぜ用いられなかったかという思いがあるというわけです。2007年の新景観政策時に高さは20mから15メートルに行ってこう高度が下げられたということではあります。けれども、元々の周辺の低層住宅地との差異が生じて、なってきたということであります。やはり計画地は、分かりやすくいますと周辺は2階建てであります。で5階建てマンションのそこに投機型であったり住居型であったりマンションの形態は様々かもしれませんが、3階以上からの目線というものがやっぱり住宅地に大変脅威があるということも聞き及んでいるところです。そういったことから先般開かれた業者の説明会、再説明会の中ですけれども住民からは何とかたとえ今の計画地の用途がそうであるにしても、我々の要望を受け止めて調和が取れる、そういう建築物としての計画の対応をいただきたいこういうふうに求めたところ、しかし、事業者側からはですね、どのように見えるかということの対策は何も法的義務は課されていないんだと、極めて限定的であって、ましてや、建築基準法上にはそのような規定はないとこういう ふうにおっしゃられたとこういったことがですね、やはり、それは法の建て付けと住民の思いにはそれだけの大きな差が生じているというところをね、京都市はどのようにこの問題を解決するのかということを問うということであります。今のところこの開発業者ですけれども、建設棟の敷地境界線から南側道路これは北線通りと言いますが11メートル幅でここで 6.5m、西側道路松ヶ崎通りですけれどもこれも11m幅ですがで7~9m、そして、北側の生活道路6m幅ですが9メートルセットバックするということで、このことについてはね一定そういう話し合いの経過はあるということであります。あとは、住民はやはりですね、高さの問題について、しかもこれだけの大きな集合住宅群がそびえ立つというね、街全体の景観は一変し印象が変わるということに対して、できる限りの調和を図る努力を求めるということであります。2007年平成19年ですが 都市の先ほども述べましたが新景観政策の高さ見直しの時、この建設土地を都市に必要な機能への配慮として、京都市は都市や地域の拠点学術研究地区等の都市生活上必要な地区について、景観に配慮しつつ一定の土地利用に配慮した高さとするというふうに位置づけたということなんですけれども、やっぱりこの一定の土地利用に配慮した高さを受けていた。元株式会社かんぽ生命事業所の高さ 15mの高度地区ということですが、2021年5月以降事業所が閉鎖し移転をするとこういう経過をたどってますからね。直近まで、その事業所が開設し営業していたというのではなくて、一旦国策としてこの事業が閉鎖をし、そして、いったんそこは機能していない土地という状況があったと。この時期になぜ近隣周辺住宅地との調和を図るという努力をされなかったのかここに住民の切実たる思いがあるということを私も現地で肌見に感じたところです。ぜひ、京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例に照らして、この巨大なマンション開発計画、適合と言えるのかと、議会の先生方の中でも十分に、場合によっては現地を調査をいただき、肌身で感じながら真摯な議論をお願いしたいこういうことであります。事業所のこの元かんぽ生命保険事業所ですけれども、この事業所の閉鎖について近隣住民が知ったのはこれも 閉鎖直前のことだったということであります。 1000人規模の人々が行き来をしていた事業所の移転っていうことですね、このこと自体も街に大きな影響を与えたという事実がありますけれども、京都市は当然、住民より相当早く知り得る立場であったと考えられますと。それならば都市計画やその後の良好なまちづくりを考慮する上で、この当該土地の用途地域及び高度地区の変更をこの土地売買が行われる以前にね、やはり、近隣住民・市民の意見を聞いてですね、検討していただきたかった。そこに、このことを行ってこなかったというところに、やはり行政の問題があるのではないか。このことが請願の趣旨であります。で、とにかく住民の皆さんの声を直接聞きましたけれども、この我々が静かに暮らし合ってきたこの周辺の住環境との調和が徹底して図れるような、そういう業者への指導を含めてですね、京都市としての責任を果たしていただきたい。このことが長くなりましたけれども、請願に込められた趣旨でございます以上です。
●委員長:ただいまの蔵田委員の説明について何か質問はございませんか。(なし)なければ次に理事者補足説明願います長尾 都市経営幹部土木担当部長着席して説明してください。
<当局による補足説明>
☛都市景観部土木担当部長:はい、ありがとうございます。それでは請願第5号用地用途地域の変更及び建設計画の市場につきましてご説明申し上げます。まずお手元の 請願文書表をご覧ください。請願者につきましては記載の通りでございます。次に趣旨でございますが、請願内容は先ほど紹介議員の方からご説明 されましたので、本市の考え方を説明させていただきます。最初に用途地域の変更についてでございます。当該敷地は第一種中高層住居専用地域 15m高度地区でございます。敷地の北側西側南側につきましては第1種 低層住居専用地域10m高度地区となっておりますが東側につきましては当該敷地と 同じ規制の第一種中高層住居専用地域15m高度地区となってございます。またさらに東側には京都工芸繊維大学の敷地といたしまして第 1種中高層住居専用地域20m高度地区が広がってござい ます 過去の経過を確認いたしますと松ヶ崎一帯は昭和8年から高さ20m規制となっておりましたが、高度経済成長期に宅地開発が進み、昭和48年の用途地域の細分化の際に低層住宅が立ち並ぶエリアについては10m 規制とし20m程度の建物が建っていたかんぽ生命跡地のあるエリアや東側の隣接する大学の敷地につきましては20m規制のままといたしました。その後平成19 年の新景観政策により、かんぽ生命跡地は15mの規制と厳しくなっております。これは当時規制であった市内全域の多くのエリアにつきまして各地域の特性を考慮した結果15mに規制を強化したものでございます。その一環としてかんぽ生命跡地の高さにおいても原則通り見直しを行ったものであり一定の土地利用に配慮した取扱いはございません。一方隣接する大学の敷地は都市の土地に必要な機能への配慮から20m規制が継続となってございます。なお当時20mから10mに規制を変化変更した箇所はございません。また都市計画の基本的な考え方として都市計画法の中でも都市計画区域について定められる都市計画は当該都市の特性を考慮して土地利用都市 施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを一体的かつ総合的に定めなければならないとされており、一つの敷地の土地利用の状況に変化があった都度ですね、見直しを行うことはございません。次に周辺の景観と調和した建築景観になるよう業者指導をすることについての本市の考え方をご説明いたします。当該敷地のマンション計画につきましては、これまで地元の皆様から 問い合わせなどについて町内の関係する部署が連携しながら 丁寧に対応を行っていたところでございます。また当該計画は中高層条例の対象であり今後の同条例の手続きにおいて周辺 住環境に配慮した景観計画となるよう指導をしてまいります。さらに当該景観規制は山並み背景型建造物修景地区であり事業者は景観法第16 条第1項の規定に基づき行為届を提出する必要がございます。この手続きに通じてですね周辺の景観に配慮した計画になるよう指導してまいります。今後 とも 各部署が連携しながら必要な指導を行ってまいります。説明は以上でございます。
<各議員により請願審査>
●委員長;ただいまの理事者の説明について何か質問はございませんか
●島本委員(南区 自民):よろしくお願いいたします。今のご説明でですね。請願の具体的なね最後の1、2の特に1に ついてよく理解はできたんですけれども全体的にですね。私達もこれについては意見ありますのでやっぱり京都市が取り組んでいかなければならない部分とかですね様々なことを思うところもありますので。まず最初ですね、この今回のこのマンションの計画に関してです。
そもそもの計画に対していつからねどういう話が始まってとかまたあの事業者さんあの地域住民の方そして市民の皆さんいろんなあのお話とかなんか経緯とかお申し出とか何かあったかもしれませんけど、その辺のところですね少しちょっと 詳しくちょっとお教えください。
☛(答弁)都市景観部土木担当部長:はい経過についてでございます。昨年11月1日事業者がまちづくり条例に基づき開発構想届を本市に提出いたしました。開発構想届に対する意見書を受け付けたところ85件の意見がございました。11月21日事業者が 同条例に基づく説明会を開催しております。本年1月29日事業者が任意対応ですね、再度説明会を開催しております。4月11日には寄せられた意見に対する見解書を事業者が本市に提出いたしました。 各種意見に対して見解書で示された内容は主に次の3点でございます。まず1つ目でございます周辺の意見、一つ目の意見でございます。周辺の住宅に比べかなりの圧迫感がある高さを低くするべき道路から建物をセットバックするべき事業者からの見解といたしまして高さ、階数は変更しませんが、できる限り道路からセットバックするとともに道路沿いの緑地をさらに広げる検討を行い圧迫感の軽減を図る。2点目の意見でございます。バルコニーから家の中が覗かれるプライバシー対策が不十分。事業者からの見解といたしましては屋上ルーフバルコニーの位置を変更し真下を容易に見下ろせないように工夫する。3つ目の意見といたしまして歩道がなく幅員6mの狭い道路に出入口が多い。住民の安全を考えた計画としてもらいたい。事業者の見解といたしましては道路のない道路に歩道のない道路に面した車両出入口2カ所を1箇所に集約する、メインエントランスを一部歩道のないコーナー部分に計画していたところを人と車の交差の少ない歩道のある道路の中ほどに変更する。見解書に対する再説明要求書を受け付けたところ38件が提出されました。5月14日事業者が再説明要求を受けて説明会を開催しております。見解書で示した見解に基づき当初構想の見直しについて説明をしております。5月 25日再説明状況報告書を事業者が本市に提出しております。以上でございます。
島本委員:なんかかなりの最初ねご説明 にあったようなと違っても結構印象的にはもういろんなことをしておられるんですね。かなり、いろいろお話し合いして地域住民の方々のご要望とか受け入れして環境のためとかにしておられるんですね。なるほど。高さ規制のこのかんぽ跡地ですか、この周辺のですね高さ規制の経緯これちょっと改めて確認しておきたいと思いますお願いいたします
☛(答弁)都市景観部土木担当部長:はい、かんぽ跡地周辺の高さ規制についてでございます。松崎一帯は昭和8年に住居地域とされそれ以来高さ 20m規制でございましたが高度経済高度経済成長期に宅地開発が進みまして住居が立ち並ぶようになった場所につきましては 昭和48年の用途地域の細分化の際10m規制となりました。一方、隣接する大学の敷地やかんぽ敷地につきましては20m規制のままとされました。平成19年新景観政策により大学の敷地は20m規制が継続となった一方で簡保跡地につきましては15m規制と規制が厳しくなったところでございます。以上でございます。
島本委員:厳しくなったんですね。先ほどの説明の中で、この事業者側の人はですね、かなりまああのご説明聞いているといろんなご要望とかにお答えする形で、再三の対応とかですね、住民の方にね、規制にはない任意の計画変更であったり、説明会の対応とかして来られたようなご説明ありましたけども、京都市としてですね、この請願者の方とか近隣住民が担当部局の皆さんですね、この近隣住民の皆さんとか請願者の方々と何らかのやり取りとかですね、してこられたのかどうか、また、されてこられたのでしたらどんなやり取りされてこられたのか、その辺のところちょっとお聞きしたいんですけど。
(答弁)都市景観部土木担当部長:都市景観部土木担当部長:請願者や近隣住民の皆様とのやり取りについてでございます。 請願者の方はこれまでから何度も近隣住民と共に窓口である都市計画課に来られましてその際には本市職員が面談し意見交換を行ってきたところでございます。また、窓口への来庁以上にですね電話でもご意見を頂戴しており、その都度丁寧にですね対応をしてきたところでございます。それぞれの対応の中で本市は「事業者には地元に寄り添い真摯に対応するよう求めていること」や「今後も求め続けていく旨」を丁寧に説明をさせていただくとともにですね、いただいたご意見につきましては事業者にもしっかりお伝えをしてきたところでございます。以上でございます。
●島本委員 わかりました。しっかりその辺やっていただいているということですが、あのこの ね 請願の文書の中ほどちょうど中ほどですね。先ほども少しお話出ておりましたけどね 2007年平成19年ですねこの新景観政策の時にですね。いわゆるあのこのかんぽ生命保険の事業所が存在していたので一定の土地利用に配慮した高さ15mの高度地区というのが設定されたけれども、この2021年令和3 年ですねこの事業所が閉鎖移転した時点で、一定の、先ほどもちょっとご説明あったかな、確認ですけどね、一定の土地利用に配慮する前提が失われたものだから、その時点で高さ規制を周囲と同じ10mに見直すべきだったのではないかというような主張されておられるんですね。ちょっと改めて確認したいんですけども、そもそも、カンポ跡地のこの高度地区っていうのですね、一定の土地利用に配慮して決められた定められたものだったのでしょうか。その辺のところちょっと確認お願いします。
(答弁)都市景観部土木担当部長:はい一定の土地利用の配慮の考え方についてでございます。新景観政策の際にはですね従来20mの高さ規制としていた市内全域の多くのエリアにおきまして原則として規制を15mに強化させていただきました 一方でカンポ跡地の周辺で言えばですね、京都工芸繊維大学の敷地につきましては、従来の20m規制のままとされてございます。これは当時市街地全域での高さ規制の見直しについて都市や地域拠点学術研究地区などの都市生活上必要な地区につきましては景観に配慮しつつ、一定の土地利用に配慮した高さとする、との方針の中でですね。左京区におきましては、地域の拠点となる商業地や学術研究施設の高さにつきましては現行のままとするとしており、その対象の中に京都工芸繊維大学が含められたものでございます。その中には、カンポ敷地の高さ15mの高度地区は一定の土地利用に配慮した高さとして位置付けられたとございますが 、実際にはカンポ跡地につきましては一定の土地利用に配慮した高さの規制は設定は行っておらずですね、地域市内全域の多くのエリアと同様に、原則通り20mから15mに規制を強化したものでございます。以上でございます。
●島本委員:はいわかりました。まあまあここまでの部分はねあの確認なんですけどね。私はね重要だなと思いますのは実はですね。報道でもあったし京都市のことですからあのご存知かと思いますけれどもね。6月1日 京都市の伏見工業跡地の件ですね、京都新聞でした、これ朝刊に載ってた切り抜きなんですけどね、あのこういうようなね、大きな街の開発、これ新聞報道にあった部分、これは京都市の周知のことで今回民有地この差はあるそういった差はあるかもしれませんけどね、大きなねあの住宅開発、まちの発展のためのですね、こういったことに変わりはないと思うんですけれども、こういったこの伏見工業高校跡地ですね、これ京都市がいわゆる環境型のですね23これからの時代のですね。いわゆる二酸化炭素排出量0っていうのを 目指した住宅街の整備に乗り出すということこの掲載ありましたけれどもねで今回のねこういったマンション計画もねこれを民間の開発ですけども京都市もいろいろ指導する立場ですけどね これからというか今はもうねあの本当にこういう環境問題とかですねいわゆる脱炭素などの取り組みにね貢献するようなものにねすべきだなと思ってるんですけどもこれはそういうようなことになっているのかなっていうようなことが1点思っております。そしてですね、また、あのそれ以外でもですね、この事業者このマンション計画に先ほどもちょっと環境のこととかセットバックのお話もありましたけどね、工夫しようとしているようなことですね、せっかくそういった工夫があるんであればですね、もしもあるんでしたら事業者もそれを地元にちゃんとね丁寧にあのしっかり説明すべきと思うんですけれども、その辺のところが重要だなと思ってるんですがいかがですか
(答弁)都市景観部土木担当部長 はい事業者の工夫についてでございます。伏見工業高校跡地でのですね本市の取り組みである脱炭素の取り組みといたしましては今回民間事業者においてもですね同様に例えば、ですけども共同住宅部分のエネルギー収支を実質ゼロするような省エネ性能の確保であったり、太陽光発電設備の設置電気自動車の普及を見据えた充電設備の設置などを今後検討していくと聞いております。先生ご案内がありましたそれ以外の案内につきましても住居者の従業者に自治会への加入を働きかけ地域活動への参加を促すこと、約1200m2規模の公園を整備し地域の方の潤いの場を創出すること、敷地避難東部に地域の良質な賑わいをもたらす店舗の誘致を図ること、敷地内に歩道上空地を設け周辺の歩行者の安全を図ること、といった取り組みを通じまして地域に貢献したいとも聞いております。先般説明会ではですね、事業者はただいまご説明を申し上げました脱炭素の取り組みに加えてですね、松ヶ崎地域のここ10年の国勢調査の結果を見ますと人口推移は横ばいですが若年層や子育て層につきましては減少をしていること、マンション計画で若い世代も増えるので地域にとって活性化が図れるプラス面などもあること、さらにですね、このように事業者は単にマンションを建てるだけではなくマンション事業を通じて地域の活力を高めることに貢献したいとの思いを地域の皆様に丁寧に説明したと、聞いてございます以上でございます。
●島本委員:その最後の部分ね、それそれそういう大切なことをしっかり今回狙っていただいてるみたいです。京都市もね、今後都市計画局、今までね、あのこんなこと言ったら悪いかもしれませんが都市計画局、法にのっとってここにこういう建物建ててよいかどうか判断しておられたかもしれませんけれど、だけじゃないと思いますけどね、やっぱりあの環境政策局、今の話そう環境政策局もですし、例えば文化市民局で地域コミュニティの活性化京都市がいろんな問題抱えてますよね一番はやっぱりさっきからもずっと話出てるように新しい世代とか子育て世代の市街流出であったりね住むところの問題とかそういったことをね人口減少の問題高齢化少子高齢化の問題様々取り組まなければならない多くの問題を抱えています。当然環境問題もそうですし、地域の活性化の問題もそうですし、いろんなことがあると思います。そういったねまたこれから高齢化の方が高齢者の方々のねまたあの健康長寿 のね取り組みそして子育てもちろんですよ福祉のこととかねそういったこと全てね、いろんなあの地域課題にですねいかにですねこの問題に解決に資するかという取り組みもですね非常にこれ一軒に二軒のを家を立てられるって言うんじゃなくて、やっぱりこの大きな一つの町を作るというような非常にある意味は京都市にとってねあの地域にとってもそしてまたねあの市にとってももう嬉しいありがたい大きなお話であると思う んですね。しかし、ただ単に作るだけじゃなくてこれからは今言ったようなね多角的な働きかけていうんかな 京都市としてその辺が今後非常にあの重要になっていくと思っておりますし、考えますし、絶対にこれしなければならないことだと思いますけれども、都市計画局とされましては、その辺どのようにお考えか、その辺ちょっとお伺いしたいお願いします。
☛(答弁)都市景観部土木担当部長:今後の対応についてでございますがこれ までは本市から事業者に対してまちづくり条例の手続きの中でですね、地元に真摯に対応するよう強く求めてきたところでございます。またあの本件マンション計画は中高層条例に基づく届出や 景観法に基づく届け出の対象となって ございます。現時点では当然それぞれの手続きに入る前の段階ではございますが この早い段階からそれぞれの担当部署が事業者に対し周辺の住環境や景観に配慮した計画になるよう検討を求めてきているところでございます。 事業計画の構想段階におけるまちづくり条例の手続きは事業者からの再説明状況を報告書の提出を持って終了いたしましたが今後、計画の熟度が上がった時点におきまして中高層条例や景観法に基づく手続きがでございます。中高層条例に関しましては事業者に対し同条例の趣旨に基づく基づき周辺住民と十分協議をしながら、近隣への日照通風による影響の軽減や観望の対策などを住環境に配慮した景観計画になるよう指導してまいります。加えてですね 景観に関しては「山並み背景型建造物修景地区」に指定していることから同地区のデザイン基準を踏まえ事業者に対して例えばですけど、外壁面の分節や色彩・素材など具体的なデザインの工夫、さらに道路沿いの植栽計画など周囲の景観に配慮した計画の協議を進めてまいります。最後になりますが、このように今後の手続きの中でも議員ご指摘のように地元の皆様の思いにいしっかりと踏まえながら事業者に対して強く要望をしてまいります。以上でございます。
島本委員:その辺のところですねしっかりちゃんと取り組んでいただきたいと思いますがね。 これあの何もこの地域松ヶ崎の今回のことに限っただけのことじゃないですよ。念押しておきますけども例えばちょっと話それて申し訳ないですけど、私ずっと訴え続けております。その前に似たような話がね塔南高校跡地どうするんやっていうようなことも、あのずっとこないだの代表質問でも訴えさせて要望を出させていただいておりますし、そしてまた あのずっと訴えつつ、もう10年以上になりますけど西大路十条というところにね、これはもうここにも1万坪の土地がそのまま今回やっとですね、ちょっとの期間あのサーカスやってをずっとして欲しいんですけど本当はね。企業誘致にしてもマンション建てていただくにしても、あのそういった観点で先ほど申し上げたような観点でまちづくり文化的な地域の貢献に地域の発展に資するような取り組みということにしていただきたいと思っておりますし、このことだけじゃなくて京都市全体のことで南区のことだけじゃ なくてですねぜひ取り組んでいただきたいと思っております。今回の請願内容についてはね特に1番のところなんかについては最初の局の説明でもねよくわかっておりますけどね特にこの 今おっしゃられた2番の方ですねしっかり とですねこれからもあの努力してこられたと同じようにですねまあ請願の可否いかんにかかわらずですね このマンション計画都市計画だけでなく今言うたような観点からですね、このうち 今回はこの松ヶ崎地域ですねそして ひいては京都市のまちづくり未来を大きく絶対に貢献するようなものと なるようですね皆さん方には絶対この事業者に対してね、しっかりと市で指導していただきたいと今決議述べられましたけど またあの何回も繰り返しになりますけれどもねあのこの事業者に対して地元の皆さんの思いをしっかりと丁寧に答えながらですねあのいろいろやっていただいてはいるようですけど、丁寧にご説明とお答えしながらですね、取り組みを進めていただきますようご指導ですね、皆さんからはしていただくようにお願いを申し上げますということでね私 の質問これで終わらせていただきますので よろしくお願いいたします
●森本委員(維新・京都・国民 伏見区):これまで経緯とか取り組みルールご説明本当に詳細にいただきましたので私の方 からですね請願に関しての事実関係とかの質疑ではなく、これあの今もお話ありましたようにこのまちづくり、そもそもまち作りっていうことできますと、やはり地元の方住民の方に十分納得していただく。これが一番大事だと思いますし、引いては地域の活力を生み出していく、そのために皆さん日々取り組んでおられるということは十分理解しております。本請願に関しても地元では過去にない大規模な開発でありまして学区の人口が1割以上も増えるもので、またあの景観今までも散々出てますけども経過もそうですですけれども、当会派におきましても左京区選出の議員が3名おりますので、実際に地元の様々なご意見やご不安こういったお声もですね 我々の会派の議員にも届いておりますので、ぜひですね、当然あの事業者が地元の方説明というのもあるんですけどもぜひ従来よりもですね、さらにですね本市の方々にも頑張っていただいて間に入っていただきまして、様々な場面がこれからも想定されると思いますので、丁寧にですね、ご対応いただくとともに事業者に指導を行っていただきたい。そういうことを考えておりますけども、その点についてご見解をお伺いしたいと思います。
☛担当部長:はいあの 繰り返しのご案内になって申し上げないですけ、どこれまでから我々は事業者に対しては地元に寄り添って対応することっていうのを申し入れてきたところでございます。この手続き面での業者の申し入れてきた内容っていうのはこれまで からもこれからも変わることなく地元の皆さんにしっかり寄り添うことと我々の業務といたしましてはそういう風な説明が丁寧な説明を事業者がやり尽くしているかという観点で厳しく点検をして指導の方をしてまいりたいと考えている次第でございます以上です。
●森本委員:ありがとうございます。今までの強いですねご決意というかこれからの取り組みも述べていただきましたので本当にそれをご丁寧 にやっていただくことをお願いしまして私の 質問ではございませんけどもお願いとして終わらせていただきます以上です。
●平井委員(日本共産党 中京区):先ほどもやり取りかなりされていましたけれども事前に指導をかなりされてこられたっていうことや、それだけ影響のある大きな建物だということの認識だというふうに思うんですけれども、まあ指導状況やどのようなやり取りされてきたかということは縷々述べられましたので、まずは今後も継続して指導を同じように行うことを求めたいというふうに思いますし、地域の皆さんのそのいろんな思いを受け止める形でぜひ調整役としてやっていただきたいというふうに思いますし、同意がどこまで取れるのかっていうのはあると思うんですけれども、同意が取れるところまでどうもっていくのかっていうのもぜひあのいろいろ考えていただきたいというふうに思います。 あのまあ請願された地域はですね。それぞれの区域ごとに用途地域や高度地区の図も見せてもらってますけれども、やっぱり確かに20mの地域とその15mの地域と10mの地域と分かれているわけでありますけれども、やっぱりこの地域のど真ん中に15mの地域があってですね、いろんな割合が違うっていうことでありまして。例えば容積率で言いますと、住民から出されている地域は容積率は80%で、今先ほど総合庁舎やこのかんぽの跡がある地域は200%になっているということが一つと、高さで言いますと周辺住民は10mの高さになっているとカンポ跡地は15mになっているということで、容積率と高さが違うことで、まちなみに大きな影響。その以前はね、もちろん影響あったと思うんですけれども、影響を与え続けてるっていう事でこの5mの差がねやっぱり住んでる人にとっては生活環境を害してるんじゃないかと思われているわけでありまして、法令上そのどうかっていう話よりもですね、都市計画そのものはやっぱり住んでいる方々にとって、こういう違いがあれば大きな影響があるというふうに思うんですけども、この単純な認識については今お聞かせいただきたいと思います
☛(答弁)都市景観部土木担当部長:都市計画の基本的な考え方だと思うんです けど先ほど従来ご案内させていただいている通り、まずあのこのところにつきましては繰り返しになりますけども、カンポ跡地の高度地区につきましては一定の土地利用に配慮した高さに付けられたものではないということでですね。 改めてご説明をいたしますがその際には市内全域の多くのエリアに同様の原則通り20m 規制から15m規制に 強化したところでございます。議員ご案内いただいたように確かに請願者の方とのですね差では10mと15mという風に高度地区が異なるのは 事実でございますですが、これも過去からの経過をずっと説明して改めて説明はいたしませんけれども、そもそも我々としては行って規制を強化しての範囲であって特別扱いをしてきたところではないということと、もう一つ都市計画の基本的な考え方でもご説明させていただきますけど、まずは都市計画法の中でも都市のその健全な発展と秩序あるその整備を図るために一体的総合的に定められなければならないとされておりまして、一つの敷地の土地利用の状況が変化があったとですね、変更を見直すことはしてなくて、都市計画自身がそういうふうな見直しを行うものではないということでご案内申し上げます。以上でございます。
●平井委員:かなりねこういう所っていうのは経過があると思うんでよね。その10mの地域と15mの地域に分かれるっていうのは元々の経過があったと思いますし、まあ言えば、元々の建物が建ってる時にですね、そこであの害されている方々もたくさんおられる、というのと今回の変更でそれが変わるという方々ももちろんおられるわけでありまして、あのこの経過がもう一つわからないんですけれども、特別扱いはしていないっていうことで言われたんですけど、もちろんそうだとは思うんですけれども、住んでる住民にとってね、その変化がどういうふうにあるのかっていうのはよく見ていただきたいというふうに思います。150m近い 敷地なんですよね。ほぼ正方形の。やっぱりそういう敷地を開発することで容積率も含めてですけども15mが連なるという部分が増えてくるわけでありまして、 そういうことになると、先ほどもちょっと述べられてましたけども、今後の課題だとは思うんですけれども、日照とか風とかですね、あの例えば車両の通行量なんかも含めてですね、影響を及ぼしてか環境一変させるようなものが出てくると、あのよく可能性は非常に大きいわけでありまして、また、あの景観で言いますと、五山の送り火なんかはですね、逆に言うとマンションの人だけ見えるっていう事もありうるわけでありまして、これまで見えてた人が見えなくなってマンションの人がそこを見るっていう形になってくることもあるわけでありまして、こういう住民の方々の危惧してる点についてどう考えているのか。今後のところどういうふうに思われてるのかちょっと教えていただきたいと思います。
☛(答弁)都市景観部土木担当部長:まずあのこれまでの指導のあり方でございますけども、まずあの事業者に関しては議員ご案内ございましたように地元の方が不安に思われている点につきましてはこれまでから真摯な対応を地元対応を求めていることと我々の業務の中でも事業者が地域に対して丁寧に説明を尽くしているかという観点で点検しておりまして、これはこれからも変わりません。これまで通り変わることがないというふうに考えています。またあの具体的な手続き面でもご案内いただきましたけど、繰り返しのご案内になりますけど例えば中高層条例に基づいた指導であったりとか、もう一つ言うと景観のその指導についても山並みの、失礼しました、第16条の第1項に届出がございますので、そういった今後の手続きの中でしっかりと事業者の方には指導してまいりたいと考えているところでございます以上でございます。
●平井委員: まああの法律の枠組みとしてはですねあの一定立て付けがあってですね、そこに基づいてやられるということなんですけども、それ以上にね、住民の方々がいろいろ求められる部分というのがあると思うんです。そういう部分もちょっと加味しながらねやっぱりどういう風に調整していくのかというのはよく考えていただきたいなというふうに 思います。あの先ほども報告議案でですね大規模都市計画の見直し行うことが進められてますけども都市計画の見直しというならば住んでいる人との関係でねやっぱ都市を形成していくということが、僕が一番重要だなと思っておりまして、公の施設がここの地域この15mの地域 は集積しているということで、まあその建物等の配慮なんかはですね、この低層住宅地域とは違うわけでありまして。そういう差がやっぱりどこまでも出てくるということは住民との対立を生むということも、やっぱありうる話なんですよね。開発中心に置かれることなく住んでいる方々が住み続けられるように指導するべきだと思いますし、多分そういう方向でやるっていうことで言われると思うんですけども、ぜひそういうところをやっていただきたいということと、歴史的にねやっぱり元々はあの田畑が広がってる地域だと思うんです。現地見て来ましたけどやっぱ水路とか結構あの昔の機能が残ってるところでありまして、そういうところから先ほど説明あったように昭和48年に10m規制にしたということは、それまでのその宅地開発がかなり進んだということで住宅が作られて今その中での平和な暮らしが営まれているということでありますし、山に近いということで見たらやっぱり本当に風景いいんですよね。近くに山が見えるっていうことで、京都の良さがを感じられるっていう事でありまして、こういう環境を残していくことが僕は自治体の責任だというふうに思いますし、住民の方々からの提起を重く受け止めてですね、やっぱり、いろいろ検討しながらやっていくということが指導もしながらですけども、いろいろ 検討していくということが非常に大事で、そういう観点はぜひ重く受け止めていただきたいなというふうに思っております。
●井崎委員(無所属、左京区):よろしくお願いします。あの昨日、井上課長からいろいろヒアリングさせていただいて、こういう質問しますねっていうのは、もうほぼあの今出尽くしたので、私あの新人なもんですから、あの今まああのずっと質疑を聞いてて、率直に思ったところ、まああの5月14日の説明会にはあのどなたか市から参加されたんでしょうか。
☛(答弁)都市景観部土木担当部長:あの5月14日の説明会の方については出席してま・・・、ただし、それに至るまでにですね事業者とはですねしっかりとどういう風な説明をするのかであったりとかっていうのは密に協議してきたところでございます以上でございます。
●井崎委員:はいありがとうございますやっぱりあのかなりたくさんね。あの100名近い方ご参加されてすごく紛糾をしていました。であの先ほどからのこの用途地域とか高さ規制っていうのは、現状ではしっかり指導していただきつつですけど、あのこの請願者の方以外にあのお電話とか私もいただくんですけど、要するにその松ヶ崎通りと北泉通りが非常に狭い通りでそこに面してるとこが5階建立っていうのが非常に圧迫感があると、この建物のこの敷地の中がねもう少し高くなる分にはあの問題ないかもしれへんやけどっていうのは声もいただいたんですね。で、あのまあ新人なもんですから率直にちょっと質問させていただくんですけど、5月の議会で地区計画のあの面積が狭い範囲でできるようになりましたよね。逆にあれをまあ活用してですよ、これ今 15m規制やから事業者としてはギリギリいっぱい採算を取るっていうか利益を出すために全部15mで 計画してますよね、これはあの道に面しているところを下げてで地区計画を立てて住民の方ともちろん相談ですけれども、地区計画で中を上げるっていう可能性はあるんでしょうか。
☛あのまず最初にですね今晩5月市会でご審議いただいたやつについては小さな敷地の地区計画でございますので今回このやつについては元々が2.2ヘクタールございますので、そもそもが前からこういう風な取り組み地区計画提案制度は活用できるということをご案内まず申し上げます。それと地区計画のその趣旨でございますけども地域の目指すべきビジョンをまず作っていただいてそれで 地域の皆さんがご理解いただけるというのが前提でございますので言語のご案内 いただいたりそのこの地域に限らずですねこういう風なその地域についてはそういうふうなまちづくりをしていこうかっていうことの合意が得られるのであればあの可能ではございますけど言ってこの地区で言うとなかなか難しいんではないかなというふうに考えています。以上でございます。
●井崎委員:地区計画ってねあの風俗営業店を入れないようにとかそういうことで活用もされてきたと思うんですけどあの地域住民の何割の方の要望があったらあの実現するんでしょうか
☞(答弁)都市景観部土木担当部長:都市計画提案制度はそもそも3分権利者の方の3分の2の同意があったら可能なんですけど、地区計画自体は周辺の方も含めて同意をいただく必要がございますので、今ご案内申し上げたように概ね周辺の方も含めてご同意が必要というふうに考えていただいてたらいいとと思います。以上です。
●井崎委員:周辺の方要するにこの地区計画って地権者の方からの要望もあると思うんですけど周辺の方があの例えば地域住民の人口からして何割やとその提出できるとかそういうのはじゃない今 決まりはないということですか何割とか何人とか
☞(答弁)都市景観部土木担当部長:ご案内申し上げましたように地権者の3分の2の同意があれば提案できます。はいありがとうございます。
●井崎委員:つまりはその京都市の方がやっぱりそのコーディネーターという役割をしっかり果たして、かなり紛糾をしているということは、あの法的に問題なくてもやはり非常に残念に思う地域住民の方多いと思います。で、この地域のやっぱり住民自治のね歴史っていうのをあのしっかり重く見ていただいてぜひこういうやり方もあるんじゃないだろうかっていうそういう知恵を絞って住民の方の 相談に今後も真摯に向き合っていただけたらと思います私もまあもう少し地元の方 の声も聞いてまたご相談したいと思います。終わります。
<請願の取り扱い>
委員長:取り扱いはいかがいたしましょうか
●自由民主党:この請願書に対しましては不採択でお願いします。
●維新・京都・国民:私どもも請願者のお気持ちは十分理解しているんですけども本件は不採択でお願いします
●日本共産党:今日ね初回の審議で各会派からいろいろと議論がされましたし、また京都市としても今後中高層条例や景観条例にも基づく指導を丁寧に行うと、そして事業者については地域住民との合意形成に向けて引き続き努力するというふうにもおっしゃっておられますし、まだまだこれ経過を見ていく必要があるんじゃないかというふうに思うんですね。それで私どもはぜひ継続しての審議を求めます。どうしても採択を今日取らなければいけないのかということをお考えいただきたいと思います。また今日の議論の経過も踏まえてですね、請願者とも例えば陳情への切り替えということも含めて少しやり取りをさせていただく時間の猶予をいただきたいと思います。以上です。
●公明党:私どもも不採択でお願いします。
●立憲民主党:不採択でお願いします
●民主市民フォーラム:不採択でお願いします。
●無所属井崎委員:私は留保でぜひお願いしたいと思います。
●委員長:それではご意見が分かれておりますので まず 留保か否かについて、評決を取ります。まず本請願は本日結論を出さずに留保とし継続して審査することに賛成の方は挙手願います。(挙手:共産2、無所属1)少数でありますよって本請願は本日結論を出すことといたします。それでは、まず自民党不採択、維新京都国民は不採択、公明党は不採択、 立憲民主党は不採択、民主市民フォーラムは不採択でよろしいでしょうか(はい)。留保と答えた会派へご確認いたします。共産党はいかがいたしますか。
●共産:採択すべきと主張いたします
●無所属の井崎委員:採択でお願いします。
●委員長:それではご意見が分かれておりますので評決を取りたいと思います。なお表決につきましては採択・不採択の順に挙手を求めますが、採択不採択いずれも少数の場合は審議未了の扱いとなりますので、ご承知おき願います。それではまず本請願を採択することに賛成の方は挙手願います(少数挙手)。少数であります。次に本請願を不採択とすることに賛成の方は挙手願います(多数挙手)。多数でありますよって本請願は不採択とることに決しました。以上で請願審査を終わります。
(更新日:2023年06月12日)
敬老乗車証制度を元に戻してほしいという市民からの陳情を話し合いました~敬老乗車証、実は公共交通や地域経済を支える縁の下の力もち~2023年5月22日京都市会環境福祉委員会
◇陳情1、2号 敬老乗車証制度の交付基準の見直し
◉とがし豊:よろしくお願いします。敬老乗車証は、昨年の9月の更新交付から本人負担が2 から3倍に値上げになりました。今年はさらに3倍から4.5の値上げが予定されており対象年齢は段階的に75歳まで引き上げられる予定で、昨年は第1段階として70歳から71歳に引き上げとなりました。敬老乗車証の交付数は実数では 2万4935人の減少。交付率では44.67%から37.67%に大幅に下落をいたしました。申請者の65%を占める負担金3000円の市民税非課税世帯は6,000円の2倍に値上げをされ、次いで多い22%を占める所得額200万円未満の世帯は5000円から1万円の2倍に値上げをされましたが、それぞれ交付率が7.6%も減少するということとになりました。今回交付を断念された高齢者の方にお話をお聞きいたしますと、「もう高くて払えない」と、「よっぽどのことがないと外出できなくなる」ということでした。また、今回なんとか申請できた117,711人の方の中にもですね、今後さらに3倍から4.5倍に値上げとなれば交付申請を諦めるとおっしゃっている方が多数いらっしゃいます。これh、社会参加を促進するとした敬老乗車証制度の趣旨に反する事態が生まれてるんじゃないかと考えますが、この認識はいかがでしょうか。
☞(答弁)健康長寿のまち京都推進室・介護ケア推進担当部長:敬老乗車証制度の見直しについてでございます。これまでからご説明もしておりますけれども、この制度につきましては昭和48年に創設されたということで、その当時、発足から50年が経過しているという状況でございます。当時に比べまして、平均寿命が11歳伸び、対象者も8万人から32万人に増加をしているということで、本制度を取り巻く社会情勢というのは大きく変化しているということでございます。また、開始当時の市税負担は3億円であったものが令和3年度では52億円になるといった状況で社会情勢の変化、それから高齢化の状況、そういった状況が非常に変わってきているといった状況でございます。こういった変化の中で、従前の制度のままでは制度が破綻する恐れがございましたことから、本市におきましては、他の政令市等が廃止、それから制度をもともとないと言った状況の中でも、本市は将来にわたって続けていくために見直しを実施するということとしまして、令和3年9月の市会において条例改正のご議決を頂戴したところでございます。社会参加を促進・支援していくという趣旨でございますけれども、社会参加につきましてはこの敬老乗車証制度を使って市バス・地下鉄等にお乗りになられる、これだけで社会参加ができるというものではございません 。徒歩で社会参加されるという場合もございますし、また、自転車と使われるといった場合で、敬老乗車証につきましては社会参加の一つのツールとしてご自身の生活スタイル、ライフスタイルに応じて使っていただくものかというふうに考えております。この負担金につきましては、先ほど議員からご紹介もありましたけれども、6割以上の方が見直し前では年額3,000円ということで月250円のご負担で乗り放題という状況になっておりましたが、受益と負担のバランス、それから世代の負担のバランス、こういったことを踏まえまして、令和5年10月以降については6割以上の方の負担金額が年間9000円と月750円でフリーパスでお乗りになれるといった制度という形になってまいります。今後ともいただいた付帯決議を踏まえまして見直しの趣旨の周知でありますとか、この令和5年10月からの敬老バス回数券等の新しい取り組み、これをしっかりと周知をしてまいって、未来に向けて引き続き続けていける敬老乗車証制度になるように、引き続き、取り組んでまいります。以上でございます。
◉とがし豊:敬老乗車証だけが社会参加ではないというふうにおっしゃるんですけれども、現実に敬老乗車証があるから買い物に出かけることができるという方いらっしゃって、本当にね、高齢者にとっては、この自転車も乗れないような状況にある中で、バスだったら安心して乗ることができるということになるわけなんで、私は間違いなくですね、この京都市が今回行った措置によって社会参加を損なわせているというふうに指摘しておきますし、この点については皆さんも否定できないと思いますが、その点はやっぱり実際しっかりと受け止めていただきたいと思います。で、今の敬老バス回数券の導入によって今後交付率が上がっていくという話があったかと思います。で、一定の負担金を支払って交付された段階になっても無料という敬老乗車証とは根本的に異なるものだというふうに考えますし、これでもってこの敬老乗車証の負担金の値上げ、あるいは年齢の引き上げによって奪われたこの市民の皆さんの足を取り戻す代替になるものではないということを指摘しておきたいと思うんです。あの敬老乗車証制度においては実際に利用した人数・頻度に応じてその総額を京都市の一般会計から交通局や民間バスなどの事業者に補助金として支払う形を取っています。敬老乗車証制度の改悪によって利用者が減少すると減収、その分の運賃収入が減少して市バス・地下鉄・民間バスの経営に直接影響が出てきます。そのため最終的にですね、今回、敬老乗車証制度改定が完了した、今から言うと8年後になるかと思いますが、単年度収支への影響について、京都市交通局は昨年12月23日の産業交通水道委員会での委員会質問への答弁として、市バス地下鉄合わせて21億円の減収になり、新たに今年から導入されたされる敬老バス回数券と現金・ICカード利用に移行する方で9億円の増収はあるものの、差し引きで12億円の減収になる見込みだという風に答弁をいたしております。で、つまり、この12億円の減収というのを片道のバス料金230円で割りますと 521万7千人の減ということになります。365日で割ると1万4000人の利用者の減となると。それだけ多くの利用者の利用の萎縮効果が出てしまうということでありますので、敬老と高齢者の社会参加を後退させるという今回の負担金の値上げ方針は撤回すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
☞(答弁)健康長寿のまち京都推進室・介護ケア推進担当部長:今回の敬老乗車証制度の見直しについてでございます。今回フリーパス証等の負担金の引き上げ等の行いますとともに、先ほどもご紹介をいたしましたけれども 敬老バス回数券等の新設というのを行ってまいります。これにつきましては、フリーパス、敬老乗車証は市バス・地下鉄等をお乗りになられないという方については、これまでから敬老乗車証をお持ちでない方もいらっしゃったかと思いますし、敬老乗車証、これまで持っていたけれども例えば今年はもらわなかったという方々については、フリーパスの負担金ほど乗らないという方がいらっしゃるかと思います。そういった方の選択の幅を広げるという意味で回数券を導入することで、あまり乗らない方の選択肢の幅を広げるという意味ではこれも社会参加の一助として敬老乗車証制度の一つの枠組みという形だと、私どもは認識をしております。交通局等の負担金というご指摘もございましたけれども、この敬老乗車証制度につきましては、既存の公共交通機関、交通局をはじめとした公共交通機関これの交通網の枠組みを利用して、それぞれの公共交通の協力を得て実施をしているものでございます。交通局への補助という形で実施しているものではございませんで、協定に基づいて決めた協定の交付金というのをお支払いをするという形になっておりまして、公共交通そのものが今後その京都市全体としてどうしていくかにつきましては、我々保健福祉局を含めて京都市全体においてそういうふうに考えて取り組んでいくことだというふうに考えておりますので、公共交通の全体の問題については、我々も交通局さんそれから都市計画局さんと関係の局とも連携をしながら引き続き取り組んでまいりますし、敬老乗車証制度につきましては、いただいた議決をしっかり踏まえつつ、また、付帯決議もしっかり踏まえながらこの 見直しというのをしっかり進めていくのが我々の責務だというふうに考えております。以上でございます。
◉とがし豊:他局ともよく協議したいという話があったんですけれども、敬老乗車証という制度が実際に果たしてきている役割っていうのを見る必要があるというふうに思うんですね。京都市内の市バス・地下鉄そして主に京都市内周辺部の交通を担う民間バス・コミュニティバスの経営を支える縁の下の力縁の下の力持ちとしての役割を果たしてきたっていうのが実際の姿です。敬老乗車証でバスに乗って地域交通が支えられ、その地域交通があるから高齢者の方が京都の様々なところで公共交通を利用して、敬老乗車証を利用して公共や民間の サービスにアクセスして生き生きと暮らす展望を見えるようにしてきたというのが実際の姿なんですね。で、これまさに今、気候危機打開、歩くまち京都の基本方針とも合致するものだというふうに考えます。そして敬老乗車証があるから、外出機会が作られ53億円の税金投入に対して507億円の経済効果が生まれているというのも、またこれも事実です。私はその意味で、敬老乗車証制度の充実など福祉の向上と成長戦略というものは軌を一にするものと確信しております。「健康長寿のまち京都推進」という理念、非常に素晴らしいものですから、その観点からぜひ各局と協力をして敬老乗車証の負担が軽くなる方向で工夫が考えられないか。今一度、保健福祉局の取り組みを求めたいと思いますが、答弁を聞いて終わりたいと思います。
☞(答弁)健康長寿のまち京都推進室・介護ケア推進担当部長:はい。地域公共交通の問題については、高齢者だけではなく、支援が必要な高齢者以外の若い方そういったいろんな方の問題かというふうに考えておりますので、地域公共交通どうするかにつきましては、先ほどご答弁も申し上げましたように、関係局と連携してどうあるべきか、というのを考えていかなければならないというふうに考えております。また経済効果のご指摘もございましたけれども、結果としてそういう経済効果があるのかもしれませんけれども、敬老乗車証制度につきましては高齢者の社会参加を支援するといったことで経済効果、それを求めた上で行っているものではございません。しっかりと見直しをさせていただきますけれども、利便性を高める見直しをこの10月から実施をしてまいります。そういったことも、今年度しっかり取り組んでまいりまして、敬老乗車証制度が将来にわたって継続していけるように引き続き取り組んでまいります。以上でございます。
◉とがし豊:あの、経済効果の話若干出ましたが、あの、私ここで紹介した趣旨というのはやっぱりね、これは高齢者に対するサービスにではありますけれども、しかし、これ自身、福祉充実させること自身が実は若い人にもプラスになっているのだと、京都で暮らしてられる方、観光に来られる方にとっても実はプラスになってるんだということが実際にあるわけなので、そういう観点からも保健福祉局として自信を持ってこの敬老乗車証の制度の負担軽くする必要があるんだという立場で頑張っていただきたいということを申しあげたかったという趣旨ですので、ぜひ受け止めていただきたいと思います。
(更新日:2023年06月09日)