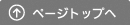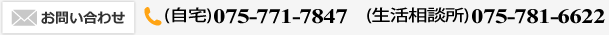とがし豊議員
■多文化共生のまちづくりについて
●2024・25年京都国際高校へのSNS上でのヘイトスピーチに対し、京都市は京都府と協力して削除要請をされた。このような差別事件は根絶させなければならない。
●ところが、参議院選挙を前後して、短期滞在の外国人が国保を乱用している、外国人が優遇されているなど、事実に基づかないデマにより外国人への差別や偏見を煽るヘイトスピーチが蔓延した。厚生労働省の2023年の調査では、国民健康保険被保険者のうち、外国人の占める割合は全体の4%。外国人総医療費は全体の1・39%、高額療養費は1・21%であり、厚労省も「外国人被保険者に対する国内の診療実績の数値は、必ずしも被保険者に占める外国人の割合に比して大きいとは言えない」と述べている。そもそも、国連人権規約社会権規約第12条では「締約国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める」としており、各国は互いにこの責務を果たしており日本も例外ではない。島根県の丸山知事は「日本人が外国で生活するときに不合理な扱いを受けないためにも、日本という国は外国の方々をできるだけ内国民、国民として扱う」と述べ、「近視眼的に、外国人を排除していけばこの社会がよくなるっていうふうに受け取られかねない言説、主張がなされている」と警鐘を鳴らされた。同時に、現に、このような排外主義の風潮が多くの人の心を傷つけていることは見過ごすことができない。日本人ファーストという言葉も同様だ。この言葉は、国内外の多様なルーツある人々が同じく協力しあい京都のまちを形づくり支えているにもかかわらず、その多様なルーツのある人々を排除する言葉の暴力でもある。それにどれだけたくさん人々が傷つけられたか、我々はその痛みをわがこととして受け止めければならない。
●市長は、先の本会議で「互いの文化や習慣に敬意を払う」「相互の尊重のもと誰もが安全安心に生活できる多文化共生社会の実現」をと答弁されたが、全国知事会は青森宣言において、相互の尊重にとどまらず、「排他主義、排外主義を否定し、多文化共生社会を目指す」と立場を鮮明にした。局別質疑では「政令指定都市においてはまだその動きはない」との答弁だったが、世界文化自由都市宣言をしている京都市の市長として、このタイミングで排外主義を否定するガバメントスピーチを発すべきだ。いかがか。
【答弁→市長】
ご指摘の通りで世界文化自由都市宣言はまちの憲法であり、その精神を尊重しなければならない。たくさんの海外の旅行者が来ている。一人一人の観光客の問題ではないが、たくさんのインバウンドで、京都の文化とまちの生活が危うくなっているという考えもある。何をもって排外主義と定義するのかという問題もあるが、いろいろインバウンドを迎えトラブルがあり、生活上の課題を抱えている市民の気持ちにも配慮しなければならない。海外からの方には京都の文化を尊重していただき、われわれもそういう方を排除しないという相互関係が必要。排外主義とレッテルを貼るのではなくお互いに尊重できる関係を築きたい。
●わが党も文化の相互理解の立場だが、現局面はそれにとどまらず、人権の問題との認識が必要。人間にファーストもセカンドもない、川崎市に続いてヘイトスピーチ規制条例を制定すべきことを求めておく。
■気候危機打開、地球温暖化について
●市長からは代表質問で「地球温暖化対策は人類共通の喫緊の課題」との認識が示された。ただ重大なことに、国も京都市も温室効果ガス排出量の削減目標が2030年までに2013年度比46%以上にとどまり、目標値も具体策も実績も、国連1.5℃報告書や第六次評価報告書の水準に至っていない。日本政府が2月に国連に提出した日本のNDC(国が決定する貢献)として示された温室効果ガス削減目標でも、2013年度を基準に2035年度には60%、2040年度には73%削減にとどまる。環境・市民団体や若者たちからあまりにも不十分、目標を引き上げよという声が上がっている。わが党としても、気候危機を打開するためには、2013年よりも8%少なかった2010年度を基準年として2030年までに温室効果ガス排出を50~60%削減、2035年までに2013年度比で75%から最大80%削減を目指すべきと提案している。環境団体などの試算では、エネルギー消費全体で6割減らし、電力消費量は3割削減、再生可能エネルギーで電力の80%をまかなえば十分可能な目標である。京都市としても、世界で気温上昇を1.5℃までにとどめるという立場に立ち、政府よりも踏み込んだ削減目標を掲げ、国内における議論を引っ張るべきだ。
【答弁→市長】
目標の数値達成に最大限取り組んでいる。環境審議会において次期削減目標についてご議論いただくが、本当にあらゆる努力が必要であり、例えば産業観光局においても。そして政策メニューとして予算に示していく。もともと46%の目標についても、本当にできるのかと私自身が考えていた。精神論で行けるのか、経済が回るのか、市民生活が回るのか、責任ある立場が必要だと。しかし、この長い夏を経験し、温室効果ガスの影響を身をもって体験し、10年前、20年前の懐疑的な考えは全体として少なくなって、本当に取り組むべき課題と認識されてきている。R8年度の予算に反映させる。それを現実化するのがプロの行政官と自覚している。
●気候危機は経済基盤自体を掘り崩すもの。7年前に目標が示されてからも、世界の政治が政策を現実化できていない。容易ならざる事態。一企業や個人のレベルの問題ではない。これ以上の深刻化を防ぐうえで乗り越えなければならない水準は非常に厳しい。だからこそ、政府・自治体の姿勢が問われている。局別質疑で、省エネをとことん徹底し再エネ100%を実行する最高水準の100%ZEBを求めたことにたいし、環境政策局からは「費用対効果」で判断して「できる限りZEB水準の高いものに目指す」との答弁にとどまった。ソーラーシェアリングも相談があったら対応するという答弁にとどまった。都市計画では環境の視点が非常に弱い。これでは気候危機に対抗できない。そこで3つに絞って伺う。1点目、公共建築脱炭素仕様の更なる改定を行い、公共建築については最高水準のZEB、再エネ100%を目指すべき。2点目、ソーラーシェアリングにもついても農家まかせではなく、農業振興センターが積極的に地元農家や農協と経験をつくり、普及促進を図る。3点目、業務部門での温室効果ガス排出増加とヒートアイランド現象の深刻化の悪循環をもたらす過剰なオフィス・マンション・ホテル供給のための規制緩和は見直す、再エネを口実にした乱開発を未然に防止する土地利用規制などの都市計画施策の展開などに取り組むなど、やるべきことまだまだあると考える。いかがか。
【答弁→市長】
提案の点は一つひとつコスト面での課題がある。しかし、ソーラーシェアリングにしてもZEBにしても、新しく取り組むにはコスト面などネガティブになる面もあるが、しかし全庁挙げての取組が必要。例えば市民セクターを前に進める必要があり、省エネ家電の買い換え支援など市民の意識を変えていただく。また交通局など各部局の取り組みも必要。コスト・財政面もあるが、どう支援するか総力挙げて知恵を絞って進めていく。
●我々も協力していきたい。
■農業振興について
●本来、農地として守られるべき市街化調整区域における向島の優良な農地が、未来投資促進法を使った京都市政策変更により物流倉庫への転換がすすめられている。しかも、局別質疑を通して、単に農地が減るにとどまらず、「緑の基本計画」において「緑の軸―主要河川における生態系ネットワーク」および「緑のふち」と位置付けられる場所が喪失されること、アセスメントではレッドデータブックに載っているシギ・チドリ類はじめ貴重な生物多様性が失われることが明らかになった。
●総合企画局の質疑では「行財政改革計画の成長戦略」で重要指標とされた「産業用地創出46㌶のうち43㌶は向島農地」であること認められ、同時に「いったん終了している」との答弁だった。産業としての農業を切り捨てることで産業用地を創出するという発想自体が食料自給率38%の国において本末転倒だといわざるを得ないが、その総合企画局でさえ「指標としてはいったん終了」とのべ、農林振興室は「農地を産業用地とする方針はない」と答弁した。だったらこれ以上の農地の産業用地化はやめて、農業振興に舵を切ると言明すべきと考える。いかがか。
【答弁→市長】
京都市において農地の産業用地化の考えはない。地権者の意向や、個々の事情はあるが、市全体のバランスにおいて考えるべきもの。そのような政策目標はなく、営農の意思を尊重するし、営農が継続できない場合も相談にのっている。農業の振興を図っていくのでご理解を。
●農地の産業用地化は市の方針として議会に説明されてきたもの。ご理解をと言われても整合性が問われる。営農困難な方への相談も農地を残すためであるべき。
●先般、日本共産党として「京都市の都市農業と農地を守り活かす」政策提案をさせていただいたが、農業をもっと位置付けてもらいたい。
(更新日:2025年10月27日)
文教はぐみ委員会2025年9月24日
一般質問「不登校支援について」
とがしの責任で文字起こししました。
正確な中身についてはYOUTUBEや後日公開される議事録でご確認ください。
なお、このやりとりののち、京都市議会本会議で京都市は不登校児童生徒へのアンケート調査を表明!
当事者や保護者のこの間の教育委員会への粘り強い働きかけが市政を少しずつ動かしています。
――――――
◎とがし委員
不登校支援についてお聞きをいたしますけれども、不登校っていうのは、この10年で休増してきたわけですけれども。まず視点としてはやっぱり今不登校にある状況あるいは行きしぶりであるっていう1人1人に寄り添った子供たちや保護者・親が安心できる取り組みということで1つ1つ丁寧にやらなければいけないという面と、もう1つはやっぱこれだけ不登校が増えてきているという状況の中で、今の教育のあり方を問う子供たちのSOSの声だっていうことで、正面から受け止めていく必要があるという風に思います。その意味でね、不登校34万人という風に全国で言われていますけれども、これも、それ以外の30日未満の項目も含めますとものすごい数になりますけれども、そういう状況で数の議論っていうのはちょっと場合によってはその一人ひとりを見ないっていう風に見えてしまう可能性もあるんですけど、ただやっぱりそれだけの人が増えたという状況をやっぱり深刻に受け止めて、教育のあり方そのものをどういう風にしていくのかっていうことを関係者が総力を上げて、分析をして改善をしていくっていうことが必要だと、そういう立場から質問したいと思います。市長の議案説明の際に、新規の不登校児童生徒数が30人減少したというに報告をされまして、子供支援コーディネーターを配置した学校では全体で24人減少したという報告がありました。ただちょっと詳細お聞きをいたしておりますと、30日以上不登校の状況にある児童生徒数は、全体では、前年の2023年3151人から、2024年・令和和6年度については3308人ということで157人増加しているということであります。様々な取り組みで行って、効果、改善した部分もあるという風に思いますけれども、他の今の、そうした努力も含めてですけれども、この現状についてはいかがお考えでしょうか?
◆教育相談総合センター所長
はい。不登校、全体についての、受け止め、また特に、令和6年度の数値というか人数についての受け止めということでございます。不登校、今委員おっしゃましたように、1人1人抱えてる背景違いますので、いかにその子に寄り添っていくかということも、きめ細かな対応と非常に大事だと思っております。一方で、不登校だからということでないんですけれども、明治の最初から行ってきたこの150年の中で作られてきた学校教育のあり方が今この時代に来て、ボランタリティというか、あの不確実性、将来がなかなか見通せないこの時代において、学校教育とはどうあるべきかということは、もう不登校のことによらずですね、しっかりと我々教育委員会としても考えていかなければならない課題だという風に考えてるところでございます。その中で今ご紹介ありました、不登校の数、市長の方からご説明があったことも含めてですけども、まず、不登校の毎年度の数におきましては、継続されてる方、継続して不登校になっておられる方に、学校復帰された方の分を引きまして、そこに、新たに、新規に、その年度に不登校なれた方を加えた数で算定をしているところでございまして。市長の方から報告させていただいたのはこの令和6年度に新規に、不登校になられた数というのが、令和5年度の新規に比べて、総数として減ったという中で、特に、特に中学校の方なんですけども、この子ども支援コーディネーターという、そこに専門的にかかわれる教員のOB等の人員を配置させていたところで、一定効果が見られたということをご説明させていただいたところでございます。しかしながら、継続の方も含めてですね、数としては、3000人を超える状態で高止まりをしておりますし、子供たちの数全体が減る中でも、この数がいう状況については、いわゆる在籍率についても少し特に小学校の方では上昇している傾向もございますので、我々としては引き続き、これまでの取り組みに加えて、さらにどういったことができるのかしっかりと考えていかなければならないという風に受け止めているというところでございます。
◎とがし委員
不校の子供たちは、決して怠けていたりとか、弱さがあるだとか、親のせいだっていうことではなくて、やっぱりそれぞれ様々な事情があって、その社会、学校や社会の中で違和感抱えて、いろんな形でをつきながら、我慢に我慢重ねて、頑張って学校行ってたけれども、もう行けなくなったということで、そういう形で心が折れているといというケースも非常にありますので、学校に復帰することが全てではないという風にも思いますし、同時にこれしっかり休んで休息するってことも極めて重要なことだという風に思いますから、その点ではこう長期化している方についてもそうした子供1人1人にふさしい受け皿が必要であるという風に思いますので、その点では校内サポートルームやあるいは、地域に様々ある居場所を振スクールなどの、えっと、支援っていうのもあるいはその新たな受け皿っていうのもしっかりと教育委員会あるいは民間と協力して確保していただきたい。これは要望しておきます。の上であの子供支援コーディネーターが11学区(正しくは17学区)でしたっけ、27人配置をされていてそれぞれの中学校の周辺のいくつかの小学校にも出向いて、支援されてるという風にお伺いをいたしております。64の中学校区ありますから全体カバーできてないっていうのは非常に残念なんですけれども、そこら辺は、あの人数的にももっと充足していただきたいという風に思いますから、この点での教育委員会の認識はどうか。あとは、この子供支援コーディネーターっていうのがいう方がその子供たちにとっては、どういう存在として、認知されているのか、ちょっとその辺も含めてですねそれぞれのあの拠点となる中学校や訪問先での小学校でのどんな、取り組み子供たちと過ごされているかとか、先生方と連携されているかっていうことについて、ご説明いただけたらと思います。
◆教育相談総合センター所長
まずあの不登校の実態について少しあの先ほどの答の続きも含めて触れさせていただきたいんですけれども、一言で不登校、規定としては、年30日以上休みになられて休まれる場合を不登校と呼んでおりますけども、これも、年30日から70日未満、大体週に1日から2日という場合も要は週の半分以上学校に来れてるけれども、何日か来れないという子供さんもられば、190日以上というか、ほとんど来れない方もある。非常にこれはあの幅がある。一言、不登校という申し上げても、子供の様子も幅があることかと思いますし、そういった条件に応じて、どうそれぞれの段階で教員になり、また周りの大人の方保護者の方も含めてですけども関わっていくのかということが大切かと思いますし、今現状としては、委員おっしゃりました、無理に、学校行かなくてもいいよ。休むことも大事だよという考え方も認知が広まってきていると思いますけれども、ただ、それが長引きますとやはりなかなか次学校に足が向かないということもありますので、それぞれの状態をどう見ていくのかっていうことが非常に難しいと思いますし、それにおいてはやっぱりご家庭での考え方もあると思いますので、そうしたところなかなか学校だけで解決できる問題ではないという風に認識も立っておりますし、2度についてもしっかりと取り組んでいきたいという風に思っております。その上で、この子供支援コーディネーターですけれども、ご紹介いただきました。今17の中学校ブロックで、小中学校合わせで56に配置をしております。基本的には中学校単位ですので、中学校をメインとしながら、校区の小学校を回るということで、大体、2校ぐらいに1人ぐらいの割合で配置をして動いているというような形になっておりまして、教育関係、この子ども支援コーディネーターではなくて、特別支援が必要な子供へのサポート的なスタッフでありますとか、いろんな角度でいろんな人員の方に学校教育に入っていただきたいということで、
財政当局にも要求をしているところでございますので、今、ここだけはなかなか拡充ということには言ってないわけですけども、今回令和6年度の部分で少し、そうした効果的な、いわゆる、エビデンス的なところも見えたかなという風に思いますので、我々としては、こうした人員との充足についてもまた財政当局の方にしっかりと要望していきたいという風に思っております。長くなりますが、その上で、子供たちからの見立て、また、開始して歴が浅いですので、これもしっかりとした知見が積み重っているわけではないんですけれども、特に中学校って言いますと、教員いわゆる教科担任の教員ではない、また保護者でもない立場の第3者ということで、子供たちが色々相談がしやすかったりとか、ですね、今以外の立場で家庭訪問を言っていただく場合もあるんですけども、保護者にとってもそういう色々話がしやすいということがありますし、専属でそういった子供に関われるということで、子供へのきめ細かなケアもできるという風に、そういったところが、効果として現られてるのかなと思っておりますし、子供ともそういう安心感、周りからそういう大人がいるということの安心感に繋がっている分があるんではないかなという風に、ま、今見立てているところでございます。以上でございます。
◎とがし委員
子供に寄り添って支援していく上では、もう本当に非常に大事なのがやっぱりそういう話を聞いてくれるというね、子供、保護者もですけれども、話を聞いてくれるだけで随分保護者は救われるという部分があると思います。本当に、懐になると、日常生活も一変してしまうっていうこともありますけれども、何よりちょっとあの、自分たち自身も経験してきたことがないような状況にあるっていう中で、ま、他の子供が通っているに自分の子供が通っていないということに対する焦りとかもあります。これに対してやっぱりそれを受け止めて、聞いてくれるだけでも随分違うなという風に思いますし、同時に、この支援継続的にできるっていうのは非常に重要だと思ってまして、ま、今ちょっと、ま、会計年度任用職員っていう形で募集されているというに思いますけれども、やはりその子供にとってやっぱり馴染んだ先生が続けていただくっていうのは1番ありがたいし、保護者としても非常にやりやすい。先生が他人の先生変わるたびに1から全部説明するっていうのが、繰り返されるわけなんですけど、それ自身もかなり疲弊をするという面がありまして、その誰か、見れるっていう状況、子供支援コーディネーターなんかもできるようにできいただけたらなと思いますし、学校でもちょっと職員配置の移動とか色々事情あるにしてもいきなり先生が全部変わるようなことだけはないようにして、ちょっと誰か子供の知ってる先生が残るようなことなんかも、あの、工夫ができたらという風に思います。と、そういうことなんですけれどもその点でですね、あの、これ今ちょっと子供支援コーディネーターなんかも知見ちょっと今、あの、蓄積し始めてところですけれども、拡充に向けて財政局に働いかけていただいておる、いただいてるということでありまして、大変心強いご答弁いただいたんですけれども、今もあのお話ありましたように、不登校というも、そだれ統合も含めて本当にあの幅広い広くこう様々なケースっていうのがありますけども、ま、それぞれに応じたあの寄り添った対応っていうのが必要であろうなという風に思っておもいます。ただやっぱり同時に今あるその学校のあり方そのものも問われておりまして、ま、学校に合わせ、子供たちを学校に合わせるという発想から脱却をして、子供たちに合わせて学校が変わっていくべき時に来てるんではないかなという風に思います。現在、文部科学省で学習同領なども見直しがされてるという風にお伺いしておりますけれど、ちょっと京都市教育委員会としてもやっぱり現場の子供たちの要塞で現場の先生から聞く声なんかも参考にして子供たちが、学校に安心して変えるような学校作りということについても是非取り組んでいただきたいですけど、最後にその点だけりたいと思います。
◆教育相談総合センター所長
不投校、ま、様々な情報があるということ、ま、私ここで答弁としては、1人1人に有り添ってということで、あの、答弁させていただいていますけど、本当に現場では本当にご苦労され、ま、ご苦労されているというか、1人との様子本当に違うと思いますし、あの、今日の先生方には大変ご苦労をいているところだと思っております。なかなかあの言葉で言うのは簡単で実態はあの難しい部分があるかなと思っていますので引き続きその部分はあのしっかりと委員会としてできることは現場にあの還元ちょっとおかしいかなあのしっかりと政策を打ちながらですねあの取り組んでいきたいという風に思っております。あの、ご承いただきまして、国の方でも今、教育学習指導の改定に向けた議論が進んでおりまして、一定の取りまとめ案、方向性の案っていうのが今、つい先日、え、9月に入って、公表されております。その中でも、教育課程の柔軟化っていうことが1つのキーワードとして出ておりますし、学校の方で、子供たち1人1人の様相ですね、例えば、特別支援が必要な子供、いわゆる通常の学級に望まない子供、馴染まない子供、それぞれに応じてどういう教育家程を組んでいくのかということが、今後の学校に求められる大きな政策の1つかなと思っております。これについてもしっかりと教育委員会としてもですね、今の指導の中で示された報酬を踏まえながら先進的にというか検討を進めていきたいという風に考えてるところでございます。以上でございます。
(更新日:2025年10月04日)