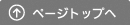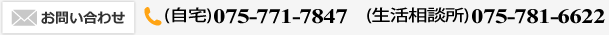とがし豊議員
■多文化共生のまちづくりについて
●2024・25年京都国際高校へのSNS上でのヘイトスピーチに対し、京都市は京都府と協力して削除要請をされた。このような差別事件は根絶させなければならない。
●ところが、参議院選挙を前後して、短期滞在の外国人が国保を乱用している、外国人が優遇されているなど、事実に基づかないデマにより外国人への差別や偏見を煽るヘイトスピーチが蔓延した。厚生労働省の2023年の調査では、国民健康保険被保険者のうち、外国人の占める割合は全体の4%。外国人総医療費は全体の1・39%、高額療養費は1・21%であり、厚労省も「外国人被保険者に対する国内の診療実績の数値は、必ずしも被保険者に占める外国人の割合に比して大きいとは言えない」と述べている。そもそも、国連人権規約社会権規約第12条では「締約国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める」としており、各国は互いにこの責務を果たしており日本も例外ではない。島根県の丸山知事は「日本人が外国で生活するときに不合理な扱いを受けないためにも、日本という国は外国の方々をできるだけ内国民、国民として扱う」と述べ、「近視眼的に、外国人を排除していけばこの社会がよくなるっていうふうに受け取られかねない言説、主張がなされている」と警鐘を鳴らされた。同時に、現に、このような排外主義の風潮が多くの人の心を傷つけていることは見過ごすことができない。日本人ファーストという言葉も同様だ。この言葉は、国内外の多様なルーツある人々が同じく協力しあい京都のまちを形づくり支えているにもかかわらず、その多様なルーツのある人々を排除する言葉の暴力でもある。それにどれだけたくさん人々が傷つけられたか、我々はその痛みをわがこととして受け止めければならない。
●市長は、先の本会議で「互いの文化や習慣に敬意を払う」「相互の尊重のもと誰もが安全安心に生活できる多文化共生社会の実現」をと答弁されたが、全国知事会は青森宣言において、相互の尊重にとどまらず、「排他主義、排外主義を否定し、多文化共生社会を目指す」と立場を鮮明にした。局別質疑では「政令指定都市においてはまだその動きはない」との答弁だったが、世界文化自由都市宣言をしている京都市の市長として、このタイミングで排外主義を否定するガバメントスピーチを発すべきだ。いかがか。
【答弁→市長】
ご指摘の通りで世界文化自由都市宣言はまちの憲法であり、その精神を尊重しなければならない。たくさんの海外の旅行者が来ている。一人一人の観光客の問題ではないが、たくさんのインバウンドで、京都の文化とまちの生活が危うくなっているという考えもある。何をもって排外主義と定義するのかという問題もあるが、いろいろインバウンドを迎えトラブルがあり、生活上の課題を抱えている市民の気持ちにも配慮しなければならない。海外からの方には京都の文化を尊重していただき、われわれもそういう方を排除しないという相互関係が必要。排外主義とレッテルを貼るのではなくお互いに尊重できる関係を築きたい。
●わが党も文化の相互理解の立場だが、現局面はそれにとどまらず、人権の問題との認識が必要。人間にファーストもセカンドもない、川崎市に続いてヘイトスピーチ規制条例を制定すべきことを求めておく。
■気候危機打開、地球温暖化について
●市長からは代表質問で「地球温暖化対策は人類共通の喫緊の課題」との認識が示された。ただ重大なことに、国も京都市も温室効果ガス排出量の削減目標が2030年までに2013年度比46%以上にとどまり、目標値も具体策も実績も、国連1.5℃報告書や第六次評価報告書の水準に至っていない。日本政府が2月に国連に提出した日本のNDC(国が決定する貢献)として示された温室効果ガス削減目標でも、2013年度を基準に2035年度には60%、2040年度には73%削減にとどまる。環境・市民団体や若者たちからあまりにも不十分、目標を引き上げよという声が上がっている。わが党としても、気候危機を打開するためには、2013年よりも8%少なかった2010年度を基準年として2030年までに温室効果ガス排出を50~60%削減、2035年までに2013年度比で75%から最大80%削減を目指すべきと提案している。環境団体などの試算では、エネルギー消費全体で6割減らし、電力消費量は3割削減、再生可能エネルギーで電力の80%をまかなえば十分可能な目標である。京都市としても、世界で気温上昇を1.5℃までにとどめるという立場に立ち、政府よりも踏み込んだ削減目標を掲げ、国内における議論を引っ張るべきだ。
【答弁→市長】
目標の数値達成に最大限取り組んでいる。環境審議会において次期削減目標についてご議論いただくが、本当にあらゆる努力が必要であり、例えば産業観光局においても。そして政策メニューとして予算に示していく。もともと46%の目標についても、本当にできるのかと私自身が考えていた。精神論で行けるのか、経済が回るのか、市民生活が回るのか、責任ある立場が必要だと。しかし、この長い夏を経験し、温室効果ガスの影響を身をもって体験し、10年前、20年前の懐疑的な考えは全体として少なくなって、本当に取り組むべき課題と認識されてきている。R8年度の予算に反映させる。それを現実化するのがプロの行政官と自覚している。
●気候危機は経済基盤自体を掘り崩すもの。7年前に目標が示されてからも、世界の政治が政策を現実化できていない。容易ならざる事態。一企業や個人のレベルの問題ではない。これ以上の深刻化を防ぐうえで乗り越えなければならない水準は非常に厳しい。だからこそ、政府・自治体の姿勢が問われている。局別質疑で、省エネをとことん徹底し再エネ100%を実行する最高水準の100%ZEBを求めたことにたいし、環境政策局からは「費用対効果」で判断して「できる限りZEB水準の高いものに目指す」との答弁にとどまった。ソーラーシェアリングも相談があったら対応するという答弁にとどまった。都市計画では環境の視点が非常に弱い。これでは気候危機に対抗できない。そこで3つに絞って伺う。1点目、公共建築脱炭素仕様の更なる改定を行い、公共建築については最高水準のZEB、再エネ100%を目指すべき。2点目、ソーラーシェアリングにもついても農家まかせではなく、農業振興センターが積極的に地元農家や農協と経験をつくり、普及促進を図る。3点目、業務部門での温室効果ガス排出増加とヒートアイランド現象の深刻化の悪循環をもたらす過剰なオフィス・マンション・ホテル供給のための規制緩和は見直す、再エネを口実にした乱開発を未然に防止する土地利用規制などの都市計画施策の展開などに取り組むなど、やるべきことまだまだあると考える。いかがか。
【答弁→市長】
提案の点は一つひとつコスト面での課題がある。しかし、ソーラーシェアリングにしてもZEBにしても、新しく取り組むにはコスト面などネガティブになる面もあるが、しかし全庁挙げての取組が必要。例えば市民セクターを前に進める必要があり、省エネ家電の買い換え支援など市民の意識を変えていただく。また交通局など各部局の取り組みも必要。コスト・財政面もあるが、どう支援するか総力挙げて知恵を絞って進めていく。
●我々も協力していきたい。
■農業振興について
●本来、農地として守られるべき市街化調整区域における向島の優良な農地が、未来投資促進法を使った京都市政策変更により物流倉庫への転換がすすめられている。しかも、局別質疑を通して、単に農地が減るにとどまらず、「緑の基本計画」において「緑の軸―主要河川における生態系ネットワーク」および「緑のふち」と位置付けられる場所が喪失されること、アセスメントではレッドデータブックに載っているシギ・チドリ類はじめ貴重な生物多様性が失われることが明らかになった。
●総合企画局の質疑では「行財政改革計画の成長戦略」で重要指標とされた「産業用地創出46㌶のうち43㌶は向島農地」であること認められ、同時に「いったん終了している」との答弁だった。産業としての農業を切り捨てることで産業用地を創出するという発想自体が食料自給率38%の国において本末転倒だといわざるを得ないが、その総合企画局でさえ「指標としてはいったん終了」とのべ、農林振興室は「農地を産業用地とする方針はない」と答弁した。だったらこれ以上の農地の産業用地化はやめて、農業振興に舵を切ると言明すべきと考える。いかがか。
【答弁→市長】
京都市において農地の産業用地化の考えはない。地権者の意向や、個々の事情はあるが、市全体のバランスにおいて考えるべきもの。そのような政策目標はなく、営農の意思を尊重するし、営農が継続できない場合も相談にのっている。農業の振興を図っていくのでご理解を。
●農地の産業用地化は市の方針として議会に説明されてきたもの。ご理解をと言われても整合性が問われる。営農困難な方への相談も農地を残すためであるべき。
●先般、日本共産党として「京都市の都市農業と農地を守り活かす」政策提案をさせていただいたが、農業をもっと位置付けてもらいたい。
(更新日:2025年10月27日)