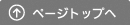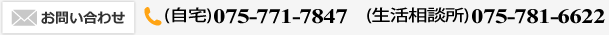新洞小学校の跡地活用については、民間活用ではなく公的な活用を求める立場で、一貫して求めてきました。とはいえ、西松建設が「候補事業者」に選定され地元との協議を開始した以上は少なくとも十分な合意形成が図られるべきであると考えます。ところが、漏れ聞こえてくる京都市の硬直的な姿勢は、当初の地元の要望書や募集要項の見地から考えたとき、あまりにも硬直的であり、改める必要があると思い、加藤議員とも相談し以下の質疑にいたっております。京都市担当者の皆さんにも、事業者の皆さんにも、しっかりと受け止めていただきたいと思います。
20250924総務消防委員会摘録(新洞小学校跡地について)公表用
ーーーーー
総務消防委員会2025年9月24日
【行財政局 一般質問】
※このメモは、日本共産党京都市会議員団事務局による摘録です。正式なものとしては、市議会ホームページで公開される議事録か、youtube動画をご確認ください。
【質疑者:日本共産党・加藤あい議員】
◆新洞小学校の跡地活用について
〇わが党としては、学校跡地は、民間活用ではなく、公的な活用を求める立場に変わりないことを述べておく。
新洞小学校の跡地活用について、公募プロポーザルによって2社が競い、1社が事業候補者として3月に選定され、事前協議が続いている。8月の説明会や周辺町内会への説明会でも様々なご意見が地元から寄せられたとお聞きしている。留学生寮190室、有料老人ホーム90室で、ボリュームがあまりにも大きく4階建てを3階建てに変更してほしい。また、消防団がホース延長の訓練をしようにも、最長で44mしかとれず、20mホースを3本連結しポンプを配置した訓練が困難というもの。
従来グラウンドで実施してきた夜間の消防訓練や、あるいは、区民運動会についても十分な実施スペースが確保できない。これでは、募集要項p18「屋外スペース(オープンスペース)」で記載のある「運動会等の地域イベント」「これまでの地域イベントが継続出来るように十分に配慮した提案」になりきっていないのではないか。また、周囲の住宅・マンション・寺社と比してもあまりにも圧迫感が強い巨大な建物であり、検討委員会が当初要望書で求めてきた「落ち着いた街並みと調和した施設」にもなっていないのではないか。
(→学校跡地活用促進部長)地元の跡地活用検討委員会での議論を経て提出された地元要望を反映した形で募集要項を作成し、事業者からの提案募集を行った。今年2月、最も地元要望をかなえられるような最良の事業者を選定し、京都市、連合会の3者による事前協議会を設置し、住民説明などでいただいた様々なご意見、ご要望を踏まえて、事業化に向けた合意形成の協議を行っている。
〇現段階の計画について「ボリュームが大きすぎて、地元活動が保障できない」「周辺の街並みと調和した施設になっていない」という指摘に対して、そのような認識をもっているのか。
(→学校跡地活用促進部長)地域活動の継承、確保は、学校跡地活用の基本的な考え方。事業者からの具体的な提案を受けて、地元のみなさんからいただいた個々の意見については、真摯に耳を傾けながら、要望をかなえられること、かなえらええないことについて、協議を重ねていきたい。
〇要望をかなえることは大前提、絶対にあいまいにしてはならない。
公募プロポーザルという方式では、応募した企業提案の範囲でしか、地元には選択権がみとめられない。その枠内で変更は認められないという前提で事前協議が押し付けるから余計に地元の合意が困難になるのではないか。今年3月に候補事業者に選定された西松建設との「基本協定」では「第4条2(1)本件跡地の活用に係る具体的な活用計画、(2)自治活動の継続、避難所機能の確保その他本件跡地の活用にかかる施設の整備、運営などに関する具体的な内容」を協議事項としている。さらに、「第4条の4、京都市および自治連が疑義または意見を述べた時には、これに対し誠実に説明し、活用計画の見直し、解決策の提示その他の必要な措置」についても協議事項とされている。たとえば、60㍍も擁壁のような建物が続き圧迫感が酷く、せめて4階建ての計画を3階に引き下げてほしい、運動会や消防団の訓練が従来通りできるようにグラウンド面積を現計画よりも拡大してほしいなどの要望についても、協議事項として取り上げることはできるのではないか。
(→学校跡地活用促進部長)地元住民から様々な意見、要望をいただいているが、事業の採算性、継続性の観点から、事業規模に関することなど、要望通りにかなえれないこともあるが、着地点をさぐりながら事業者とも協議を進めていきたい。
〇協議事項として取り上げることはできるのか。
(→学校跡地活用促進部長)協議事項として議論していきたい。
〇事業者と地元住民の利害が対立したときに、事業者の側が優先されるというスキームになっている。これでは、地元の思いを尊重することにはならない。
元植柳(しょくりゅう)小学校跡地活用事業をめぐっては、京都市・安田不動産・植柳自治連合会の三者での事前協議では、公園地下への体育館計画を見直し、敷地のホテル面積12%を削った上でその部分を学校敷地内の屋内運動場と変更した。どのような事前協議の経過だったかというと、2019年3月の基本協定ののち7月から協議が開始され、30人弱の委員以外にも住民の傍聴は認められたものの発言がみとめられておらず、地域住民の意見を反映していないとして、スケジュールが変更され、翌2020年2月4日に第11回事前協議会の後、2月22日に住民意見を聞くための事前協議会が開催され、さらに第12回事前協議会で取りまとめがされるはずだった。京都市が新型コロナ感染予防のため中止としたためとりまとめがされないまま、3月に自治連合会の総会が開催される、とういう経過をたどった。植柳小学校の場合でも十分ではないと住民から声があがっていたが、こうした経過と比較しても、京都市がこの間の新洞小学校めぐる説明会でとってきた姿勢はあまりにも硬直的。住民意見を協議の俎上にあげるべきだ。
(→学校跡地活用促進部長)事前協議会で、7月に全体住民説明会、8月には町内ごとの意見交換会を5回開催するなど、幅広く住民のみなさんの意見を聞く機会を設けている。引き続き、自治連合会とも連携しながら取り組んでいきたい。
〇十分やっているかのような答弁だが、地元のみなさんの受け止めとは乖離がある。基本協定締結前のみならず、基本協定で「事前協議会は公開しないものとする」としているため、検討委員の方と所属団体構成員や地域住民との意思疎通が図れず、その結果、地域の合意づくりにも支障をきたしてしまうのではないか。地域での人間関係がぎくしゃくしかねないとの強い懸念もお聞きしている。この点、とがし議員も大変懸念をしている。新洞学区の素晴らしいコミュニティを大事にするためにも、植柳小学校での計画変更の経験も生かして、京都市としても対応を改めるべきではないか。
(→学校跡地活用促進部長)2月に契約事業候補者が決まった後、全体住民説明会、意見交換会など丁寧に対応してきた。それで終わりということではなく、出された要望などには、できる範囲の丁寧な対応はしている。
〇丁寧な対応という認識と地元のみなさんとの認識にはズレがある。
もともと新洞小学校跡地検討委員会が2022年9月に提出した「京都市への要望書」では、元新洞小学校の本館、講堂、グラウンド等においてこれまで行ってきた自治活動などが、引き続き実施できるようにし、本館や前庭の保存・再生を求められていた。街並みへの調和についても、単に既存の高さ規制さえ守ればよいという要望ではなく、落ち着いた街並みとの調和を求められていた。その点を京都市として決しておろそかにしないでいただきたい。
(更新日:2025年09月25日)