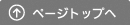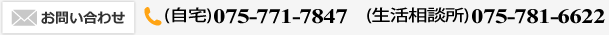活動日誌・お知らせ
バス路線維持に向けた新たな支援について~2024年6月5日予算特別委員会(都市計画局)への質疑
予算特別委員会 第2分科会 都市計画局 6月5日
とがし豊議員
バス路線維持に向けた新たな支援について
ーーーー
○今回バス路線の維持に向けた支援として、市バス8路線、民間バス19路線を支援するとして路線の赤字の5割、民間バスは赤字の8割を市が補助金で補填、穴埋めをすることで路線を維持していくというが、この対象になる基準と一定の市民利用がある生活路線という基準というのはどういうことか。あと、5割8割という補助率で本当に維持可能なのか。
(答弁→事業推進担当部長)補助対象路線の考え方は、当該路線が廃止されることによって鉄道駅やバス停の範囲、鉄道では半径800m、バス停エリアでは300mの範囲から外れる地域が発生すること、その路線の収支が赤字であること、一定の市民利用がある路線だ。一定の市民利用がある路線というのは、市内の完結路線及び市内外にまたがる路線のうち市内部分であること。それから1日3回以上の運行があること。または、国のガイドラインに示す交通空白地域に該当し、2回以上の運行があること。日祝のみの運行、季節運行路線ではないことで対象を絞っていく。補助率は、市バス2分の1だが、民間にはインセンティブ持たせることで、5分の4で非常に高い補助率にしている。今非常に困っているのは、運転手がいない深刻な状況。周辺部路線を守っていけるよう、しっかり事業の趣旨を説明していきたい。
○運転手さんの確保と処遇改善とセットだが、我が党としても公共交通を支援する考え方は本当に大事だと求めてきた。鉄道駅800m、バス停300m、あるいは交通空白地域については、2回以上だが、1往復しかない厳しい所、先ほど縮小してしまった所をなんとか復活できないかという話は、私も本当に要望しておきたい。交通不便地域として、先ほど路線がなくなってはいけないということで、1つ考え方を示されたが、鉄道800m、バス停300m以外は交通空白地という概念を交通不便地域と捉え、そもそも路線のない所も含めて、しっかりと課題解決に取り組むことを求めておきたい。
○この間、敬老乗車証制度の改悪によって、民間バス、市バスへの支援が大幅に縮小するが、経営上の打撃はかなり大きく、敬老乗車証の負担金の軽減や対象年齢を70歳に戻すなどして利用の促進をして、その分を支援するという合理的な公共交通の支援のやり方がある。京都市の公共交通の計画においては、使って守るということを掲げているので、福祉政策も含めて総合的に民間バス、市バスの効果的な支援のさらなる検討を求めたいがいかがか。
(答弁→事業推進担当部長)敬老乗車証制度の話は、保健福祉局だ。我々は今厳しい事業所をしっかり支援して必要なバス路線を守れるように交通政策の観点で今回制度を創設する。敬老乗車証の話でいくと、この間見直しの中で年間証の拡大などに関しては我々も意見交換している。
(答弁→都市計画部長)交通制度は、市民生活を守っていく観点で非常に大切だ。我々は交通ネットワークをいかに維持していくのかは最大の観点だ。その上で持続可能性、どれだけの経費がかけられるのかを考えながら制度をブラッシュアップしていくべき。他の委員からも交通ネットワークは非常にクリティカルなものだと。東京BRTが駅から10分以内で行けますと紹介されていたが、例えば、洛西地域で鉄道駅から境谷大橋から10分以下で届く。その交通利便性をしっかりお示し、それに対してしっかり経費をかけ、しっかり利用していただく。それに対して我々としては持続可能な制度を作っていくのが1つ大事なことだ。
(更新日:2024年06月07日)

子育て世代の定住対策は、過去の大型開発の総括の上で計画を~2024年6月5日予算特別委員会(都市計画局)への質疑
予算特別委員会 第2分科会 都市計画局 6月5日
とがし豊議員
子育て世代の定住対策は、過去の大型開発の総括の上で計画を
ーーー
○2023年4月の外環状線沿道での高さ規制などの緩和を行う都市計画変更に続き、今回の「meetus山科-醍醐の推進に向けた機運醸成」予算が第二次編成で計上をされた。時を同じくして三条駅周辺の「都市再生緊急整備地域」指定の動きが表面化した。30年前、地下鉄東西線整備と一体に進められた五大プロジェクトが実施された三条駅、山科駅、醍醐駅の周辺をさらに大きな仕掛け、大きな範囲で再開発しようというものではないか。5月23日のまちづくり委員会の都市計画局長の答弁で、過去の経過を踏まえながら必要な事業・施策を展開したいという抱負が述べられた。過去の経過を振り返ると言うなら、五大プロジェクトをどう総括しているのかと正したところ、「総括は建設局の所管」だと述べられ、駅前広場の整備としてはきちんとやっているぐらいの浅い話で終わった。都市計画局としては、もっと総合的な観点から過去の経過と総括、現状分析をやるべきだがどうか。
(答弁→まち再生・創造推進室長)山科駅前地区第一種市街地再開発事業については20年以上前の事業だが、道路や駅前広場などの公共施設が未整備で、土地利用が細分化された低層の木造住宅が数多く存在したため、公共施設、住環境及び商場環境の一体的な整備を行い都市機能の向上と土地の効率的かつ健全な高度利用を図ることを目的として実施された。この結果、施行前の狭小な道路や広場、歩車道の分離、電線共同溝整備、ラクトの4棟の施設建築物の建設、公園の整備、地下道に接続する駐輪場の整備、案内板やサイン灯が配置され、分かりやすいまちづくりが進められた。人々に憩いと潤いを与える空間が提供された。これにより、山科駅周辺を始めとする地域のにぎわい活性化に寄与貢献したと捉えている。
○こういったことを提案する場合は、事前に誠実に予め説明される必要があるのではないか。五大プロジェクトについてはその後のまちづくりにどう影響を与えたのかをしっかりと総括していくことが大事な前提だ。どこの事業にしてもそんな簡単に話が進んだわけではなくて、破綻したもの、計画変更、規模縮小、紆余曲折も含めてしっかり総括がいる。それがあって初めて失敗を繰り返されないということになる。まちづくり委員会でも、京阪京津線が地上にあった時代の賑わいに時計の針を戻すという話もあったが、現実を見ない話で、願望が先走っているのでないかと危惧する。meetus山科-醍醐のプロジェクトについては、しっかり過去の経過の上に住民の皆さんの声をしっかり聞いて計画を進める必要があるのではないか。
○そこでmeetus山科-醍醐の推進本部の資料を見ると、当該エリアにはすでに大規模商業施設、マーケット、飲食店、病院などが多く存在をし、豊かな自然、公園などがまちの魅力として押し出されている。その魅力と比較して、外環状線の高さ規制を緩和し高層マンションを建てまくる構想には大変違和感がある。子育て世代からタワーマンションに住みたいとの要望が果たして本当にあるのか。むしろ、高層マンションではなくて空き家とか中古住宅に転入とリフォームを誘導する方がニーズに合うのではないか。この高さ規制緩和で無理にこの高層マンションを推進すると、地価高騰で逆にマイホームの夢が遠のくことになってしまう。京都市中心部はなかなか手が出ないが、山科だったら今回のいろんな補助を受けて住めるかなと思った人の手が届かなくなってしまうのではないか。このリスクについて、お考えを聞きしたい。
(答弁→まち再生・創造推進室長)都市計画の見直しは、外環状線沿道の賑わいと潤いある都市空間を作る目的で様々な配慮とセットで行ったもの。こういったことを実現するため、meetus山科-醍醐プロジェクトの中でしっかりと取り組んでいく必要がある。これを通じ、住みたい移住したい方の受け皿となる住まい環境向上が、山科・醍醐の魅力ポテンシャルを高めることになる。
○それが地価高騰を招いて、せっかくまだ住める住宅があるのに生かされないことになったら本末転倒になるのではないかと危惧しているので、その点受け止めていただきたい。
○東部クリーンセンターの跡地について、地元の方からは、学校の跡地を民間資本の開発に差し出すのではなくて、京都市の施設として活用してほしいと。とくに、子どもみらい館のように子どもたちが使える施設が欲しいだとか、公園を作って欲しいという要望などもたくさんある。住民の要望をしっかり受け止めてまちづくりをしてこそ、空き家に入って生活していこうかということで人口が増えるのではないか。是非そうした視点を持つよう要望しておく。
(更新日:2024年06月07日)

都市再生緊急整備地域の拡大(三条駅周辺)について~2024年5月23日京都市会まちづくり委員会
2024年5月23日まちづくり委員会(文字お越し冨樫)
とがし委員:どうぞとよろしくお願いいたします。都市再生緊急整備地域の拡大について、とりわけ、私からは三条駅周辺エリアについてお聞きしたいと思います。平井議員は京都駅南エリアで私は三条駅周辺エリアを、昨日調査をしてまいりました。それで現地で様々、全ての方会えたわけでありませんけども、ちょっと話をお聞きできる方には聞いたりしてまいりました。それを受けて質疑したいと思います。まずです。5月20日から6月2日までパブリックコメントということでありますけど3月に既に国に対して拡大申請しておきながら議会への報告が今になったのはなぜか、ということです。とりわけ今回、全く新規に提案されているこの三条駅周辺地域については住民の方に何の説明もなく突如として大規模規制緩和措置を可能とするような都市再生緊急整備地域への指定を申請されたということであります。これ、おかしいんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
担当部長:そもそもなぜ今報告かというところでございますけども、3月に申し出を行っておりますけども、この間、国とも協議をずっと続けてきたということでございまして、今回のあくまで国が主体でございますので、国との協議が今回整ってパブリックコメントを始めたというタイミングでご報告をさせていただいたというところでございます。先ほど地元への説明をということでありましたけども、繰り返しになりますが、今回の指定は国が行うものということであります。これも繰り返しになりますけども、今回の指定によりまして、新たな規制の強化や緩和を行うものというものではございませんので、本市としては改めて、今回の指定のためだけに、説明会であるとかパブリックコメント等の意見聴取というのは行ってはございません。地元の学区の会長などにはご説明をさせていただきまして、期待の声をいただいているというところでございます。
とがし委員:冒頭の平井委員とのやり取りで、結局そんな具体的なものを示しているわけではなくて一般的に期待を聞いたという話だったということだという風に答弁、やり取りを聞いて認識しているわけなんですけども。果たしてです。学区の自治会の会長さんだけに聞いて、それでもって地域の意見を聞いたということで済ましていいのかということも、そもそもの問題だと思います。おそらく、学校の自治連の会長さんのとこにはそんな十分な情報もいってへんと思いますけれども、その下で、なおかつ、そこにしか声がかからないという下で進んでいると。しかも、新規で京都市が提案をして、それを受けて、国が検討するという枠組でありますから、そう考えた時にはやはりきっちりと手続きの考え方としても住民の皆さんにまずお示しするっていうのが、当たり前のことではないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
担当部長:繰り返して恐縮なですけども、今回の申請によりまして、特に規制の強化であるとか緩和というものが行われるものではございませんので、本市としては、改めて説明会であるとかパブリックコメント等の意見聴取は行ってございません。今回の指定にあたりましては、都市計画マスタープラン、これは住民の意見を聞いて策定されたものでございますけども、こういった方針に基づいて行うというものでございまして、住民の意向を反映したものであるという風に考えてございます。仮に、今後規制の強化であるとか緩和を行う都市計画の見直しを行うにあたりましては都市計画手続きの中で住民の方々の意見を聞くという機会がございますので、そういった中で、住民の意見を反映していくということを考えてと思います。
とがし委員:都市計画マスタープランを策定された段階っていうのは、こういう規制緩和を可能とする前提ではない中で、都市計画マスタープランっていうのは策定れていると認識しています。ですから当然、住民の皆さんは、ここにかかってる景観とか用途制限とかそういう規制ですね、新景観政策に基づく規制というのがかかってる前提で都市計画マスター プランを議論されたという風に思うんですけど、その点はいかがですか。
担当部長:規制の見直しをこれから仮にする場合には、当然、都市計画マスタープランについてはそこまで細かいことてのは書いてありませんけども、そのビジョンの方向性に沿って都市計画というものは定められるものでございまして、仮に規制を見直しをするというような場合には、また別途住民参加の手続きを経て、都市計画審議会の議を経るなど、厳格の手続きを経た上で見直しをする、ということでございますので、当然その手続きの中で住民の意見を反映していくということが可能であるという風に考えてざいます。
とがし委員:それで言いますと、現段階では規制緩和をするわけではないと言われますけど、そもそも、その説明のところでは規制緩和の措置っていうのが1番に掲げられてますね。で、この中では、以前の容積率を緩和していくんだと。これ代表例として言われてますけど も、用途制限等ですから、高さ制限とかもちろん対象になると思うんですけど。三条エリアについては高さ制限の見直しとか用途制限の緩和はやらないという前提なのか、いかがですか。
担当部長:地域の指定、決して規制緩和ありありきではございませんので、あくまで今回は指定をしたとのみというところでございます。現時点で何か都市計画の規制の緩和をするという予定があるわけではございませんけども、仮に今後、民間事業者からの提案が個々なされた場合には、ご紹介したのは都市計画の手続きを経て必要な判断をしてまいりたいという風に考えてございます。
とがし委員:そうしますとすね。制度の枠組上はこの指定を受ける地域が拡大されることによって規制緩和が非常にしやすくなるということははっきりしていると思うんですね。そういう点で私やっぱりそういうことを住民にまともに図らずに勝手に進めていくというのはあってはならないことだという風に思います。これは私は京都市がその本当に住民参加のまちづくりを思ってるのであれば、こんなことはありえないというに思いますので、私は間違いであったという風に指摘しておきたいと思います。三条駅の中身に入るんですけど、この三条駅周辺地域ということで現地をぐるっと回ってまいりました。そうしますとまあの西側は鴨川に面して三条京阪の関連施設がありまして、通り沿いにはまマンションホテルお店などが立ち並んで、南側には有済小学校があって、真ん中ありから東側にかけては、三条市営住宅が広がるということでありました。先ほど富委員からもありましたように、三条駅エリアに関しては、特にこの京阪グループが所有する部分に関しては、2001年に地下鉄東西線に関する5大プロジェクトの一環として、バスターミナルも含めまして大規模な開発が行われまして、その2年後には京阪の商業施設がオープンをいたしております。その際、開発に関して京都市としても、かなりお金を使ってると思うんですけども、事業費とはどれくらい投入をして、まちづくりとして、その時のまちづくりとしては、それをどう総括されてるんでしょうか。
担当部長:予算については手元に資料がございませんのでお答えしかねます。
とがし委員:予算については資料が手元にないからわからないということですが、HP上で見たら駅前広場整備費21億円と書かれているんですけど、何をもって21億円かはわからないけどもそういうのがありましたけども。まちづくりとしてはこの取り組みをどう総括されていますか。
担当部長:少なくとも現状で未利用地となっているところ、この地域について新たな都市機能の集積をして賑わいを増やしていくことが必要だと考えてございます。
とがし委員:先ほどからうまくいっていないという話が出ているんですけども、過去の開発が失敗したのであればそれをきちんと総括をして問題点明らかにして、じゃあどうするかっていうことで考えて、新しい方針考えなければいけないんですけど。今で言うと過去21億円か、少なくとも駅前広場整備で21億円 使ってるけれども、京阪も当然開発してはりますから、お金使ってはりますよね。しかし、それはなぜうまくいかなかったのか、と。で、それはなぜうまくいかなかったか、と。そういう総括をされて、今回の提案が出てきたのかという風に聞きたかったんですけど、今の話で言うと、そういう総括はせずに、とにかく現状を見たら駐車場になってて利用されてないということで、今回の提案に至ったという理解でよろしいですか。
土木担当部長:委員ご指摘の三条京阪の整備については、交通結節点の整備として建設局の方で行って、バスターミナルとかそういったことを整備しておりまして、今もその機能は存続して市民の皆さんが使っていますので、決して失敗とかではなしに、要は公共インフラの整備という形で整備したものでざいます。ですので、特に今も有効に活用されていますので、決して失敗ではないと考えております。詳細は建設局の事業でございます。
とがし委員:ということは失敗でないという認識であるということでありますと、そしたら、完了してるということなので、後は京阪グループの責任である、問題であるということなんですか。
土木担当部長:誰の責任とかそういったものじゃなしに、京都市が投じた21億円、それについてはインフラ整備として有効に活用になっている。その当時、連携しながら整備されたと推測されますけども、今の段階で誰の責任とかそういったものではなしに、建設局としては税金を使った目的として公共イフラの整備については適切に整備できたという認識でございます。
とがし委員:今その真ん中の土地は駐車場になっているんですけど、元々、商業施設が入った時はバスターミナルの中心に京阪の商業施設があるということで、結構苦戦をされていたんですけれども、事業としてはもう終わってしまって、結局、5大プロジェクトと名打ったけど 三条については一応バスターミナルとしては機能して確かに私思いますけど、ちゃんと機能してるしタクシー乗り場もちゃんとしてるし、機能はしてると思うんですけど、しかし駅前開発としては今の現状に至っている、と。その辺をどこまで総括してるのかっていう認識を聞きたかったんですけど。とりあえず、京都市が担当した分についてはまうまくいってるんだという程度の総括をされた上で、今回、新たに都市再生緊急整備地域の指定拡大をして、規制緩和を可能にしていこうという話に進んでるんかなという風に思うんですね。この京阪グループさんが昨年、新聞記事にも出ていましたけど、昨年の中期経営計画の中で「三条駅前に東山観光の拠点となる日本や京都の文化を発信する複合施設の整備を推進しターミナル機能を強化する」ていう計画を打ち出されました。ということで言いますと、京阪グループ自身としてコロナ後の取り組みとして、こういう新しい機軸を打ち出されて取り組んでいくんだともうすでに言われておって、もちろん当然その採算とか見込みながら提案されてるという風に思うんですけども。そういう状況で言えば、新たな規制緩和っていうのは別に必要ないんではないかという風に思うんですけど。その点はいかがでしょうか。
担当部長:繰り返しになって恐縮なんですけども、今回の制度は規制緩和ありきではございませんので必要に応じて民間事業者から提案があった場合には必要な手続きの中で判断をしていくということでございます。仮に税制優遇などを行う場合にあたっては、公共施設の整備であるとかそういった質の高いものに限って支援をするというものでございますので、そういった提案が仮に京阪からあれば、そういった提案を踏まえて検討してまいりたいという風に考えてござます。
とがし委員:新聞記事によりますと 2010年頃には京阪のCOE最高経営責任者の方が当時のコメントとして高さや容積率の制限により事業計画を立てられないと指摘して着工の遅れを明らかにしたという風におっしゃってるということが新聞記事として書かれているわけでありますけども。ただ私は言いたいのは、2023年の段階で今日出された段階では別にそういうことをおっしゃって提案されたわけではなくて、色々当然社内の中でおそらく検討されて責任を持って提案されてると思いますので、私はその意味では現段階で新たな特別の指定をする必要なくなく、別に街づくりとして進んでいくんではないかという風に思っております。ですから、今の話で言うと、別に京阪さんから何か要望が既にあるとあったというわけではないという理解でよろしいですか。
担当部長:何か規制緩和等々で決まってることは一切ございません。
とがし委員:決まってることないのは分かっているんです。京阪から申し出、要望があったのかどうかっていう確認です。
担当部長:具体的に京阪側から何か意見提出があったとかそういうものではございません。意見があったというものでもございません。
とがし委員:京阪から要望はなかった。意思疎通とかもされてないですか。
担当部長:民間事業者とは常日頃から情報交換を、京阪さんに限らずしておりますので、協議は色々とさせていただいておりますけども、今、本件に関して特に何かをしてくれというようなことは聞いてございません。
とがし委員:それであれば別に何かこの新たなことをする必要ないんでないかという風に
思います。そもそも、ここの指定される区域の大半っていうのは京都市の土地になっていますよね。市営団地ですけど、今、新しい棟を建築中のとこを除いたエリア全体が指定されているということなるんですけども、京都市の都市計画局の中になるかもしれませんけども、市営団地を担当するセクションから京都に対して何らか規制緩和あるいは、財政税制上の優遇措置が欲しいからということで、要求があったりとかしたんでしょうか。
担当部長:この地域につきまして、そもそも、質の高いプロジェクトを推進していく必要があるという風に、少なくとも都市計画局として判断をしているということで、今回の指定を国に申し出だというところでございます。あくまでも指定をしたからと言って規制緩和されるわけではないですし、制度が活用されるわけではなくて、仮にこう質の高いプロジェクト、公共施設の整備を伴うような質の高いプロジェクトがあった場合に支援が受けやすいようにということで指定をするということでございます。
とがし委員:市営団地整備っていうのは京都市の事業ですよね。だから京都市が施主としてここでは規制緩和は求めないということをはっきりしていただけたら非常に分かりやすいんですけど、その点はいかがですか。
担当部長:三条市営住宅につきましては現在、団地再生事業をやっておりますけども、この事業の完了後には将来活用地が生まれるということからも、この地区の魅力や活力の向上目的としまして医用方針も含めて、今後検討していくということでございますけども、仮にそういったところでも質の高いプロジェクト、公共施設整備を伴うプロジェクトを行うという場合には、そういった支援が受けられるようにしたということでございます。
とがし委員:つまりそういった支援っていうのは、ここで示されている法制上、都市計画の見直しとかも含めた法制上の支援で、財政上の支援、金融支援、税制支援と、この4つの柱で支援を受けられるという枠組をこの市営団地の用地についても考えているということでですか。
担当部長:この制度で利用可能なものを仮にこの跡地について民間事業者等々が事業をやる時には受けられにするということでござます。
とがし委員:私は、京都市の土地ですから京都市がわざわざ自分から規制緩和するっていうのはあってはならないと思うんですね。市民の皆さんに対して様々家を建てるとか、店舗を建てるとかいう時には規制をかけるわけですね。新景観法に基づいて。それをみんなが守ることによって景観が守られるわけなんですけど、そういうことを考えた時に私はやはり京都市はその市営団地の敷地、そこの敷地においてそういう規制緩和をするようなこと誰が手を上げたとしてもあくまでも現行法の枠内での取り組みでやってくださいということでえこのえ法制上の支援の措置というのは除外するという姿勢を示すべきだと考えますけどいかがでしょうか。
担当部長:まず緩和、力ではありません。これから民間事業者から提案があった場合には必要に応じて検討していくということでございます。この活用方針自体がこれから検討ですのでまだそこで決まったことはございません。仮にこの規制を見直すという場合に何度も申し上げておりますように、都市計画手続き等々が必要になりますので、その中で住民のの方々意見も聞きながら判断をしていきたいという風に考えてございます。
とがし委員:ちょっと否定なさらないっていうとこが非常に残念なところなんですけど、私 やっぱりきちんとあの今のあの神権化政策を守った上でま団地再生の敷地の部分に ついては活動用地も含めてですねあの考えていただきたいということを求めておきますでまあのまその点ではですねやはりこのその面からもね団地再生計画の面から もま今回のえっと規制緩の措置はいら含むような組いらないんじゃないかという風に思ますで次にあのまそれでですねあとあの歩いておりまして大きな空地がありまして誰の土地かて住民の方に聞いたらこの広大な空地は全部京都市のもんですっ言われてでそのまちょうどエリアの真ん中ら辺ですね、22棟の北側から三条通りに面するところまでの広大な空地があるんですね。この空地は誰かと思ったら京都市の官房もちゃんと貼ってありまして、あったわけです。この土地というのは、市営住宅の整備に絡んだ土地なのかどうなのかっていうのちょっと確認したいということとある。この土地自身はその地元の方に聞いてたら、京都市がゆくゆくは緑地にしようとしてるんだっていう話とかもお聞きをしてるんですけども、これは実際どうなのかということで、結局、京都市は空地の部分はどのようにしようという風にして
取得をされてるのかっていうことについてあるいは別に京都市の土地じゃないん やったらそれでいいんですけど一応京都市のなんか看板も貼ってあったんでね京都市 のもんかと思ったんですけどこの点はいかがでしょうか。
担当部長:三条鴨東地区のことをご指摘をされてるのかと思いますけども、こちらにつきましては、住宅地区改良事業というものを実施をしているところでございまして、現在未買収物件がございますので、こちらの買収をに向けたま買収構想に向けた取り組みを行っているというところでございます。住宅地改良事業の中での緑地などにするような緑地にするようなことをあの計画所は位置づけているというところでございます。
とがし委員:住宅地区改良事業の中で緑地にするという、まずをされてるということなんですけど私はこれも、なんとかもっとうまいこと活用今ちょっと全面的これえっと宅地まだあの僕見に行きましたけど、人いらっしゃいまして、これ本当にそのままにしとくんでなくてちょっと建設工事の駐車場で使ったりされてますけども解放できるとこでも解放するとかなんかそういうこう段階的にでもあのま活用したらどうかと思ったりもしたんですけどまそういうのちょっと思ったんですけどただやっぱこれそういうことで言いますと京都 市として今回えっと都市再生緊急整備地域拡大するていう場合にこのこのえ緑地にするとしてるあの空地の部分についてはきちんとそら緑地のとしてきちんと位置 づけていくというのは変わらないっていう ことでよろしいですか。
担当部長:現在現在の住宅地改良事業におきましては緑にするとということをづけているというところでございます。
とがし委員:そうそうしますとやはりここの整備計画、結構そのあああいうとこに広大な緑地ができたらまどんな名前つけたらいいなろと思いながら思いましたけど、やっぱり都会のオアシスとか,そういうこう憩いの場とかねそういうものが、ここの中にえ整備方針の中に入ってきてもおかしくないんじゃないかなと思うんですけどそういうものがこう全然ないんですね。住宅地区改良計画の中で緑地にするんだという風にはっきり計画も持っておられるわけだからそれだったら、それにふさわしい記載があってもいいと思うんですけどそれはどこに該当しますでしょうか。
担当部長:都市再生緊急整備地域につきましては、この地区の全てのことを書くものではなくて、あくまでも、この中で民間事業者が質の高いえ公共施設整備を。伴ったような開発をする場合に支援を受ける際にあたって参考するというか、そういう時のための基準ということでございますので、特にこの住宅地改良 事業に関してその抑するというようなことは位置づけてはございません。
とがし委員:私はそういう枠組でないから書いてないんだっておっしゃるのやけど、そういう実際にそういう計画があるんですからそういう計画を前提にこういうものもあの整備 方針っていうのは立てられるべきだという風に思いますから。その点でも私はこれ は あのまおかしいんじゃないかと思いますし別にわざわざま言うてみたら公園に緑地 あるいは公園にするわけですからそうなってきましたら別にあの法律をいじくらなくてもあのできるわけなんでえしっかりとあの整備したらいいんじゃないかという風 に思いますからまその意味でもですね。これ改めてです。これここにそのえ都市再生緊急整備地域拡大っていうのがえ突然出てきたっていうのがやっぱり理解できないと いう風にまえっと指摘をしておきたいと思いますでえっと最後にですねあのこの エリアに隣接して今回指定されエリアに隣接して南側にフルモンフルモン前通り 元町地区がありますけれどもここはあの地区計画によって重環境保護されているん ですけども それとの関係で言うとやはりここれ本当に隣接しますし現状であればあの北川に えっと有さ小学校があるという状況の中でえ言ってみたらそこでま守られてる部分も あるかという風に思うんですけどもそれが今回その有さ小学校もこの再開発レアに 位置付けられてしまってるという点で私はちょっとそその点でここのあの住民の皆さんがせっかく地区計画を作って京都市もあの積極的に入ったっていう話聞いてますけども、その努力が代なしになってまうんじゃないかっていう不安を覚えるわけなんですけども、この点についての配慮とかは検討されてるでしょうか。
担当部長:えっと今回の整備地域の指定によりまして規制の強化緩和がなされるものではありませんので、現行の規制の通りで特に組織計画の見直しをしなければ、現行の規制通りで物が立つというところで ございます仮に今後あのこの地域の規制を見直すという必要が生じた場合にはあ都計画手続を通じて住民の方々の意見も 聞きながら判断をしてまいりたいという風に考えてございますとか私はですねあの隣接してるところがあるのでそれを例えば これいろんなあの条件とか整備方針の中にしっかり隣接するそういう地区計画についても尊重するとかねあの調和することとか があっても叱るべきではないかなと思ったんですけどちょっとそれはえ考えとられ ないということでまそれは非常にちょっと あの危惧する点であります。ちょっと11つ抜けておりましてあの有済小学校なんですけれども、私やはりあの地域の皆さんが先ほども、ちょっと他の委員からもありましたけれども地域の皆さんが非常に大事にしておられ、並行していこうもので、地域で非常にあのえあの有さ小学校の体感も含めてですねあの大事に使われてまして地域になくてならないものだという風に思いますでえそれであのまあそこま教育委員会も使ったりもしてますけども あのま是非あの有効活用を有効活用というかですねあのこういわゆるなんかまえ新党 の場合なんかはもう80年とか長期貸借とか話出ましたけどもそういう形ではなくて やはり地域の住民と一緒にまこのえ活用とか今ある施設を有効に使うということえま 適切に回収しながら使っていくということでやっていただきたいまこれあの要望しておきたいと思います以上で終わります。
(更新日:2024年05月25日)

京都市の本年度の予算案(第二次予算編成)が示されました
第二次予算編成が発表され、
第一次編成とあわせ、
松井新市長の初の予算編成の全体像がでそろった。
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000323130.html
前の市長さんのおっしゃっていた
財政破綻はどこへやら
厳しいと言いながら
凍結していた大型公共事業再開
消費的経費と投資的経費を区別していたけど
それをまるっと「上記以外の歳出」表現。
つなわち、大型開発予算が膨張すると
市民サービス予算が圧迫されるという
古臭いフレームが示されたわけだ。
あれだけ選挙で強調していた
第2子以降の保育料無償化も打ち出さず
開発は前のめりだけど福祉には鈍い。
もちろん、公共交通を守るための補助金などのメニューもあるけど、今後、
議員団で予算案全体を精査をし、
審議し、改善すべきは改善を求めたい。
#第二次予算編成
#京都市
#日本共産党 #京都市会議員
#とがし豊
(更新日:2024年05月21日)
第1回 元新洞小学校跡地活用の事業者選定委員会を傍聴して2024/5/20
 元新洞小学校跡地活用の事業者選定委員会を傍聴しました。「募集要項案」では、最長80年という定期借地権も可能で前例のない長期に渡る提案がされています。今回の審議を経て京都市が成案化すると思われますが、本当に80年もの長期・何世代もの先々までのことを今の世代だけで決めてしまっていいのか、従前の地域活動の継続と本館・前庭などの保存・再生などを基本とした活用を要望された住民の皆さんの意向が今回の「募集要項案」で本当に担保されるのか。住民の皆さんの意向もしっかりうかがいたいと思います。
元新洞小学校跡地活用の事業者選定委員会を傍聴しました。「募集要項案」では、最長80年という定期借地権も可能で前例のない長期に渡る提案がされています。今回の審議を経て京都市が成案化すると思われますが、本当に80年もの長期・何世代もの先々までのことを今の世代だけで決めてしまっていいのか、従前の地域活動の継続と本館・前庭などの保存・再生などを基本とした活用を要望された住民の皆さんの意向が今回の「募集要項案」で本当に担保されるのか。住民の皆さんの意向もしっかりうかがいたいと思います。
(更新日:2024年05月21日)
北陸新幹線の京都地下延伸計画、洛西など均一区間外での民間バスに同調した市バス運賃値上げについて、政府担当者から直接聞き取り〜倉林明子参院議員&京都市会議員団〜
日本共産党京都市会議員団は2024年5月15日、倉林明子参議院議員と一緒に国土交通省職員から2点の施策について説明を受ける「政府レクチャー」を実施。
北陸新幹線地下延伸計画について、民間バス運賃値上げに同調しての京都市バス運賃値上げについて説明を受けました。北陸新幹線に関しては「無用な混乱をもたらす恐れがあるから」とほとんどの情報が不開示とされましたが、わかったこともいくつかあり、その結果をご報告しています。また、バス運賃に値上げに関しては、同調しなくてもよいこともわかりました。実際はどうかは別として今後の議会論戦に大いに生きる収穫の多い取り組みとなりました。
(更新日:2024年05月17日)
聖護院門跡前のマンション建設の指導について(とがし豊)~京都市会まちづくり委員会2024年5月9日~
2024年5月9日京都市会まちづくり委員会
https://youtu.be/JePUtdmUrJ0?si=xOlNiX_6Uig716cl&t=3892
◇一般質問・聖護院門跡前のマンション建設の指導について(とがし豊)
とがし委員:どうぞよろしくお願いいたします。聖護院門跡前のマンション建設の指導について質疑をいたします。現時点での中高層条例や景観法に基づく手続きの状況と京都市としてどのように指導をしているところなのか。まずご説明お願いいたします。
建築指導部長:聖護院門跡前のマンション計画の中高層条例に関する手続き状況でございますが、令和5年12月7日に標識の設置が行われまして、同日に本市に標識設置届けが提出されております。その後、事業者が近隣住民への個別説明を行うともに、12月12日に条例に基づく説明会を開催されまして、令和6年 1月15日に説明状況報告書が提出されております。報告書の修正も終了しておりますので、条例上の手続きは完了しまして、今、建築確認の申請ができる状態となっております。以上でございます。
都市景観部長:続きまして警官に関する手続きの状況でございますが、山並背景型美観地区にかかる認定申請がこの地域ですと必要になってまいります。現在、事業者とは事前協議をしているところでございます。引き続きになりますが、春日北通からの見え方など、パースフォトモンタージュ、こういったものを利用しながらシミュレーション行い、検証
を1つ積み重ねて、歴史的な街並み景観あるいは東山36峰の緑豊かな自然景観との調和、こういった景観の基本方針に、あるいは、デザイン基準にあったものになっていくよう、引き続き求めてまいりたいと思っております。
とがし委員:そこでですね。景観法上の 手続きに関して当該地含む地域っていうのは山並み背景型美観地区に指定されておりますけれども、先ほどちょっと答弁が若干ありましたけれども、この地区の景観形成の基本方針について簡単にご説明お願いします。
都市景観部長:山並み背景型美観地区の基本方針についてでございます。まず区域についてでございます。京都大学・吉田・田中からなる鴨東地域の一部と、下鴨神社の北側の歴史的市街地の一部から構成している地区となります。この地区の基本方針に関しましては吉田山・糺の森の市街地における貴重な緑地空間の保全を図るととともに、これらの緑地景観に配慮した都市景観を継承することとしております。その中でも当該地、聖護院・吉田山周辺地域につきましては、吉田神社・真如堂・金戒光明寺等の社寺が立地し、それぞれに特徴的な景観を形成していること。また、銀閣寺道、東一条通、丸太町通から沿道の社寺と一体に東山の山並みを眺望することができ、東山を身近に感じることができること、こういった地域の景観特性を継承することを基本方針としております。この基本方針を実現するために、先ほど少し申し上げましたが、建築物の形態・意匠の制限を定め、指導しているところでございます。
とがし委員:そのデザイン基準なんかも、私も拝見させていいたんですけども、見下ろしの景観に配慮したまとまりある街並の景観を形成、大規模建建築物は東山への眺望に配慮、周辺への 圧迫感の低減、通りの景観の連続性の保全、背景の山並みまたは市街の緑との調和というものでありましてま詳細な規定もされております。昨年、12月6日にのまちづくり委員会の審査の際には都市景観部長の方から、景観との調和m、周辺への圧迫感の低減を図るためとして、春日北通からの見え方、聖護院からの見方につき、シミュレーションを事業者に出させて検証を行うという答弁がありました。今もちょっと先ほど答弁の中でも同じようなことあったんですけど、この実施状況っていうのはどういう段階でしょうか。
都市景観部長:先ほど申し上げましたが、現在の景観法に基づく認定申請はまだ出ておりません。事業者と事前協議の段階でございます。前回に私から答弁させていただいた通りですが、そういった特定の場所、春日北通りですと、聖護院の中からの見え方こういったもののシミュレーションを提出させ、それについて先ほど申し上げました基準に適合しているかどうか、こういったもののチェックを繰り返しております。
とがし委員:周辺の景観との調和という点で言いますと、吉田山や黒谷さんから聖護院に至るエリアっていうのは、低層の住宅群が広がっており、それが良好な街並の景観を形成いたしております。住民の皆さんがこの度眺望景観創生条例に基づく新たな視点場を提案され、東山の稜線が見えるようにして、実質的な高さ制限につながる提案をされております。この提案というのは良好な町並の景観を守る上でも非常にま重要だと、私は捉えているところです。審査には1年かかるという風に言われておりますけども、住民の皆さんは是非、今言った問題とも一体に検討して欲しいという風に求められております。この地区の景観保全する観点から、京都市として景観政策の政策上の手立てを何とか取れないかという風に考えますがいかがでしょうか。
都市景観 部長:繰り返しになりますが、基本方針につきましては景観法に基づく認定手続きの中でデザイン基準に基づく審査を通じて実現を図っていくものです。眺望景観に関する提案についての審査はこの美観地区の認定制度とは別の仕組みであります。ただ市民から頂いた貴重なご提案でございますので、提案内容が京都の優れた眺望景観の創生にふさわしいか否かを判断してまいります。その判断にあたりましては視点場として優れた眺望景観を享受できる場所であるのかどうか、対象として優れた眺望景観の要素となるかについて具体的に判断して参りたいと考えております。眺望景観については引き続き審査を進めてまいりたいと思っております。
とがし委員:是非、検討お願いしたいという風に思うんですけれども、やはり地域の方に取りましたら、これ視点場という形で提案はされておりますけれども、15mの壁ができることによって、今まで見えていたま大文字を初めとした眺望が一変するという事態となりますし、このマンションを許したら何が起こるかと言ったら、ドミノ倒しのようにどんどんとそういう15mのマンションが立っていくんじゃないかというま不安があります。そうしますと、歴史ある聖護院門跡の周りを15mのマンション囲むような事態なりかねない わけで、私はやはりそれは京都の景観のあり方で、この黒谷さんにつながるこの道のあり 方として、いいのかどうかってことは極めて大変重大な問題だと思っておりますし、今、景観保全していただきたいということで。景観政策の観点から是非しっかり取り組んでいただきたいということについて、改めて要望しておきます。
とがし委員:それで、中高層条例の手続きについては、説明状況報告書が提出されているという話でありました。ただ、それで説明が終わったというにならないというに思います。この間の三菱地所レジデンスによる住民説明会につきましても、やはり、説明はやっぱり不十分ではないかという風に考えますし、住民側が求めてる資料についても十分提出されていないという状況であります。地元の住民の方にお聞きしましたら、明日、三菱地所レジェンスによる住民説明会が開催されるという風にお聞きをしておりますけれども、事業者に対してはやはり住民への歩み寄りと共に、真摯な説明を求めたいという風に考えます。その点で京都市としても、こういう風に住民に寄り添ったま指導を求めるわけでありますけど、この点はいかがでしょうか。
建築指導部長:先ほどもご説明させていただきました通り、中高層条例の手続きは完了しておりまして、今回5月10日に行 れる説明会についても、当方で把握しておりませんので、事業者に確認しましたところ、条例に基づかないま任意の形で説明をされるという風にお伺いしております。そういう状況ではありますけれども、今後も周辺住民に対しまして、共同住宅の管理ですとか、工事の進め方につきまして、必要に応じて中高層条例に基づく手続きであるかどうかに関わらず、今後も必要に応じて、周辺住民に丁寧に対応するようにして指導してまいりたいという風に考えております。
とがし委員:先ほど景観のこともお話させていただきましたが、住環境の観点からも住民の皆さんはやはりこれはボリュームを下げて欲しいということを切実に求められているところです。先日は熊野神社のお祭りがありまして、このお祭りの際に、行列が最初に聖護院門跡に少年勤王隊の演奏を奉納するわけなんでありますけれども、その際に背景にはそのマンションの予定地があるわけです。まさに聖護院門跡の非常に大事な仮御所なども置かれた場所から、そういうマンションがど真ん前に見えるようになってしまうということであります。その意味で、しっかり低層にしていただきたいと。実際、私も感じましたし。何より、周辺は本当に2階建ての建物が並んでおります。その横に、真横に本当に15mの高い建物が立って5階建物 が立ってしまうということになると本当に住環境としては悪化します。すでに南側にもっと高い建物が立っておりまして、だいぶ日照が遮られてる状況の中であの建物が立つと、15mの建物ということになります。そうなりますと、完全に光が入らなくなるんです。三菱地所レジデンスからすると、自分とこの影だけが問題だっていう風にわるんですけども、やはり住まれてる方からすると完全に日照が遮られるという問題を受けるということであります。これ本当に住環境としても、眺望という点からも大変深刻であると私は思いますので、そういう住民の皆さんの思いもやっぱり受け止めていただきたいし、三菱地所 レジデンスからしたって、例えばその横に同じような規模のものができたら同じように自分たちの眺望も遮られるわけで、その意味ではあの地域においては2階 建てとか3階建てぐらいがふさわしいんではないかと思いますし、地主さんは東本願寺でありますけれども、地主さんともよく相談していただいて、この事業者の皆さんにも、考え直していただきたいなということについて要望いたしまして、質問を終わります。以上 です。
(更新日:2024年05月13日)

元松賀茂公園拡張予定地の売却について~2024年4月24日京都市会まちづくり委員会
元松賀茂公園拡張予定地の売却について 2024年4月24日まちづくり委員会
とがし豊議員(共)
よろしくお願いいたします。松児童公園の元拡張予定地だったところの売却について質疑を行います。京都市は4月3日に公募プロポーザルで住友林業を事業候補として選定しました。協議を経て5月上旬にも15億円で売却契約を結ぶという風に公報発表をされました。私は、現時点からでも売却を中止すべきであるということで3月の公募プロポーザルの最中ですけども、3月8日の代表質問でもそういう風に要望したところです。松ヶ崎にある松児童公園の横の緑地の売却の理由は「財政破綻しかねない」という前市長の認識でありましたが、財政破綻どころか2年連続の黒字決算に加え2年連続で収支均衡予算が提案され、2024年度に至っては前年度比で199億円多い予算がたてられた、と。で、理由が失われたわけですから公園整備計画のあり方そのものを見直して、今からでも売却を中止をして、京都市の予算措置で公演として整備すべきだと考えますがいかがでしょうか。
緑政策推進室事業進担当部長:元松賀茂公園予定地の跡地活用なんですけども、これにつきましては、周辺に公園が一定整備されておりまして、公園に求める機能が充足しているとか、新規より再整備の公園整備というのを重点的に進める方針であるとか、また、公園以外の土地利用へ転換を図ることが都市の発展につながるということから、公園予定地の都市計画を廃止させていただいております。また京都市の資産有効活用の基本方針というものを踏まえまして、本市での活用が見込めない状況であることから住宅系用途として売却するというような方針で取り組みを進めてきたというところであります。ということで、売却の方という形で進めているというような形でございます。以上です。
とがし委員:現時点についてはこの売却の契約に関してはどういう状況なんでしょうか。
緑政策推進室事業進担当部長:契約の状況なんですけど、昨日に、契約候補事業者でありました住友林業株式会社と本市の間で売買契約を締結したというような状況でございます。以上でござまいす。
とがし委員:元々ですね5月上旬に売買契約を結ぶという風に公表発表されていたんですけれども、何のための公表発表だったのかという風に率直に思います。既に売買契約もされたという話なんですが、私、あの広報発表の後で、周辺の住宅訪問いたしまして、回りましたけども、京都市から報告があったっていう方は誰もらっしゃらなかった。広報発表からだいぶたってから行ったんですけど、そういう状況でした。昨日、正式契約されたということですけれども、それまでのところで、やはり住友林業の計画について住民に対して周知をして意見を求めるっていうプロセスがあっても良かったんじゃないか、と。議会に対してもそういう場がなかったというのは極めて残念だという風に思います。そもそも、先ほど公園が充足している、「一定充足」って言い方でごまかされていたんですけど、公園は充足してないけど「みどり」はあるからということで都市計画が廃止されたということやったと思うんです。けれども私は、そもそも、緑の基本計画のところで市民1人当たりの公園面積を10㎡以上にしていこうということを掲げながら、6㎡に満たないという率直に遅れた現状がある、と。その中で実際に土地があるにも関わらず、売却していくということになっているわけで、この点について、極めて問題だという風に考えます。その点について、どうお考えなのかということと、今回の契約で結局、公園の面積は少しでも増えたんかどうか。この点はいかがですか。
緑政策推進室事業進担当部長:まず、今回売却させていただいた部分というのが公園予定地ということですので、現状の公園面積には含まれてませんので、数値としてはここが廃止されたことによっても変わらないというような状況になっています。地元の方々からも、様々なご意見をいただいているということで、通常でしたら、価格競争での一般入札という形で売却になるんですけど、地元の意見というものを慎重に踏まえまして、単なる価格競争ではなくて、住宅系用途として公募もさせていただいております。また、地元から出された隣接する公園の再整備という話もありましたので、そういう形の提案がいただけるような募集要綱の工夫もさせていただいた結果、事業者から公園の再整備というものも提案をいただいているということでありまして、地元の意見を踏まえて今回もそういう形で対応させていただいた状況です。
とがし委員:地元の声を聞きながらとおっしゃるんだけど、やっぱり1番多かった声っていうのは、きちんと計画通り公園として整備して欲しいというものであったという風に思います。それから、結局、公園面積は変わらないって話ですけれども、ここの議論なんかでも、それはやっぱり売却にあたっても、例えば開発される場合でも公園が提供されたりとかいうことがありますけれども、そういった公園を少しも増やさないっていうのはどういうことなんだという意見もあったかと思いますが、そういう声も踏まえられなかった、と。だから予定通りこれ全部売っちゃって売ってしまってるわけですね。そういうあり方が本当にそれでいいのかと思います。それから、先ほどちょっと選定にあたって、その既存の公園の部分について住民の声を聞きながら整備する、そのお金を住友林業が出してくれるという話なんですけれども、当然その時、きちんと住民の声を聞くってことはされると思うんですが、やっぱりあの公園自身があの面積やっぱり狭いていうのが公園の課題であって、公園を広くしてほしいっていうのが、元々あったということなんですね。だから、今度整備されて、もちろんその今の公園よりは機能は良くなるという風に思うんですけれども、ただそれは結局1990㎡の公園に過ぎない、と。本来であれば 5380㎡の大きな公園として整備、リニューアルと合わせてされるべきであったという風に思います。今回、住宅として販売されるという話になるんですけれども、15億円で、住友林業が購入されてるということで20戸にしていくと。住宅になっていくということでありますが、そうなると一戸 1億円以上の住宅が並ぶという話になるんじゃないかと。普通の若者世帯が入ってくるような利用の仕方にならないなという風に思います。ですから、今後の問題でも、契約されてしまったって話なんですけど、今後の公園の整備のあり方として、私は緑の基本計画で掲げた1人 当たり10㎡っていうのをしっかりと目指して公園整備していくという立場で財政状況もだいぶ変わってきたという中で京都市自身がもっと住みやすいまちにしていかなければいけない。魅力ある町にしていかなければいけないということ考えると、公園を増やすということについても真剣に考えていただきたいということを最後にお聞きしておきたいと思います。
緑政策推進室事業進担当部長:公園なんですけど開発なんかで事業者さんの方が開発公園という形で京都市の方に引き継いで京都市が完了していくという部分も当然ありますんで、公園が増えないということはないんですけど、当然京都市としましても現状としましては、やはり公園の老朽化というのが非常に進んでるということで公園のその再整備というのを重点的に 進めているというところでありますので、そういう状況も踏まえまして今後のあり方についてもしっかりと考えていきたいという風に思っております。以上でございます。
(更新日:2024年05月09日)

松ヶ崎かんぽ跡地の巨大マンション建設について~2024年4月24日京都市会まちづくり委員会
まちづくり委員会R060424①
https://youtu.be/ESksYmagR5A?si=MVb-7CS2lg3Ncvjk&t=5069
とがし豊議員(共)
とがし委員:よろしくお願いします。この松ヶ崎のかんぽ跡地、左京区役所の横に広がる広大な敷地でありますけれども、ここに大和ハウスなど5社が施主として長谷工に施工させてつくろうとしているという巨大マンションの問題についてでございます。昨年8月21日、松ヶ崎地連合会はこの京都市議会に対して大規模マンション建設計画に対する指導等を求める陳情書を提出し、このまちづくり委員会でも9月26日に審査が行われました。この陳情書では、明確に、松ヶ崎自治連合会としては松ヶ崎プロジェクトが松ヶ崎学区における良好なまちづくりを大きく阻害する計画であり、かつ、開発事業者が地域住民との対話に対し誠意ある対応をする意思がないと指摘をされていました。私はやっぱり、松ヶ崎住民の総意を汲む形で自治連合会が提出された極めて重たい陳情であったという風に思っております。そこで改めて京都市としてこうした住民、松ヶ崎住民の皆さんの思いに寄り添って事業者に対して計画的な抜本的な見直しを求めていただきたいという風に思いますが、この点はいかがでしょうか。
建築指導部長:今回の計画に対しましては京都市も早い段階から事業者との協議を行いまして地域の方の声もお聞きしながら中高層条例の手続きにおきましてもその趣旨に基づきまして周辺の住環境に配慮した計画となるように関係機関と連携しながら指導を行ってきたことところでございます。その結果、日照や通風また見下ろし対策などにつきまして、例えば、三方の道路からのセットバックによる圧迫感の低減が図れますとともに、道路の安交通安全対策として敷地内に2mの歩道を拡幅整備するなどの対策が図られてきたところでございます。そのように地域の方のお声も頂戴しながらそれを反映させる形で計画が進んできたところなんですけれども、今回、抜本的おっしゃっていただきましたけれども、各種の関係法令に適合した計画でありましたら、なかなかそのボリュームの低減などについての指導は困難ですけれども、今後も見下ろしとか、安全対策などにおきまして、周辺の重環境に配慮した計画となりますように、引き続き周辺住民に丁寧に対応するように指導してまいりたいと考えております。
とがし委員:今おっしゃられた部分っていうのは本当にもう本当に微々たるものでありまして、もっと事業者はこの松ヶ崎学区のあのエリアに大変なインパクトを与えるということをもっと自覚をして、もっと譲歩すべきであるという風に私は思っております。9月26日にも、やり取りありましたのでその点は省略いたしますけど、この自治連合会がまとめになった4点、住民の声を具体的な声として4点整理されております。大規模な敷地を取り囲むような建築物に対して多大な圧迫感を感じるため建築物のボリュームを大きく低減してほしいということ、敷地境界近くまで中高層の建築物が建設されることから周辺の低層住宅の住民に対するプライバシーが大きく侵害されるため、建物の建築物の高さを抑えるべきだと3つ目には防災上の観点から消防車両の乗り入れや消火活動に支障をきたすことが懸念される建築物の密度であることから土地利用計画を見直すべきだ、と。4点目には400世帯分の住民の車両・自転車・歩行者等の出入りにより敷地周辺地域の住民の住環境が一時悪化することが懸念されるため、敷地内への出入口、敷地内透水施設配置計画を見直すべきだ、と。こういう風に指摘をされましてこれに対して抜本的な解決に取り組むという回答が得られないということが指摘をされて、今回この計画っていうのは、やっぱり地域の良好な住環境に適合しないんだということで見直してほしいというところから、昨年の陳情が出されているということであります。私、やっぱり抜本的には、実質11棟の建物であるにも関わらず廊下で繋いたら一棟とし見なしていいんだという、このやり方自体に大変大きな問題があるという風に考えます。そして、本当に今必要なのは、やはりここの松ケ崎で言うと妙法の眺めを保存して8月16日に送り火をされるということで、その妙法を見てもらう人っていうのはあのマンションの上層階に住んでいる方に見てもらうというよりは、もっと広い松ヶ崎あるいは京都市民全体にできるだけ多くの方に見てほしいと、見えるように取り込まれているということでありますので、そういう思いから、出されてきているということをご理解いただきたいと思います。その意味でやはり京都市にとって京都市民にとって極めて大事なその五山の送り火の景観というものが長大な壁のような建物ができることによって阻害されてしまうということなるこの計画については京都市としても、京都市のアイデンティティ、事業者もですねえその京都市のそういうもの売りとして住宅を作られた販売されわけですからその意味ではやっぱり京都市としても京都の町のあり様というのものについても施主である大和ハウスも含めてですね、しっかりとお伝えいただきたいという風に思います。そういう形で是非住民にとことん寄り添った対応というのを求めて終わります。以上です。
河村諒議員(維)
よろしくお願いします。今おっしゃられた地域の感情に配慮しつつ、市として定めたもの諸々には適合した形でマンション建設、助言認めていきたいという話でございますけども。確認なんですが、その街づくり条例であったり景観条例であったり、その他、市が規定する様々な条例規則全てに基づいて全てその今回建築されるマンションについては適合してる ことは確認をされていらっしゃるんでしょうか。
建築指導部長:民間の指定確認検査機関によって確認は降りてるんですけれども、それに必要な関係法令の他に、景観法と景観に基づく手続きですとか、まちづくり条例も都市計画課内の手続きなどにつきましても、きちんと適合してるという風に捉えております。また、防災上につきましても建築基準法に定められております消防署の同意を得て進められていると いうことを認知しております。
河村副委員長:分かりました各法令に従ってしっかりと審査されているということでございますけれども、であれば、今回私もやっぱり住んでるのが下鴨なのでこういったお声たくさんします。やはり住民の中ではですね、長谷工さんですか事業さんが住民の意見に寄り添ってないばかりか、なんか抜け穴みたいなのを利用してるんじゃないかとか、そういったそのいわゆる疑問というかそういったものがやはりまだまだ地域の中には存在いたしますので、この法令にちゃんと適合しているという場面について事業者任せではなくて、やはり市の方から行政としてしっかりご説明する機会っていうのはもう1度複数回設けていただくというのが必要かと思いますがいかがでしょうか。
建築指導部長:中高層条例の手続きも最終的に行ってもらったんですけれども、その趣旨としまして計画の周知の手続きですとか、紛争の予防ということがございますけれども、説明会を中高層条例に基づく説明会だけでもえ過去に3回していただきましたりですとか、その後調整会議も2度行ったと。それで合意に至らなかったためあの今回調停に進むということになっておりますので、引き続き地域の方のご意見も聞きながら、しっかり進めていきたいという風に考えております。
河村副委員長:わかりました。一定ご努力いただいていることは私も存じ上げております。しかしながらやはり説明にあたってはその点については事業者に任せていますとか、あの資からは答えられないという風な回答が非常に多かったと私ちょっと実際見てないの申し訳ないんですけどもありまして。で、そういったところやはり条例とか規則に基づいてはしっかりやっている今答えていただきましたけど、これに加えて、地域の感情的なものもしっかり考慮いただきまして、既に2回3回やっていただいていると言わずに、やはり納得行くまで市民を派遣し、市民に対しての説明派遣していただくとか、事業者にお任せせずに行政として立場発揮をしていただくようなことが今後も必要になってくるかと思いますので、すでに十分やられているということも十分分かっておりますけれども、これ以上にもう少しお時間と手間をかけて説明していただきたいと思います。最後にこの辺りについてご答弁お願いいたします。
建築指導部長:今ご指摘いただきましたけれどもやっぱり事業を進める主体として事業者がきちんと周知をすると説明をするということが定められておりますので、それを中高層条例の趣旨として責務としても定めております。京都市の責務としてはそれをきっちりと進めていただくというような指導を指導するということを責務として定めておりますのでそれぞれ事業者さん、京都市住民の責務を果たしていきますように、これからも進めたいと思っております。
河村副委員長:ありがとうございます。しっかり事業者に対して指導していくのが仕事であるというにはもちろんそうだ 思うのでございますけれども今回特にカンポということで半公の施設だったということが非常に市民に対して京都市が関係あるんじゃないかという感じを呼び込んでおりますので、そういった規則とか、そういったもの以外のところについても配慮いただかないとこの問題なかなか根深い問題でございますので、今後も引き続きご努力の方をお願い申し上げて終わりたいと思います。以上です。
(更新日:2024年05月09日)

2024/5/3 #stop気候危機 #気候アクション 堀川あきこさんと
去る5月3日、憲法集会に参加した後、堀川あきこさんとJCPサポーターの皆さん呼びかけの気候アクションに参加。
#地球沸騰 #

気候危機打開へスタンディングする左から河合ようこ市議、加藤あい市議、堀川あきこさん、とがし豊市議
ClimateAction #気候危機打開
(更新日:2024年05月08日)