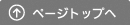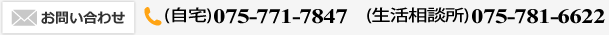活動日誌・お知らせ
#京都市議会5月補正予算の審議の報告です!医療機関・従事者支援、PCR検査について質疑
本日は、市議会の5月補正予算の審議が3つの委員会に分かれて行われました。
私は、保健福祉局・子どもはぐくみ局・建設局・教育委員会に関連する議案の審議を行う分科会に出席し、質疑に立ちました。
厳しい経営に立たされている医療機関支援強化に向け、その前提となる実態調査を求めました。保健福祉局は、実態把握ができていないことを率直に認め、ヒアリングの実施を約束しました。PCR検査の拡充をめぐっては、一日当たりの日常的な検査体制は現状80件に上乗せ10件を行う予算とともに、集団感染の疑いが生じた場合にそなえた3000件を9月末までの検査予算であることが明らかになりました。
医療崩壊を食い止めるために、感染拡大が一定収まっている今だからこそ、第二派に備えて、入院患者や医療従事者へのPCR検査の実施も求めましたが、認められませんでした。京都大学や府立医大などが少なくとも手術患者などへのPCR検査公費助成を求められていることも紹介しましました。
妊婦へのpcr検査の公費助成について、いったん本人が負担して後から公費助成となる「償還払い」ではなく、行政が直接支払う方式になるように鈴木議員が求めました。
教育委員会には、ICT環境整備の必要性は認めつつも、その活用の前提としても、少人数学級の必要性を樋口議員が指摘しました。また、経済産業省が「共同の学び」を否定し、教育よりも狭い意味の「経済」を優先する動きがあることに警鐘を鳴らしました。
そして、委員会が終了直後には下記のように、緊急事態解除宣言の報道。
「緊急事態宣言」諮問委が全面解除を了承 5/25(月) 14:02配信
https://headlines.yahoo.co.jp/vide…/nnn…
日本共産党左京地区委員会では、現在、左京区内の学生マンションなどに以下のようなチラシ(QRコードからサイトに入って回答)をお配りするとともに、ネットでも直接アンケートを募集中です。
https://docs.google.com/…/19u…/viewform…
(更新日:2020年05月25日)
#保健所の体制強化が必要 #COVID19
#保健所の体制強化が必要 #COVID19
◆1994年以降の「保健所」切り捨て政策の見直しが急務
今朝の毎日新聞。とても大切なことを伝えてくれました。新型コロナウイルス対策で厳しい状況にある保健所の実態を特集している。1990年度に全国850か所あった保健所。1994年の保健所法改正により、おおむね10万人当たりに1か所設置するとしていた指針を廃止以降、各地の行政の「効率化」の掛け声の下で、統廃合が進み、2019年度は427か所に半減。とりわけ、政令指定都市である大阪市では2000年に24区にあった保健所を一か所に統合していることを紹介している。そして、新型インフルエンザ流行直前の2009年3月に、保健所長会が保健所機能弱体化を懸念し、医師ら専門職の人材確保と育成が急務であることを表明していたことも伝えています。
◆京都では公務員削減の嵐と一体に
2010年、2017年に大改悪
京都では、2010年に各行政区にあった11の保健所が、京都市役所に一本化されて、各区保健所は保健センターに格下げされ、保健所としての基本的な権限は市役所に集中。この保健衛生体制の後退を許してはならないと、労働組合の皆さんも、そして私たち日本共産党市議団の徹底的に闘いましたが、今の市長の下で、強行されてしまったのです。
とはいえ、当時の保健衛生室長は「日常的な業務については保健センターで完結できるようにしている」との答弁(2010年10月6日決算特別委員会、私への答弁)にみられるように、権限のみの一本化という話でした。ところが、その約束は、7年後に裏切られることになりました。2017年の組織改正です。その現場に残っていた保健所機能=「日常的な業務」さえも、本庁にある京都市保健所一本にしてしまったのです。
民泊対策で直ちに問題が生じました。それまで住民の相談に乗ってきた各区にある保健福祉センター(組織改編前は「保健センター」)が、住民が相談にいっても本庁の窓口を紹介するという対応にかわってしまったからです。感染症対策も同様に本庁へと完全に引き上げられていくということに。
左京区役所・保健所の移転問題のときに、現場の皆さんとよくお話しする機会があったのですが、極めて大変な業務量をこなしていらっしゃいました。もっともっと地域の皆さんといっしょに取り組みをしたいとおもっても現実にはなかなか仕事がまわらないという厳しい状況を聞くにつけ、この業務をリストラの対象とする国や京都市の在り方に大変な憤りを感じてきました。充実すべき保健所体制を、リストラの対象とみなしてきたこれまでの京都市政、国の政治を、この際しっかりと改めさせる必要があると考えます。
◆特集/役割が多岐に及ぶ『保健所』に密着…電話相談・検体回収・結果連絡・入院や宿泊施設調整まで MBS 2020年5月1日㈮放送
https://www.mbs.jp/mint/news/2020/05/04/076822.shtml
◆瀬戸際の保健所 いま何が起きているのか NHKWEBニュース
2020年4月28日 23時07分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200428/k10012409901000.html
・罵倒される保健師たち
・「ただ頑張れ、のみ」
・統廃合進む保健所 約30年でほぼ半減
◆大阪市保健所 コロナ対応職員、月平均60時間残業 昨年から倍増 市民から罵声も
会員限定有料記事 毎日新聞2020年5月10日 05時00分
https://mainichi.jp/articles/20200509/k00/00m/040/154000c
◆《新型コロナ》保健師、長期戦で疲弊 患者の聴取や電話相談殺到 茨城県、退職者を採用へ 茨城新聞 5/10(日) 7:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200510-00000007-ibaraki-l08
(更新日:2020年05月10日)

#フィンランドの教育 これからの学校教育を考えるヒント
話題①こんな時だからこそ、学校教育を考えたい。
いつか行って学んでみたいと思う、フィンランドの教育について、デジタル視察してみました。あくまでも、ネットで拾ったものでありますが、一定の実態を反映していると思いますので紹介します。
9月入学とか、小手先の制度変更でなんとかなるというのは大間違い。
この際、コロナ後の教育は、抜本的に変えさせましょうや!!
すでに日本の子どもたちは、14万人が30日以上学校に行かない不登校。
立派な「スクールストライキ」です。
非常事態です。
そこにコロナ危機が来たわけです!
感染防止対策を実施できるようにするためにも、学級編成の見直しや一人一人への子どもへフォロー体制の確立は不可欠でしょう。
◎おすすめサイト◎
フィンランドの小中学校教育 5分でわかるフィンランド
・20人以下の少人数クラス、宿題は最小限、数字による成績評価も最小限、成績ランキングがない
・義務教育である基礎教育は小中一貫校の9年間
・学費が当然無料で、教科書や教材なども無料、で提供毎日昼食が無料
・芸術、音楽、体育、語学の教育に特化した小中学校もあり
・「エリートを育てない」どんどん先に行かすのではなく、わからないこのサポートをするように指導
◎おすすめサイト◎
「海外に”不登校”という概念は存在しない?フィンランドの事例」
・いろんなスタイルで、リラックスしながら授業が受けられる子どもたち。
・子どもを学校に「適応」させるのではなく、学校をあわせる。
・学校の中に、さらに「少人数学級」もあり、子どもの違和感をとらえて予防的に対応。
・地域に30歳以下の子どもたち・わかものたちがくつろげる場所があり、よき相談相手となるお兄さん・お姉さんがいて、学校にも顔を出してくれる。
話題②これは面白い、強く同意↓
日本共産党の今回議員・zoom会議
#新型コロナ、国政を論じ尽くす
https://youtu.be/qy5FaGag5jU
・人間を人件費で見るのをやめようよ!人を大事にというタムトモの最後メッセージよかった。ライブ中になんと1万4千ものメッセージがあったとのこと。
(更新日:2020年05月05日)
学校休校が長引く中、児童生徒の健康上の課題への対応と学習・発達保障を
党市議団では、学校休校が長引く中、児童生徒の健康上の課題への対応と学習・発達保障を強く求めています。
学校再開してほしいけど、感染拡大防止対策とどう両立しながら学校を再開するのか、という不安の声もお聞きします。そして、再開するにしたって、すでに3月、4月と二か月の空白が生まれているもとで、5月も休校が伸びる可能性があるわけで、そのもとで学校が再開したとしても、教育内容の精査は避けなられないでしょう。
文部科学省が検討しているという手段をとったとしても、専門家会議が「長期化」を念頭においているもとで、学校のありかたそのものを大きく変えないと無理でしょう。
だからこそ「学校」って何か?今こそ考えなくちゃいけないと思っています。
「学校」によって、子どもたちが何を得られるのか、それを休業中にも少しでも保障するすべはないのか。「登校日」や再開後のわずかな機会をどういう時間として生かしていくのか、この機会に私自身もしっかり整理したいと思います。
皆さんもぜひご意見ください。
ーーー参考(5/4朝改定)ーーー
◼️京都教育センター「今、伝えたいこと」より
https://www.facebook.com/143072902712977/posts/1105764683110456/
◼️京都教職員組合の4/10時点での「第三次申し入れ」学校再開に関連しては、科学的な判断とともに、子どもたちの状況も踏まえた抜本的な教育環境の改善を求められています。
https://6b51eecd-ce17-4857-9778-5052195…
(更新日:2020年05月04日)
野党は補正予算組み替え動議でさらなる改善提案を示しつつ、10万円給付など実現をふまえ賛成。成立。
補正予算が昨日成立しました。
日本共産党ふくむ野党勢力は「予算組み替え動議」を財源も示して提案。
提案型で問題点を指摘をした上で、
まずは、野党が要求してきた一律10万円給付が実現したことなどをふまえ、賛成しました。
—————以下、しんぶん赤旗より—————
野党の補正予算組み替え動議(要旨)
日本共産党と、立憲民主党、国民民主党などの共同会派が29日、共同で衆院予算委員会に提出した2020年度補正予算案の組み替え動議(要旨)は以下の通りです。
【組み替えの理由】
新型コロナウイルス感染症の拡大により、国民生活と経済は先行きの見えない厳しい状況に陥っている。今こそ迅速かつ大規模に、事業や雇用、生活を守る措置を講じ、早期収束に向けて感染拡大防止と医療崩壊阻止に全力を傾ける必要がある。しかし、政府提出の補正予算は対象期間が不明であり、国民が先を見通すための予算措置として質的、量的に十分ではない。
政府は、2020年度補正予算案を撤回し、当面6月末ごろまでの緊急経済対策として、編成替えを行うべきである。
【概要】
1、追加歳出
(1)生活支援・事業継続支援
(1)中小・小規模事業者等の持続化給付金の倍増(+2・3兆円)
・要件緩和を含め持続化給付金を拡充し、予算を政府案の2倍に引き上げる。総額4・6兆円。
(2)中小・小規模事業者等の賃料の支払い猶予(財政投融資 +5兆円)
・事業用の不動産の賃料について、財政投融資を通じ、支払い猶予を行う。求償権の行使は、社会情勢や対象の中小・小規模事業者等の事業の状況等に配慮。その財源については一般会計において措置する。
(3)雇用調整助成金の更なる改善
・雇用調整助成金の特例について、日額上限を一定程度引き上げるとともに、中小企業の助成率を10分の10に引き上げる。
(4)地方創生臨時交付金の追加(+4兆円)
・緊急経済対策では自治体が地域の実情に応じて施策を実施することが極めて重要。自治体の裁量権を高めるとともに、休業協力金などの給付、テナント賃料の補助、介護施設への給付、保育や学童保育の支援などを独自で実施できるよう、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を大胆に増額。総額5兆円。
(2)医療等支援
(1)緊急包括支援交付金の改善(+0・85兆円)
・医師や看護師等への危険手当の創設、PCR検査体制の強化、人工呼吸器、高騰するマスク、防護服等の調達、軽症者等受け入れ施設の全国への設置などのための交付金を拡大。財政力の多寡によって対策が左右されることなく、交付金が迅速に執行されるよう、地方の負担割合2分の1を全額国費負担に切り替え。総額1兆円。
(2)医療機関等支援給付金の創設(+0・5兆円)
・上記の交付金とは別に、新型コロナウイルス対応等により経営環境が悪化している医療機関の経営を支えるため、給付を行う。総額0・5兆円。
2、歳出削減
○Go Toキャンペーン事業(1・7兆円削除)
・Go Toキャンペーン事業は、次の局面での予算計上とする。
3、追加歳入
(1)特例公債の追加(6兆円)
(2)財投債の追加(5兆円)
(更新日:2020年05月01日)

無駄&違法な「公共事業」と闘う住民グループが21日に京都市長相手に控訴!
2月17日の京都地裁の不当判決に屈せず、住民の皆さんは4月21日、ついに「控訴」に踏み切りました。
左京区・高野川に新たな橋をかける工事をめぐる裁判です。
もともとあった80年前の都市計画決定を放置しておきながら、計画にもないはしを3本も次々と無計画に近辺に架橋してきた京都市が、どうして今頃、8億円もかけて橋をかけるのか!
そして、そのためにどうして土地を削られなければならないのか・・・
納得のいく説明をもとめる住民に終始一貫して不誠実な対応をしてきた京都市。
それに憤り住民が調査すると、なんと都市計画決定とは14mもずれた場所に架橋しようとしており、土地収用をしようとしていることが発覚。明治憲法でも現・日本国憲法でも守られるべき「財産権」を侵害する京都市長に対し、違法な工事への公金支出の差し止めを求めています。
フェイスブックの動画で紹介しています。
(更新日:2020年04月30日)
新型コロナウイルス感染症対策に全力ーー「糺の森」4月号へ寄稿
今月の「糺の森」も大変読みごたえありです。
ここをクリック→2020年4月号「糺の森」
ゲストハウスを経営する方が、観光産業の厳しい現状を訴えられており、政府の政策についてももっと中身があるものにと切実な意見を表明されています。
私も、寄稿させていただきました。
この間の商店街などへの聞き取り調査を踏まえて、国待ちにならずに東京都が行おうとしている「感染拡大防止協力金」などを京都独自でもつくって即効性ある中小零細業者への支援策をうたなければと書かせていただいています。
また、歴代自民党政権によって削りに削られてきた保健衛生体制の後退路線が京都市行政にも深刻な打撃をあたえており、その立て直しが、今後の新型コロナを抑え込んでいくうえで極めて大事だという趣旨で書かせていただいています。
2020年4月号「糺の森」
(更新日:2020年04月16日)
気候危機といいながら、地球温暖化対策費をこんなに減らすなんておかしい!
2020年度一般会計予算(環境政策局分)
<概要>
一般会計合計 本年度予算195億7200万円(前年度比△11億6100万円)
地球環境保全費 6億9818万円(△1億2511万円)
ごみ処理費 183億2210万円(△4億6619万円)
廃棄物適正処理対策 5160万円(△5億1512万円)
し尿処理 5億0010万円(△1億1414万円)
「気候危機」といいながら、地球温暖化対策予算を削減!?あまりにひどい。
私は目を疑いました。さも「充実」かのように説明をしておきながら、分厚い予算書を精査してみると、なんと地球温暖化対策費が8259万円削減も削減。エネルギー担当部長は、6000万円の太陽光パネルの設置助成金削減をめぐって、制度の有効を認めつつも「厳しい財政状況を踏まえ、実績実情に応じた予算」と答弁。市長は「太陽光発電は強化してきたが補助金でやっているがこれは必ず破たんする」と局答弁よりも後退した答弁。市長は「補助金から脱却」「市民意識を高くして未来に負荷かけないやり方を取り組む」と、経済的メリットによる誘導ではなく「意識」による誘導を主張するなど、この間の温暖化対策の教訓を全く理解しない主張を展開。市長の姿勢が温暖化対策推進の桎梏となっていることがよくわかりました。このままでは、見通しは暗い。「気候危機」を全国に先駆けて発したはずの市長がこんな予算編成をするとは・・・。
局別では私から、市長総括質疑では山根議員がこの問題を追及。新規事業はおおいにやるべきだが、「気候危機に立ち向かう上でこの1・2年が重要」固定価格買取制度に基づく価格低迷という政府の政策を見直させるとともに、京都市としても予算減額ではなくより使いやすい制度へと見直すべきと求めました。当然の前提として、京都市自身が消費するエネルギーにおいても再エネ100%目指すべきことも求めました。
ごみ減量の目標達成は厳しい!皆さんの協力が必要です
有料指定ゴミ袋の販売によって手数料を得る方式が、地方自治法227条の「特定の者のためにする事務」に該当しないことから、違法であることを指摘。厳しい経済情勢下で値下げすべきと求めました。値下げと合わせて、分別のさらなる徹底や拡大に協力を仰ぐべきと考えたからです。観光地のごみ対策は強化されますが、地元との丁寧な協議を求めました。食品ロスゼロに向けてフードバンクへの支援強化を求めたところ「補助制度を改善する」「フードバンクから福祉団体へスムーズかつ量的に多くいきわたるように連携する」と積極的な答弁が。この点では、京都市と私たちの思いは一致します。脱プラスチックにむけデポジット制の導入を迫りましたが、京都市としては国に要請しているという答えにとどまり、地域連携で実施という提案はうけとめてはいただけませんでした。
これ以上のごみ収集の民間委託化は災害対応など支障をきたす
ゴミ収集の民間委託率が61%まで拡大したもとで災害対応などに支障をきたしつつある実態を告発し、さらなる委託化を進める予算を批判。新規採用を行わないことが職場のモチベーションを下げている点を指摘しましたが、人材育成・監察・業務改革担当部長は「業務の多様化高度化に対応した任用制度に再構築」を内部検討していると答弁。詳細は答えませんでしたが、採用方法を変えたところで、現場に新しい人が来ないなら同じです。東北部クリーンセンター改修やクリーンセンター運営について、京都市職員自身に技術や経験を蓄積させ技術職を育ててこそ、適性な仕事の発注、チェック・改善が可能になることを指摘し、民間委託化に進むべきではないと指摘しました。
まともな環境アセスメントができない「北陸新幹線」の実態
北陸新幹線敦賀新大阪間の環境アセスメントに関して、党委員が「必要性、弊害の有無、住民の合意、費用負担の相当性も含めていったん立ち止まって十分な環境影響を推し量るべき」と求めたことに対し、技術部長は「環境影響の観点から意見を述べるもの」「可能な限り・・・回避・低減に努める」「環境で新幹線をとめろという議論ではない」「(審査会で)一部の方の意見はあるが、全体的には総じて前向きの意見」と開き直りました。審査会では、京都市長の委嘱をうけた専門家の先生方が、機構側がしめした情報があまりにも乏しく判断しようがないことに厳しい意見を多数だされていました。
土砂条例は他の市町村並みに厳しい内容にせよ
土砂条例制定をめぐっては、パブリックコメントで京都府よりも面積基準を厳しくすべきという意見が多数出されたにもかかわらず、なんら修正しないまま議会に提案したことを厳しく指摘。大岩山の違法開発を反省し、条例案の修正を行うべきと求めました。
他会派の議員からはこんな質疑が・・・
自民党からは、クリーセンター破砕機での火災要因となっているリチウムイオン電池の分別徹底、東部山間埋め立て地の延命、不法投棄監視カメラについての質疑。気候変動をめぐっては、公明・民主・維新が京都市の新規事業を評価する質疑。京都党からはごみ有料化財源の有効活用、観光・公衆トイレ対策の拡充の質疑。
(更新日:2020年03月19日)

2020年3月19日、安倍9条改憲NO!左京みんなのデモ&市役所前集会・デモに参加

恒例の「左京みんなのデモ」
35人の参加。
新型コロナウィルスを口実に、
緊急事態条項で国民の権利を極端に制限する法改正を強行し、それを「憲法改正の実験台」(伊吹文明衆院議員・自民)といってはばからない自民党。
国民の苦難によりそうのではなく、
政権の都合でこんなことをやっている場合か?
穏やかな小春日和でしたが、
私は怒っていました。
そして、市役所前の集会とデモに合流。

2020年3月19日安倍9条改憲NO!市役所前にて、京都市会議員団。
(更新日:2020年03月19日)
京都市2020年度予算審議・選挙管理委員会~2020.3.3選挙公報配布の遅れ改善を
●選挙広報、選挙ハガキの期日通りの配布。郵便投票対象範囲の拡大を
◯選挙公報の配布時期について。京都市長選挙で、投票日前日の2月1日ぎりぎりに配ら
れたという声があちこちから聞こえてきた。ハガキの到着も期日前投票に間に合っていな
い。①選挙公報の遅れた理由はなぜか。②ハガキについては、次の選挙からは期日前投票
には必ず間に合うように依頼を各郵便局に対して求めるがいかがか。
(→大西選挙管理委員会事務局次長)1月19日、告示日の5時締切で選挙公報の提出が
あり、24時間体制で印刷を行い、20日の正午に印刷ができあがった。それから配送業
者に持ち込まれたのが1月21日、8000人以上いる市政協力員のところに配送された。
市民新聞2月1日号の配送の時期と重なって、仕分け、配送に時間がかかり、通常より2
日ほど遅れた地域が出てしまった。選挙広報は民主主義の根幹であり、市民新聞の配送に
よって遅れたのは本末転倒でありあってはならないこと。今後は他局との事前連絡を行い
遅配にならないようにしていきたい。
ハガキについては、郵便局の郵便約款に、郵便物の送達は差し出された日の翌日から起
算して3日前以内との決まりがある。告示日の3日前の1月16日に発送している。郵便
局に確認すると結果として5日程度かかった所もあるとのことで、今後郵便局と協議しな
がら対応を検討していきたい。
◯いつまでに配布するのか含めて事業者との間での契約をきちんと結ぶべきだ。他局との
調整がいるというのであれば、事前に相談いただきたい。市民新聞と選挙公報は全く性格
が違う。配布が重なる場合は選挙を優先すべき。各区長が民主主義の根幹にかかわると回
覧板で回しておきながら、選挙公報が前日に配布など話にならない。再発防止を求めてお
く。
今回の京都市長選挙では「はじめて選挙に行く」という方の中から、あるいは投票所が
変更になった地域から問い合わせなどもあったかと思う。それらの問い合わせの実績など
をしっかり分析して対応をお願いしたい。また、直接お聞きした中では、ネットなどで場
所を調べられて現地に着いて入り口がわからないというケースもあったそうだ。投票所の
入口への誘導についても改善を。
(→大西次長)各有権者1人1人に地図の入ったハガキを送っているが、ホームページで
も発信していきたい。伏見区と上京区で投票所の変更があったが、事前の市民新聞や回覧、
全戸配布でのチラシ、広報車での啓発などで特に混乱はなかった。引き続き投票場所の周
知に努めていきたい。
◯郵送投票の拡大を求める。現在は、限定的であり、病院・福祉施設などで投票が事前に
可能なところもあるが施設による。在宅の場合もある。そうした方の選挙権もしっかり保障する必要があると考えるが、その点で郵送投票の対象を拡大していくべきだがどうか。
(→大西次長)不在者投票の一つに郵便投票があり、重度の障害のある方、要介護5の方
が対象となっている。要介護5ではなくても、外出が困難な方も増えており、政令指定都
市選挙管理委員会連合会で、公職選挙法の改正要望で、郵便による不在者投票の適用対象
範囲の拡大を要望している。総務省でも、平成29年6月、投票環境の向上方策等に関す
る研究会において、要介護3の方まで対象となることが適切との報告がまとめられている。
◯ぜひ、他の政令指定都市とも協力して実現していただきたい。障する必要があると考えるが、その点で郵送投票の対象を拡大していくべきだがどうか。
(→大西次長)不在者投票の一つに郵便投票があり、重度の障害のある方、要介護5の方が対象となっている。要介護5ではなくても、外出が困難な方も増えており、政令指定都市選挙管理委員会連合会で、公職選挙法の改正要望で、郵便による不在者投票の適用対象範囲の拡大を要望している。総務省でも、平成29年6月、投票環境の向上方策等に関する研究会において、要介護3の方まで対象となることが適切との報告がまとめられている。
◯ぜひ、他の政令指定都市とも協力して実現していただきたい。
(更新日:2020年03月09日)