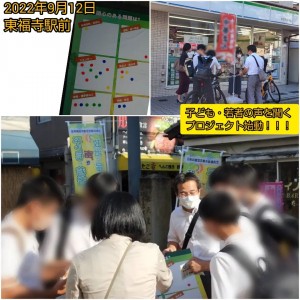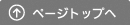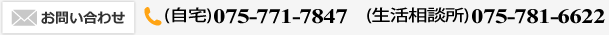え?健康保険証がなくなる?
病院にかかりたかったら
「マイナンバーカード取得して
マイナ保険証にせよ」だって?
ーーーーーーーーーーーーー
政府は2023 年 4 月からの医療機関での「マイナンバーカードの保険証利用等に係るシステム導入の義務化」、2024 年秋からは「健康保険証」を廃止し、マイナンバーカードと一体の「マイナ保険証」を押し付ける方針をしめました。
この方針の撤回を求める意見書を京都市からもあげるべきだ!と、党を代表して11月2日、討論に立ちました。
健康保険証を廃止してマイナンバーカードに切り替えさせるなど、あまりにも強権的。
システムの義務化を強行すれば、コロナ第8波の最中に、経費負担に耐えられず廃業する医療機関も生まれかねません。
党以外の反対で否決となりましたが、
引き続き、議会内外で頑張ります。
(更新日:2022年11月20日)
2022年10月25日京都市議会産業交通水道委員会
京都市森林文化交流センター(森愛館)を含む山村都市交流の森センターエリア等の活用事業者の募集について、質疑しました。
森愛館がこれからどうなるかもわからないのに、とりあえず、今年度で公的施設として廃止する条例提案が11月市会に提出されるとのこと。山村と都市の交流、左京区北部エリアのまちづくりの拠点としても、「採算」ではかる考え方はおかしいと指摘し、公的施設として存続をもとめました。
この問題では、花背など左京北部エリアで活動する樋口市議とがっちり連携して取り組んでおります。
ーーーーーーーーーーーーーーー
(とがし)お願いします、私からは、もともと、このあの山村都市交流の森の位置付けは何だったのかということで、それぞれの施設の果たしてきた役割をどう評価するかについてまずお尋ねしたいと思います。
(森林政策担当部長)山村都市交流の森でございますけれども交流の森全体で申し上げますと、森林エリアこれが1000ヘクタールを超える森林エリアと約1・5ヘクタールのセンターエリアですね。今回あのご議論を頂いておりますのが、センターエリアの再生活用というところでございます。まず、センターエリアにつきましては宿泊飲食を提供する翠峰荘、これまで文化協会が運営をしておりました。加えまして、「もくじゅ」(森の工房)という施設は京都森林組合所有の建物でございますけれどもこれは木工体験等の提供。そして、あの、全天候型多目的施設としての森愛館があったということでございまして、これは、交流の森に訪れられるお客様、あるいは地域住民の活動拠点となっているというものでございます。特にあの都市住民の皆さんにとっては森林のレクリエーション憩いの場として活用も頂いてますし、左京北部山間地域の振興拠点として、こうした役割を果たしてきているという認識をしております。
(とがし)山村都市交流の森、今お話あったように山村と都市の交流という点で大変貴重で重要な役割があると改めて私も感じてるんです。というのも、やっぱり森、森林そのものを楽しんでいただく、それは、山登りでできることですけど、しかし、それだけじゃなくてそこが生み出す様々な文化っていうのを体験するっていうこととまあリクレーション兼ねるということを通じてですね。やっぱり、その山の大切さとか森林の大切さとかそれと協調した山村、あるいは、農業にも繋がると思いますけどそういう大切さを実感することができるっていうことで、私はですね、これ、狭い採算だけで測ることができない事業ではないかと考えております。で、あと、その中でもですね、森愛館は、地域の運動会、消防団の訓練、出初式などに使われており地域にとってもなくてはならないものだというふうに考えております。で、主にですね、今、合宿施設として利用されてきた翠峰荘はコロナで利用は落ち込んでたといえばあの森林文化協会の実績とかも見させていただきましても、え~、宿泊者令和元年度で2168人なのに令和2年度はコロナに入って584人ということで少なくなったんですけども、やっぱりそれだけ、非常に大きな役割を果たしているし、そういう施設っていうのがあるからやっぱり森林体験っていうのも安心してできるかなと思います。私もあのいろんなの活動して子どもを連れた活動をとかしているとやり、そういう拠点的なとこで救護的な施設っていうのが、あるかないかっていうので全然違ってくるんで非常に大事だなと思ってます。そういう意味では、施設自身もですね、あの魅力的なものだと思ってます。この森愛館について、やはり、私自身は公の施設として存続させるべきだし、ま、翠峰荘なんかもですね、公の関与を強化することによって存続を図るべきだと考えますけども、その点はいかがでしょうか。
(森林政策担当部長)まず本市の公の施設である森愛館でございますけれどもあの今あのおっしゃっていただいたように今訪れる方々が利用いただける施設として設置をしてまいました。あのしかしながらですね、あの利用者数に関しましてはあの年々減少しております。であの直近の令和3年度で申し上げますと1年間の利用件数が年間で30件と非常に著しく低調であるという状況、それに加えましてですね。あの設置から20年が経過しておりまして、今後まあ改修経費等等多額の経費が必要となるということが見込まれております。で、あの森愛館に関しましては公の施設としての役割、これはここで一旦見直す必要があるということで、廃止をさせていただいた上でですね。あの翠峰荘も含むセンターエリアの他の施設とですね。民間の活力の導入によりまして一体的な活用による再生を進めたいとこういう思いでございます。なお翠峰荘につきましてはあのコロナ禍の影響によりまして、これまで文化協会運営されておりましたけれども、昨年の10月をもって閉館をされておりますので、何としてもまあ一日も早くですね。再開するように取り組んでいきたいとそういうものでございます。
(とがし)まあ、あの、コロナ渦って言うね、私は特殊要因だと思いますし、どのようにね回復していくか、わからないんですけれども、まあ、ただ、やっぱり、そういう施設は必要なものであろうと思います。で、あの、今の話で言うと少なくとも、これ、機能が残るとふうに考えていいのかどうか、ということとあとは土地についてはですね、あの京都市が民有地に設定してる地上権の転貸しによる対応契約として、建物ついては譲渡もしくは貸付するとされてる。で、ただしその案内休憩所やもくじゅについては、活用しないことも可能としているということなんですけれどもこの活用しない場合っていうのはどういう、この、扱いになっていくんでしょうか。
(森林政策担当部長)あのまずはの活用について選択肢を設けているということにつきましては民間事業者に参入いただく参入の障壁を下げるという観点でさせて頂いてるのでものでございます、で、活用しない場合それらがどうなるかという点で、ございますけれども、案内休憩所については文化協会の所有建物、もくじゅにつきましては京都市森林組合の所有建物でございますので、それぞれの団体においてまあの現場の利用継続も含めて検討いただくということでございます。
(とがし)今の基本的なあのその活用、今回募集しようとしてるところがもし活用しない場合であっても、各団体で考えていただく、設置者で考えていただくということだという話なんですけど、でもあのえーま現在ですね、あの森愛館と、今閉鎖中ですけども翠峰荘、運営という点では森林文化協会がされてるということですけどもまぁやはりこれ、この施設っていうのはこのエリアの中でも非常に重要な拠点的なところかなと思っております。それらを運営するのにかなりの大きなウエイトをおいてこの森林山村の振興を図るということで公益財団として活動されてるんだと思っているんですけどもこの認識いいのかどうかっていうことと、やはり、京都市も理事として関与されてると思うんですけども、あの私はですねま京都市の支援の在り様によっては十分ですね、この公益財団法人のこの京都市森林文化協会の、お力でやっていけるんじゃないかという風に思うんですね。で是非ですねあのこの大きな意味で山村と都市っていうのは相互に支え合う関係であるべきだと思いますしどちらも大事な存在であると思いますので、その意味でもやはり、京都市の関与を強めるって事を考えて頂きたいんですけどもま、これは財政的あるいは人的も様々なあの面から関与を強くして、今いろんな事業を委託れていると思いますけどもそんなことも含めて取り組んでいただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
(森林政策担当部長)まず、公益財団法人京都市森林文化協会の役割でございます。同法人は公益事業と収益事業を持っておられまして公益事業についてはあの花背地域のみならずですね、左京北部山間地域のみならず京都市全域の森林保全活動に資する活動を公益事業として取り組んでおられるところでございます。我々としても広くわれわれの事業と連携して取り組みをいただいているところでございます。一方で収益事業これはの翠峰荘の事業になるわけでございますけれども、これは財団としてそこを収益施設として、あの基本的には独立採算制で取り組まれるべきものでございまして、この間、非常に厳しい経営状況が続いてる中で、さらにはコロナ禍によって閉館を余儀なくされたものというものでございましてこの公益事業に対して京都市が直接的な財政支援をするという考えはございません。ただあの先ほど来申し上げておりますよう、非常にまた左京北部山間地域の重要な拠点であるということまた市民にとてもあの森林文化への理解を深めていただく大切な施設であるという観点からですね。同協会と京都市、それから地域の方あるいはまた左京区役所等々の関係行政機関と連携をして再生を目指していこうという取り組みであるというものでございます。
(とがし)再生目指していくっていう中でそこに民間事業者入ってただこうという話だと思うけどその場合あのえー今日これ見てましたらの選定されましたらその後協議していくっていう話なんですけどもその選定された後のその協議の中でそういうこうなんか裁量の働く範囲っていうのはあるもんなんでしょうか。
(森林政策担当部長)裁量というのが民間事業者の裁量という点で申し上げましたら民間事業者の自由な発想によってですね。あの集客であるとかあるいは地域との連携であるとかいうことに取り組んでいただくというものでございますし、またの選定の要領ですね。地域の住民とですね、定期的な意見交換であると協議の場であるとか、具体的に申し上げますと地域の皆さんが望んでおられるアイディア等々をですね、あの具現化していくような取り組みについても募集要項上に定めさせて頂いているところでございます。
(とがし)それですね、最後にしますけれども、あの今回ですね、あの条例の廃止っていうのがこれを出されてるんですね、でもちょっと言ったように思うんですけど、やはり、その、これからどうなるかっていうのはまだ募集してでまた募集した後にで選定されるかどうかも分からないし洗練されたとしてもその後協議して一体その協議はどうなるかもわからないという状況の中でありその条例を廃止しましょうっていうのはちょっとやり乱暴ではないかと思うしあまりにも拙速だと思うんですけどこの点いかがでしょうか。
(森林政策担当部長)はいあの先ほども森愛館の状況を少し申し上げましたけれどもあの申し上げました通りも極めて利用状況が低迷をしているという状況と今後の回し施設老朽化を見据えますと費用対効果と申しますかそうした点でも公の施設としては廃止をせざるを得ないという判断に立っているものでございます。で、その上で、センターの他の施設との一体的な活用によって新たな価値を見出して再生をしていきたいという考えでございます。あの11月市会にはですねあの同施設の廃止条例を提案してご審議いただければというふうに考えてるところです。
(とがし)費用対効果っていう考え方自身がちょっとこの問題についてはおかしいんじゃないかと思ってましてねーやはり最初冒頭述べましたようにこの山村と都市の交流にとって
大事な施設であるということでねまた地域でも大事な施設だという状況の中でそれを、とにかくあの、これは、廃止はするだけで廃止で決定だという風に進めていくっていうのはちょっとやっぱりそこはその趣旨から考えてその、おかしいんじゃないかなと思いますし様々なそういう公的な施設に対して支援入れたりとかいうのは京都市の歴史の中でもある話ですのでその点ではやはりこれはちょっと見直していただかなければいけないじゃないかなというふうに思っております以上です。
(更新日:2022年11月20日)

2022年9月30日京都市に対して物価高騰・コロナ対策等申し入れる日本共産党京都市議団
市長に対して、新型コロナ対策および物価高騰対策についての緊急申し入れを行いました。
——————-
京都市長 門川大作様
新型コロナウイルス感染症対策及び物価高騰対策についての緊急申し入れ
2022年9月30日
日本共産党京都市会議員団
団長 井坂博文
アベノミクスとして進められてきた「異次元の金融緩和」政策による異常円安により、一層深刻な物価高がもたらされ、市民の暮らしと営業に深刻な影響が出ています。
京都市においても、6月補正予算で中小企業等総合支援補助金を創設するなど、コロナ・物価高騰対策の取り組みが行われていますが、全く間に合わない状況となっています。現在、国においてあらたな補正予算が検討されているとのことですが、こうした予算も十分に活用しながら、本市としてもあらゆる手立てをつくして、市民生活と営業を守る取り組みが求められています。
また、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの冬の感染拡大への備えを今のうちからしっかり立てることが、市民のいのちとくらし・営業を守る上で極めて重要です。「全数把握見直し」が行われた状況の中で公衆衛生体制の再構築が急務となっています。
よって、国が検討している補正予算も十分に活用し、京都市として下記の通り取り組むことを申し入れます。
記
一、 現在準備中の国の補正予算を最大限に活用し、物価高に苦しむ市民と事業者への支援策を充実させること。
・食料支援の活動などへの支援を拡充・創設すること。
・小中学校における学校給食費の無償化を行うこと。
・上下水道料金の減免制度を創設すること。
・医療、介護、障害、保育などの施設や公衆浴場に対するエネルギー・食料品価格の高騰分などの支援を行うこと。
・エネルギー価格の高騰の影響をうけたすべての中小・小規模事業者を対象にした支援金制度を創設すること。
・中小企業・小規模事業者における賃上げ環境整備のための支援制度を創設すること。
・コロナ特例等の融資制度の返済にあたっては、市として利子補給や保証料補給などを行うこと。追加融資についても柔軟に対応すること。
・農業資材の価格高騰対策として農業者への支援を行うこと。
・既存住宅省エネリフォーム支援補助金を復活すること。
一、 新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザの冬の感染拡大に備え、医療提供体制と保健所体制を強化すること。
・一ヶ所に集約した保健所機能を各行政区・支所にもとし、公衆衛生体制の再構築を図ること。正規職員の増員をはかり、保健所体制を抜本的に強化すること。
・全数把握の「見直し」が行われたが、フォローアップセンターへの登録者を含むすべての感染者の命と健康に行政として責任をもって対処できる体制をとること。
・早期発見・早期療養により感染拡大を抑えるため、誰でもどこでも何度でも無料でPCR検査を受けられる体制を充実させること。
・高齢者施設、医療機関における定期的なPCR検査を実施すること。
・本市において、大学や民間検査機関などと協力し、迅速なPCR検査を実施できる体制を構築すること。
・第7波の教訓を踏まえ、京都府入院待機ステーションを臨時医療施設として機能させられるような体制強化等を京都府に求めること。
・高齢者インフルエンザ予防接種の負担増を撤回すること。
一、 国に対し、補正予算の総額を大幅に増やすよう求めること。
以上
(更新日:2022年09月30日)
9月26日月曜日。
朝から京都市の第一市場を視察。一期工事を経て運用一年を迎え、また、整備中の見学ルートや第二期工事の様子(可能な範囲で)を確認するために党市議団で視察に。現場で市職員さんから詳しく説明を聞きました。
実際運用するといろいろな問題が生じ一つ一つ改善しているとのことでした。当局からのこうした説明と、市場関係者から直接聞き取る声、それぞれ重要で、党市議団としても今議会にかかっている契約変更議案の審議にいかしたいと思っています。動画が普及したとはいえ、現場にたってこそわかることが多く、やはり、百聞は一見に如かずです。
(更新日:2022年09月28日)

2022年9月27日、京都市役所前での行われた国葬反対の抗議活動に参加する党市議団
#国葬反対
市議会では産業交通水道委員会およびまちづくり委員会が開会中でしたが、なんとか、昼休みの国葬反対の市役所前の行動に私も参加しました。民主主義や法治主義、立憲主義を破壊してきた安倍晋三氏、統一協会の広告塔として露骨にふるまって自民党内でも統一教会票を差配したとの疑惑が濃厚な安倍晋三氏・・・この人物をまつり上げるために莫大な税金が使われ、弔意が強要される・・・とんでもないことです。怒りを込めて写真をアップ!!

2022年9月27日国葬に抗議する党市議団と市民@京都市役所前

2022年9月27日国葬に抗議する市民@京都市役所前

2022年9月27日国葬当日に京都市役所に半旗が掲揚された
(更新日:2022年09月28日)
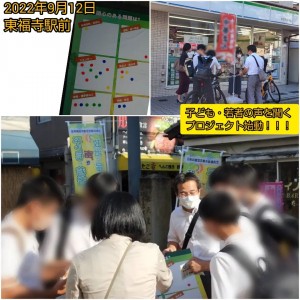
東福寺駅で中学生や高校生の声をきくシール投票・アンケートをする京都市議団
子ども・若者の声を政治に届けるプロジェクト始動!!
子どもの権利条約では、大人に対して、子どもたちの声を大切にあつかい、子どもたちにとってよりよい日本・世界に変えていく努力を求めています。日本の国で最も大切なルールである憲法でも一人ひとりを大事にしなければならないと書いています。そこでその第一歩としてアンケートを始めました。
ジェンダー平等
「今のうちにジェンダー平等にしといた方が、自分が働きだした時によいと思うから」(高校生)
働き方・賃上げ
「就職したときのことが心配なので」(高校生)
平和・外交
「中国の動きが大変不安だけど、お互いに軍備を持たない状態にしてこそ平和になるし一番の理想であり、その理想も捨てたくない。世界で唯一の被爆国の日本だからできることもあるんじゃないか」(中学生)
学費・奨学金
「うちの家、あんまり余裕ないので」「今年受験なんですごく関心あります」(高校生)
「無駄遣いが多いらしいと聞いています。もっと子育て支援に力を入れないと」(高校生)
とっても頼もしい次代の担い手たちの声をうけとめ、一歩一歩実現へ力をちくしていきたいと思いました。
(更新日:2022年09月12日)

国葬に関する申し入れを行う日本共産党市会議員団
9月8日、「国への「国葬」中止要請と、弔意を強制しないことを求める申し入れ」を京都市に行いました。下記は、その本文です。
================
国への「国葬」中止要請と、弔意を強制しないことを求める申し入れ
日本共産党京都市会議員団
団長 井坂博文
岸田政権は、安倍元首相の「国葬」を閣議決定し、9月27日に行おうとしている。「国葬」強行は、憲法14条「法の下の平等」、憲法19条「思想及び良心の自由」に反するものである。戦後「国葬令」は失効しており、実施の根拠を定めた法律は存在しない。法的根拠のない「国葬」を一片の閣議決定により強行することは、法治主義を壊すものであり、ましてや、弔意の強制は許されない。政府は2億5千万円としていた経費総額が16億6000万円になると発表した。積算根拠が示されておらず、更に費用が膨らむ可能性もある。国民世論においても、世論調査で「反対」が「賛成」を上回っており、憲法違反の「国葬」に国民の血税を使うなどということは民主主義国家においてあってはならない。よって、下記の点を強く求める。
記
一、安倍元首相の「国葬」に反対し、国に中止を求めること
一、市長、副市長は「国葬」に参列しないこと
一、市庁舎・学校等への半旗・弔旗掲揚は行わないこと
一、市職員並びに、学校・保育所・幼稚園などの現場において、弔意を強制しないこと。黙祷の協力よびかけを行わないこと
以上
(更新日:2022年09月10日)